教師の「ポジショニング」アップデート|“子供の中に入る”立ち位置を中核に【中野裕己の授業技術アップデート02】

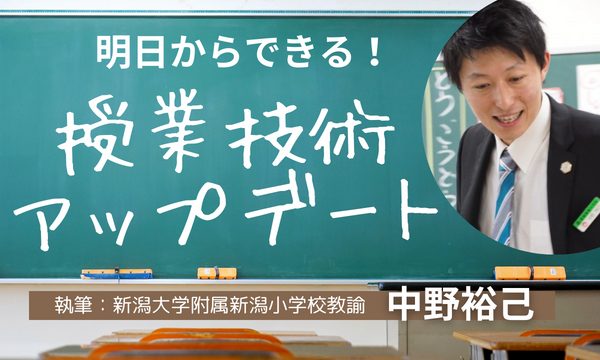
『小学校国語授業アップデート』著者で、国語科(読むこと)、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による新連載!「発問」「教師の“ポジショニング”」「価値付け言葉」「問い返し」「ICT活用」「話合い活動」「授業準備」の7つの柱をテーマに、“明日から”できて“ずっと”役立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。
第2回目のテーマはポジショニング、《子供の学びを「支える」教師の動き》です。
執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己
目次
「教師の“ポジショニング”」とは
連載2回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。
2024年となりましたね。本年も、先生方と教室の子供たちのお役に立てるよう、“明日からできる!”授業技術を紹介してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回の授業技術は、教師の“ポジショニング”を取り上げたいと思います。発問と比べてあまり馴染みのない授業技術のため、少しだけ解説をしたいと思います。
この教師の“ポジショニング”を意味する『居方(いかた)』は、佐藤学氏(東京大学名誉教授)の造語です。佐藤氏は、著書『教師花伝書―専門家として成長するために』(小学館)の中で、「教師の居方(ポジショニング)」について、以下のように述べています。
「『居方』というのは私の造語である。この言葉で私は、教師の立つ位置の取り方とその立ち位置からの子ども一人ひとりとの関係の取り方を示している。したがって、『居方』は『ポジショニング』と言い換えてもよい」
出典:佐藤学『教師花伝書―専門家として成長するために』, 小学館, 2009年4月, p.34
この佐藤氏の考えに基づきながら、日頃私が意識している教師の立つ位置の取り方を、子供との関係の取り方に結びつけながら説明していきます。
【Before】漫然とした教師の“ポジショニング”
まずは【Before】ということで、アップデート前の教師の“ポジショニング”——つまり「漫然とした」立つ位置の取り方——をいくつか挙げてみたいと思います。
【Before】①黒板の前に立つ

この立ち位置は、「漫然とした」という表現が最も当てはまりやすいポジションです。多くの先生方が、黒板の前を定位置と考えておられるのではないでしょうか。気をつけておきたいのは、この立ち位置は、「教師―集団」という関係の取り方になりやすい立ち位置だということです。子供にとっては、なんだか圧を感じたり、声をかけづらい存在として映ったりすることがあります。
【Before】②座席の間を周回する

いわゆる「机間指導」の際の立ち位置です。教師は、「個とつながる」という意図をもって、座席の間を周回します(しているはずです)。しかしながら、立ち止まることができなければ、それはただ周回しているだけ、つまり「漫然とした」周回になってしまうでしょう。ただし、子供にとっては、教師との物理的な距離が近くなる分、声はかけやすくなるかもしれません。
①、②のいずれの立ち位置も、「漫然とした」ものであるため、佐藤氏の述べる教師の“ポジショニング”としての機能はありません。つまり、子供との関係の取り方が頭にない立ち位置になっています。

