提言|大村龍太郎 各自治体の教育委員会、学校長(管理職)がすべきことは? 【不登校、コロナダメージを克服するために 今こそ、学校全体で「学級経営」を! #02】
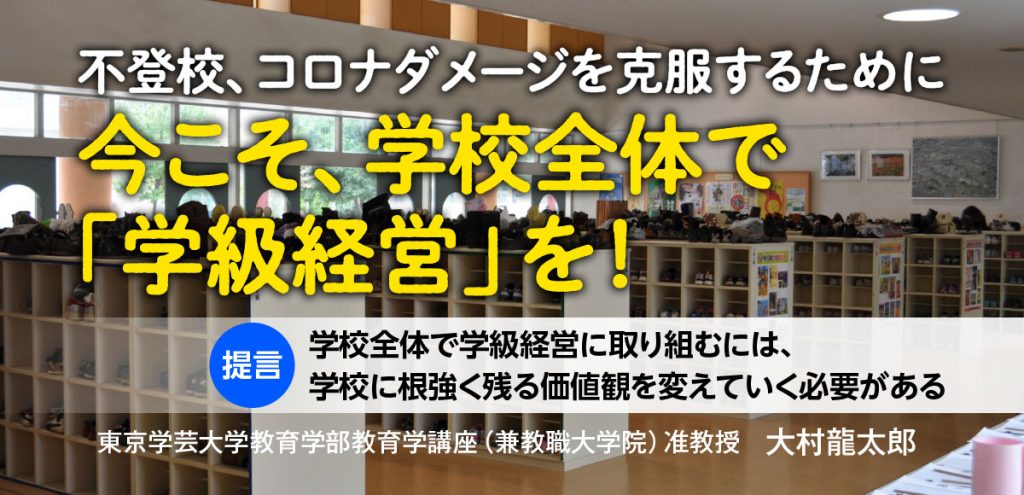
コロナ禍をきっかけに、小中学校では不登校の児童生徒が急増しています。原因は子供によって様々だとは思いますが、子供が友達とうまく関われなくなり、学校が居心地の良い場所ではなくなっていることが、一因だと言えるのではないでしょうか。そこで、もっと居心地の良い学級、学校にするために、学校が今、すべきことは何だろうかと考えたときに、たどり着いたのは学級経営でした。今、求められる学級経営の在り方について考える4回シリーズの第2回です。今回は、学校全体で学級経営に取り組むことの重要性と、各自治体の教育委員会や校長がすべきことを、東京学芸大学の大村龍太郎准教授に語っていただきました。
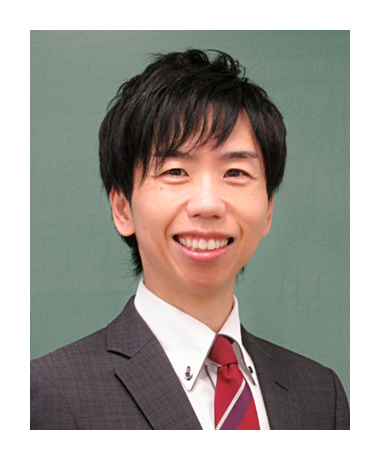
大村龍太郎(おおむら・りょうたろう)
1977年生まれ。福岡県筑豊地区出身。福岡県小学校教諭、福岡教育大学附属小倉小学校教諭、福岡県教育センター指導主事等を経て現職。日本学級経営学会理事。一般社団法人STEAM JAPAN理事。専門は教育方法学。「教科等固有の価値と教科等横断的・汎用的な価値の両者を重視した学習者主体の授業研究」及び「互いの自由と共同体の価値を実感する学級経営研究」を関連的・複合的に研究している。著書に『クラウド環境の本質を活かす学級・授業づくり』(明治図書出版)がある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全4回予定)
●提言|赤坂真二 不登校急増の今、学校が取り組むべきことは?
●提言|大村龍太郎 各自治体の教育委員会、学校長(管理職)がすべきことは?(本記事)
目次
今、学級経営に取り組まなくてはならない理由
今は学校の存在意義、 つまり、子供が学校に通う意味が問われる時代になっています。
子供が学校に通うのは何のためでしょうか。勉強するためでしょうか。それだけなら、今はYouTubeなどで分かりやすい学習動画もたくさんありますから、それで学べばよいことになります。学校に行かなくても学習する機会が担保されるのであれば、「学校に行かない」という選択をする人が出てきてもおかしくないでしょう。
そのような中でも学校に通う意味は、何より人と対面で関わることでその豊かさや難しさを味わうこと。配慮を学ぶこと。互いを認め合い、自他を大切にしながら関わり合って共に学ぶ心地よさを感じたり、その力を育んだりすることではないでしょうか。なぜなら、 人間は社会的な生き物であり、単体で生きていくことはできないからです。社会で幸せな人生を生きていこうとすると、必ず誰かと関わったり支え合ったりする必要が出てきますし、そのつながり自体が幸福を感じるかけがえのないものです。
にもかかわらず、今はインターネットによるエンタメや宅配サービスの普及などで、家にずっと籠もって過ごしてしまうこともできやすく、便利な反面、孤立化を助長しやすい社会になっています。そういう世の中だからこそ、子供が1日の大半を過ごす「学級」において豊かに過ごし、より良い人間関係や集団をつくる力を育むことの重要性が増していると言えます。人と関わり合いながら社会生活を豊かにしていく力こそが「生きる力」であると考えると、今、子供に生きる力を育むためには学級経営を重視しなければならないはずなのです。
学校全体で取り組むことの重要性
ただし、これから学級経営を重視するのならば、これまで個々の学級担任に任されてきたものを、学校全体で取り組むことが大切になります。その理由は2つあります。
1つ目は、学級における責任のすべてを担任一人に負わせることにはもう限界が来ているからです。
そもそも学級という枠組みは、生物学的には異常なコミュニティです。同じ年齢の人だけの集団は、世の中に存在するはずのないものです。生まれたばかりの子供がいて、少し大きくなった子供がいて、働き盛りの人がいて、高齢の人もいる、それが世の中にある普通の集団です。地域にも、会社にも、いろいろな年代の人がいるのが普通です。そうでなければ種の保存や継続ができるはずがありません。
しかし、学校では、大体同じぐらいの理解力であろうと思われる同年齢の子供たちを集め、同質性の高い集団を意図的につくってきました。これは世の中に自然発生するコミュニティとは違いますから、配慮をしないと問題が起こったり機能不全になったりします。いじめが起きやすくなったり、優劣を異常に気にしたりするようなことがその典型です。それなのになぜ学校は長年、この異常なコミュニティを継続させてきたのかというと、学級担任の指示で、同じことをさせることを主な目的としてきた「観」が残り続けたからです。
かつての高度経済成長期のように、工場で同じ動きを同じようにする労働者の方が大量に求められていたようなころには、みんなで同じことを同じように同じペースでやることには一定の意味があったでしょう。
しかし、今は多様性を大事にする時代です。一人一人の個性が大事であり、一人一人違っていいとされています。同じことを同じようにさせるために同年齢の子供を集めた異常なコミュニティの中で、一人一人の個性を大切にしなさい、自主性を大切にしなさい、インクルーシブ教育を進めなさいと言われるわけです。同質性を高めるためにつくられたシステムはそのままに、多様性を具現化しようとするのは、矛盾していると思いませんか?
しかも現実的に考えて、担任一人で、30人の30通りの個性に合わせて指導することなど不可能でしょう。もちろん、子供たちに関わる中心が学級担任になるのはシステム上、仕方がないことですが、一人一人の個性や多様性を大切にしながら成長を促すという至難の技を日々要求するうえに、学級のすべての責任を一人の担任に負わせるようなことに限界があるのは容易に想像がつくはずです。
そもそもそれぞれの学校には学校教育目標があって、その実現のために各学年の目標があり、カリキュラムを編成し、実践が行われています。つまり、子供は本来、学級だけでなく学校全体で育てるものです。そのことをふまえても学校全体として教職員が互いに支え合って学級経営をしていくという方針をしっかり打ち出す必要があります。そうしないと、 現状ではいつ、どの学級が機能不全になってもおかしくない状態なのです。
そのことと関連して、学校全体で学級経営に取り組む必要があると考える理由の2つ目は、子供の成長の「連続性、系統性をふまえる」という側面です。小学校の場合であれば、学校や子供の実態をふまえて、1年生から6年生まで、それぞれの段階で何を大切にして、どんな人間関係形成力を育み、どんな学級をつくることができる子供を、どこまで目指すのか、すべての先生が系統性を意識して共通理解する必要があるはずです。それができていれば、どの学年の先生も、自分の学級だけでなく、他の学年・学級の子供に対しても共通の視点でその段階に適した支援や称賛ができるようになります。
例えば、「1年生では、いろんな友達と1対1で関わるときになかよく一緒に活動したり優しい声かけをしたりすることができることを重点にしよう」「2年生では、数名の集団で活動するときにもみんなで一緒になかよく活動できるようにすることを重点にしよう」など、その段階で特に大切にする成長の姿を校内全体で検討して共通理解をするわけです。それができていれば、 6年生の担任でも、低学年の子供を見かけたときに、その視点で褒めることができます。子供たちを学校の教職員全員で伸ばすための共通理解です。もちろん、特別な配慮を要する子供の情報共有も含めてです。

