小6|画像生成AIを活用した図画工作科の鑑賞授業 【「生成AI利用ガイドライン」徹底解説 特別編】

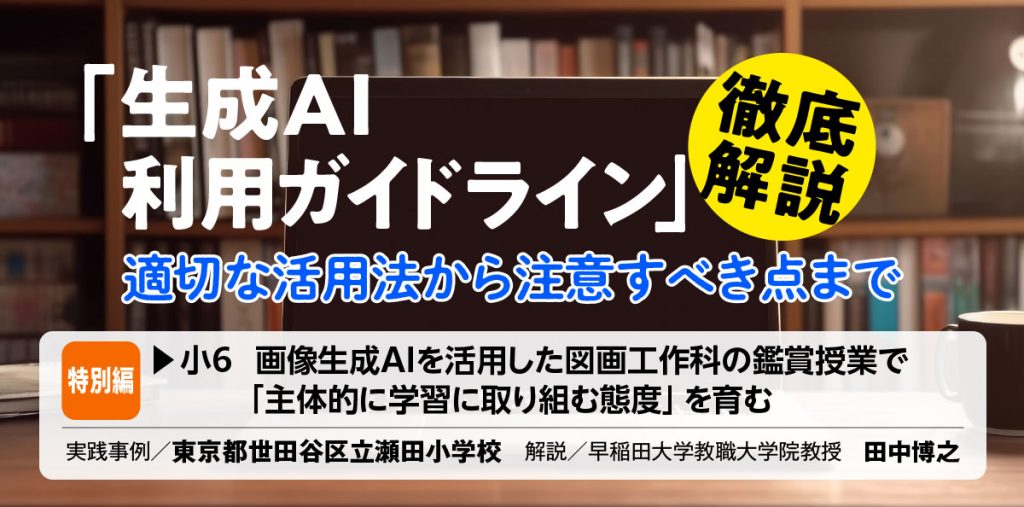
この特集ではこれまで、文部科学省が7月に公表したガイドラインの内容を5回にわたって解説してきましたが、実際に、授業にどのように取り入れていくのか、気になっている先生方も多いことでしょう。そこで今回は【特別編】として、東京都世田谷区立瀬田小学校(日高玲子校長、児童数805 名)で行われた、おそらく小学校としては日本初ではないかと思われる、画像生成AIを活用した6年生の図工科の鑑賞授業の実践例をご紹介します。この授業は早稲田大学の田中博之教授の助言を受けて行われたものであり、最後に田中教授による解説があります。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全5回予定)
●解説|田中博之 生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方<子ども用チェックリスト付き>
●解説|田中博之 学校で使用する前に確認したい4つのポイント
●解説|田中博之 生成AIの不適切な使い方と適切な使い方
●解説|田中博之 生成AIの活用で育成したい資質・能力とは?<子ども用の自己評価シート付き>
●解説|田中博之 AIリテラシー教育をどのように進めればいいのか?
●<特別編>小6|画像生成AIを活用した図画工作科の鑑賞授業(本記事)

目次
生成AIと図工科
「生成AIを授業で活用してみたい」と思ってはいても、なかなか一歩が踏み出せない学校が多いのではないでしょうか。今回、その一歩を踏み出したきっかけを、日高校長に聞きました。
「もともと世田谷区は子供たちのタブレットの活用を推奨していますので、生成AIを取り入れてみたら面白いのではないかと思いました。子供たちは、こうしてみたい、ああしてみたいという願いや思いをたくさん持っていると思うのです。ただ、それを表現しようと思ったら、勇気が必要だったり、方法が見つからなかったり、時間がかかってしまったりします。生成AIは、その手助けになるのではないかと考えました」
授業者の中根誠一主任教諭は、教職10年目、図工科の専科教員です。「図工科はアナログなイメージが強いのですが、活用場面によっては、意外とデジタルとの相性がいいと感じています」との思いがあり、今回、画像生成AIを使った授業にチャレンジしたそうです。
日高校長は「生成AIを使うにあたり、誰かを傷つけること、嘘やごまかしにつながることは、あってはいけないと思っていました。もしも国語や算数だったら、もっと色々と考える必要があったと思うのですが、まずは図工ということで、図工科の鑑賞の授業を、中根主任教諭が力を入れて進めていたのは知っていましたので、それに画像生成AIの力がどんな風に加わるのか、むしろ興味の方が大きかったです」と語ります。
◇導入10分
今回、授業を行ったのは、6年4組です。3時間目と4時間目の2時間を使って行われました。
授業は、鑑賞についての説明から始まりました。
中根主任教諭「作品をつくることも大事ですけれど、作品を見て考えたり、感じたりしたことをみんなで話し合うのはとても大事なことです。これを鑑賞といいます。今日は『美しい風景』とはどんなものなのかを話し合って、みんなの『美しい風景』を形にして、鑑賞したいと思います」
この日のテーマは、「美しい風景」です。
この時点で、具体的に何をするのか、子供たちは知らされていません。
中根主任教諭が、「先生にとって美しい風景とは何かと考えて、10秒ぐらいでつくってきました」
そう言いながら、ディスプレイに画像を提示しました。
山があり、空には鳥が飛んでいて手前には花がある画像です。

子供「10秒ぐらい?」
子供「これが?」
子供「えー?」
子供「もしかしてAI?」
中根主任教諭「そうそう。AIでつくりました」
ここで画像生成AIについて説明します。
中根主任教諭「今、世の中ではいろいろな技術が進んでいて、AIと呼ばれる人工知能が身近になりつつあります。そこで、今日は画像生成AIのアプリを使って、みんなが思う『美しい風景』をつくっていきます」

