「子供たちのために何かできないか」という初心に返る 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第32回】
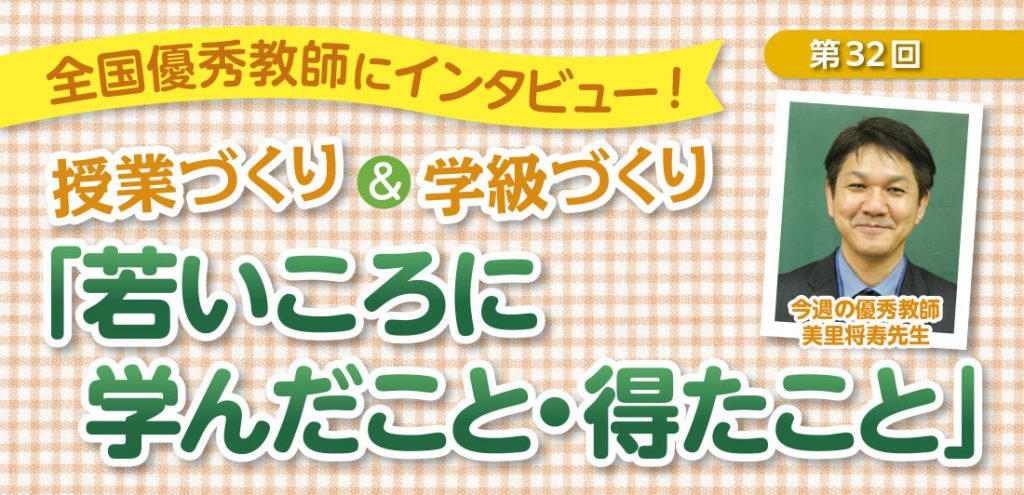
今回からは、沖縄県で算数を中心に授業改善に取り組み、前任校では授業改善アドバイザーを務め、現在は浦添市教育研究所の運営委員も務める美里将寿主幹教諭が、教師を志し、講師として教師の楽しさや苦労を知った、ごく若手の頃までの話を紹介していきます。

目次
「今は自信をなくしているだけで、やっぱり子供たちの力になりたい」
私は高校時代に進路を決めるときには、特に教員を目指していたわけではありませんでした。親は県の職員をしており、「経済的に安定しているから公務員になれ」と言われていたのですが、それに対する反発心もあって、素直に「じゃあ、公務員(教員)になろう」とは思えなかったのです。その気持ちが変わって、「教員になろう」と思うようになったのは、受験に失敗した後のことです。
受験がうまくいかず、「自分はついていない」などとも思っていましたが、よくよく自分の環境を顧みると、本当に恵まれているなと思いました。苦労せず、浪人をさせてもらっているわけで、周囲には苦労して浪人をしている人もいれば、経済的な理由で大学進学を諦めて働いている人もいるわけです。もちろん、家庭環境に恵まれず、もっと小さい頃から苦労している子供もいます。それで、「子供たちのために何かできないか」「力になれるような仕事につきたい」と思うようになり、小学校教員養成課程のある大学に行こうと考えました。とにかく、子供たちの成長を手助けできるようになろうと思ったのです。

それで、地元大学の教育学部を受験して入学したのですが、先のような理由で教員を目指したため、「特にこの教科を!」というような教科への思い入れがありませんでした。ですから、専門は教育学を選び、入学後もとにかく教員になるために単位を取ればいいという、のんきな感じだったのです。ただ、3年でゼミを選んでからは、子供たちと関わる機会も増えました。社会教育のゼミに入ったのですが、そのゼミの教授が私たち学生を連れて、地域の子供向けにキャンプを実施したり、レクリエーションを実施したりするなど、多様なフィールドワークをしていたのです。公民館などで行われるイベントの実習を通じて、子供たちと多様に関わる機会をもてましたし、私の母親が宮古島の隣の伊良部島の出身で、その母の地元の公民館での実習で、学童のキャンプのお手伝いをするような経験もしました。それで、改めて子供たちと関わることの楽しさや大切さを感じるようになったのです。
その気持ちをもって、3年次には教育実習にも行ったのですが、その経験はひと言で言えば、挫折でした。附属小学校へ行って授業をするのですが、1クラスに7名の実習生がいて、協力しながら一緒に取り組むわけです。指導案も協力して作るわけですが、力不足で睡眠を削って夜中まで指導案を書くこともありました。そうやって一生懸命に考えて授業をやっても、全然思うような授業にはならなくて、子供も乗ってきてくれないので、「教員に向いていないのではないだろうか」と思うようになったのです。
それで大学卒業後は、社会教育ゼミの教授のつながりもあり、那覇市教育委員会の関係機関の青少年健全育成市民会議で事務職として働きました。友達の中には小学校の講師をやりながら、次年度の受験をする者も少なくなかったのですが、教育実習時のこともあり、すぐに教員(講師)として学校で仕事をする自信もなくて、社会教育施設の臨時の事務職員として働かせていただくことにしたのです。そこで、少年の船事業の企画だったり、成人式の企画運営に携わったりしながら1年間過ごしました。この年、社会教育の仕事を通して多様な人と関わりながら、改めて「自分は何をしたいんだろう」と考え直したら、「今は自信をなくしているだけで、やっぱり子供たちの力になりたい」と思ったのです。そこで翌年は、小学校で臨時講師をしながら教員採用試験を受けようと決めました。

