県内すべてのクラスで生徒の探究心を刺激する理数授業を目指す 【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #08】
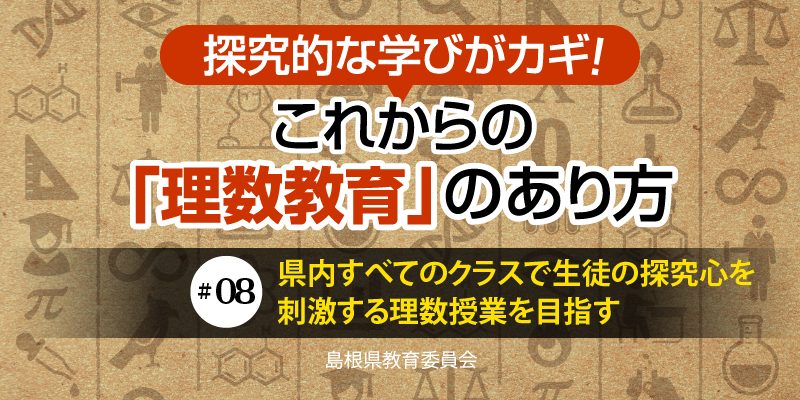
島根県が2022年より取り組んでいる「中学生の理数探究心育成事業」。この事業の目的は中学校の理数系教員の授業力を向上させることを通じて、中学生の理科・数学に対する探究心を刺激し、結果として高等教育段階での理系選択者を増加させること、そしてゆくゆくは同県で不足している産業人材の育成につなげることにあるという。今回は同事業の手応えや、関連するその他の学力育成事業について、島根県教育センターの福島章洋氏と島根県教育庁教育指導課の小室淑子氏、橋本憲氏に聞いた。

島根県教育委員会
島根県は、2020年に県の教育振興基本計画「しまね教育魅力化ビジョン」を策定し、県をあげて教育の魅力化に取り組んでいる。記事内に登場する「しまねの学力育成推進プラン」は、「しまね教育魅力化ビジョン」に掲げる学力育成を、より実効性のあるものとするため、2021年に策定された。
島根県庁舎(撮影者:SATOH PHOTO)
この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の8回目です。記事一覧はこちら
目次
中学校の理数系教員の授業力を向上させ、生徒の理数探究心の高揚を図る
2022年にスタートした「中学生の理数探究心育成事業」は、島根県教育委員会が2021年に策定した「しまねの学力育成推進プラン」の一環として展開されているものだ。中学校の理数系教員の授業力向上を核とした取組で、主管は、県の方針に基づきキャリアステージに応じた教職員研修を行う島根県教育センターが務めている。
「島根県だけのことではないと思いますが、本県では以前より、高等学校に入学後、理系に進む生徒が少なく、その結果、産業人材が慢性的に不足するという課題を抱えていました。そこで中等教育段階において、もう少し理科や数学に対する興味を高められないかと考えたのが、この取組の始まりでした」(福島氏)
1年目は、県内に5つある教育事務所管内から、教職経験が5年以上ある中学校の数学科および理科の教員各1名に参加してもらい、全10名による「中学校数学理科教員リーダー育成研修」を年6回にわたって実施したという。
第1回は、事前講義で、いま求められている数学、理科の授業のあり方について学んだ後、島根大学教育学部附属義務教育学校の授業を参観。さらに参加者同士で単元構想する際に大切な視点について協議を行った。
「授業で子どもたちの好奇心を揺さぶり、興味関心を高めるためには、単元導入時の工夫が重要だと言われていますが、これまでは一部の教員を除き、その意識が十分とは言えなかったように思います。結果、主体的・対話的で深い学びになりにくいという課題感を持たれている学校が多く、今回の『中学校数学理科教員リーダー育成研修』でも、そこにフォーカスを当てることにしました」(福島氏)
オンライン研修となった第2回は、半日かけて、各自が1時間の授業の具体的な構想を練り上げ、第3回で自校で授業を展開。指導主事が各校を訪問して、助言を行った。
第4回は、参加者同士で互いの授業を見合って学ぶ場を設定。第5回は再び、オンラインで授業づくりに取り組み、このときは、国立教育政策研究所の調査官を招いて、理科好きな生徒の育成につながる探究的な授業についての講義も実施された。
そして第6回は、参加者たちが1年かけて作り上げた授業を公開するとともに、2年目となる今年度に実施中の「授業力向上研修」で活用するため、授業の収録が行われた。

オンラインを活用し、全中学校の理数系教員を対象にした悉皆研修を開催
2年目となる今年度は、県内の中学校すべての数学科および理科の教員を対象にした「授業力向上研修」を、3回にわたって実施している。
「教員不足の状況が続いている中、これまでは悉皆研修を行うことが難しく、県としては『中学校数学理科教員リーダー育成研修』後の展開にあまり関与してきませんでした。しかし今回はオンラインを活用し、時間帯も6時間目にあたる15時ごろに設定。教員の負担をできるだけ軽減するように心がけ、『中学校数学理科教員リーダー育成研修』の参加者にも密に関わってもらいながら、無事すべての数学科及び理科の教員を対象にした研修を実施するに至りました」(福島氏)
第1回は、前年度の『中学校数学理科教員リーダー育成研修』で収録された授業動画を視聴した後、中等教育段階におけるこれからの理数教育のあり方について、参加者間で協議した。第2回は、少人数のグループに分かれて授業づくりを実施。『中学校数学理科教員リーダー育成研修』同様、子どもが自ら考えたり、解決しようとする意欲を引き出せたりするような単元導入の工夫を目指したという。今年度中に、第3回として授業研究の実施報告と、各自による振り返りを行う予定だ。
「授業力については、一度や二度研修を行っただけですぐに向上するものではないので、手応えについて語るのは時期尚早だと思いますが、単元導入が大事だという教員たちへの意識付けはしっかりできたと感じています。また、本県には小規模校が多いのですが、担当が一人で、これまで教科の悩みを相談できずにいた教員からは、研修のおかげで思いを語り合える仲間ができたと、取組を評価する声が寄せられています」(福島氏)

「中学生の理数探究心育成事業」は当初、「授業が変わらなければ子どもも変わらない」という理念のもと、授業力向上を核とした2か年計画で進められてきたが、ここに来て、子どもたちの心にダイレクトに火をつけるような施策もまた異なる効果を生み出すのではないかという仮説のもと、事業の延長を決定した。3年目となる次年度は、夏季休暇などを活用し、大学等の協力も得ながら、生徒たちが数学のおもしろさに気づいたり、理科の実験で感動したりできるような特別講座の開講を予定している。
島根県教育センターでは、常々、求められる資質・能力について一方的に研修を行うのではなく、教員自身がこれからどんな力をつけたいのかを丁寧に引き出しながら研修を進めていく工夫をしており、内容についても、また「受講者の想いに寄り添う」という部分でも、今回だけが特別という認識はないそうだ。ただ、コロナ禍で広がったオンライン研修を効果的に活用できたことで、都市部から離れた地域や離島の教員にも広く遍く、県が推進するビジョンやプランを示せたこと、さらには今回の「中学校数学理科教員リーダー育成研修」のような少人数を対象にした研修でも国立教育政策研究所の調査官による講義を実施できたことなどは、良かった点として評価しているという。

