年35時間のサイエンスタイムで実験教室などの体験型授業を実施 【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #04】
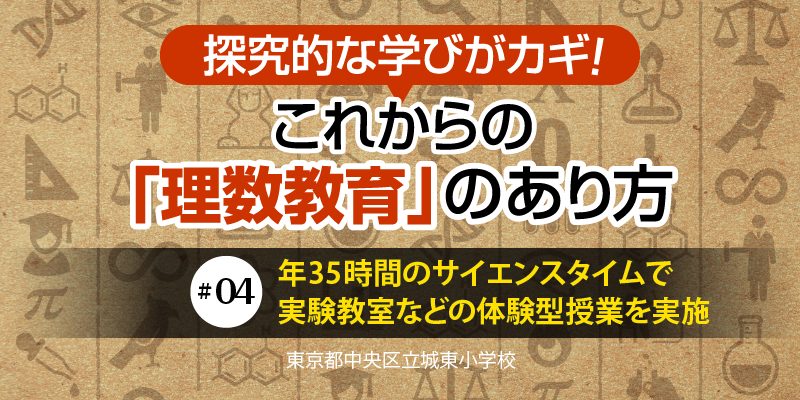
東京駅八重洲口の向かい側、高さ240m、45階建ての複合ビル「東京ミッドタウン八重洲」の中にある東京都中央区立城東小学校(児童数204名/2023年9月現在)。同校は、中央区の特認校制度により学区外からもスクールバスや路線バスで通う児童も多い人気校なのだが、その人気の理由は特徴的な立地もさることながら、中央区の理数教育パイロット校として、理科・生活科・算数科の授業の充実が評価されていることによる。城東小学校の理数教育の実態と今後について、平山尚彦校長および実験教室の取組で連携する早稲田大学理工学術院先進理工学部研究主任の朝日透教授にお話を伺った。

東京都中央区立城東小学校
1962年4月に中央区立日本橋城東小学校と同京橋昭和小学校を統合して開校した学校で、長い歴史をもつ。現在の校舎が落成したのは2022年9月。2023年度現在は1年生2クラス、2年生以上は各学年1クラスという都心ゆえの小規模校である。
この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の4回目です。記事一覧はこちら
目次
2014年から中央区の理数教育パイロット校に
城東小学校は、2014年から中央区の理数教育パイロット校になり、理数教育に力を入れ始めた。平山校長は、この春本校に着任したばかりとはいえ、もともと理科が専門で、現在も区の理科部長を担当するなど、理科への思いは強い。
「子どもたちには、科学的、数理的な視点で物事を捉えて、問題解決をしていける素養を育てていきたいと思っています。具体的には、様々な物事に興味を持ち、自分で深めて追究していける子を育てていきたい。そのためには、小学生のときからたくさんのものに触れ、学び、普段の生活の中に活かしていけるような力を育むことが必要だと考えています」
その実践において重要になってくるのが教員の指導力だが、残念ながら理科指導が苦手な教員が増えているのではないかと平山校長は危惧する。
「今、子どもよりも教員の理科離れが進んでいるところがあり、理科の指導を苦手とする小学校教諭は非常に多いと感じています。学校によっては、教科担任制の導入で理科を指導する必要がなくなり、5、6年生では、音楽よりも理科の指導実績のほうが少ないというケースも増えているようです。そういう状況ですから、まずは教員自身に理科に興味をもたせ、教員の理科の指導力を高めることも大きな課題だと考えています」
年35時間の「Jタイム」で、理数の魅力に触れる
パイロット校として実践している取組のうち最も特徴的なものが、全学年に設定されたサイエンスタイム、通称「Jタイム(城東の頭文字Jに由来)」だ。教育課程で決められた時間とは別に年35時間を捻出し、プラスαとして理数を学ぶ時間にしている。研究主任を中心に全職員で年間計画を決め、大学、研究施設、企業などに協力を求めながらカリキュラムを構築している。
具体的な内容は、後に紹介する早稲田大学と連携した実験主体の授業や、大企業の役員・OBらを中心に組織された理科実験グループ「ディレクトフォース」による実験教室、おもちゃ作り、JAXA(宇宙航空研究開発機構)等の施設見学、プログラミングなど多岐にわたる。ユニークなところでは、南極滞在経験のある教員による南極をテーマにした授業や、同じ東京ミッドタウン八重洲内に支社があるダイキン工業からの提案で、空気の性質からエアコンをテーマにした授業も行われるという。
6年生は集大成も兼ねて2学期に課題研究に取り組む。これは、理科や数学分野をテーマにした自由研究的なもので、9月にテーマを決め、各自で実験や調査を進めて12月に成果を発表する。これには担任のほか外部支援員なども入れて、子どもたちを全力でサポートする。
「現時点では、Jタイムの活動が単発的なものになっている傾向がありますが、将来的には1年生から発達段階に応じて体系的に学びを重ね、本当の意味での集大成という形にしたいですね。1年生なら1年生なりに『不思議だな』と思ったことを自分で見つけ、彼らなりの解決の仕方を育てたい。しっかりと種を蒔くという下地からの積み上げが非常に大事だと思います」

