「学びの多様化学校」とは?【知っておきたい教育用語】
不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が学校を指定し、特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。令和5年、その学校の名称が新たに定められました。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
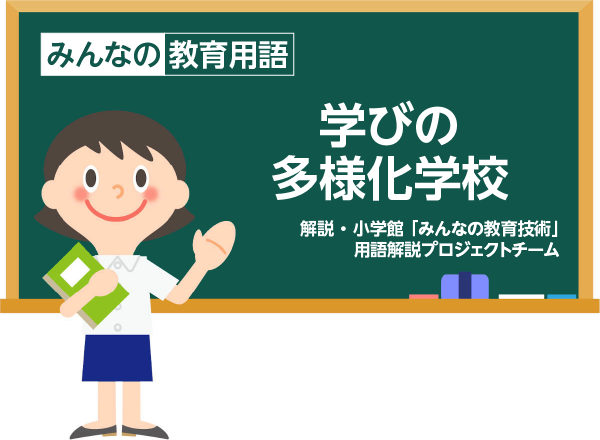
目次
学びの多様化学校の背景
不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条等に基づき学校を指定し、教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。
これまでは、その指定された学校を「不登校特例校」と呼んできましたが、令和5年3月にとりまとめられた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)において、実際に当該学校に通う子どもたちの目線に立った相応しい名称とする観点から、全国の当該学校に通学または勤務する児童生徒や教職員に対し、新たな名称の募集を行いました。その応募結果から、新たな名称に決定したのが「学びの多様化学校」です。
学びの多様化学校の現状と設置に向けて
平成28年に実施された「不登校特例校調査」では、特例校(学びの多様化学校)の在校児童生徒数小学生は横ばいですが、中・高校生においては、年々増加傾向にあります。また、「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」の結果では、小学校、中学校、高等学校あわせて、全国に約30万人の不登校児童生徒がいることが分かっています。不登校状態の児童の定義として、年間30日以上の欠席が基準になりますが、その判断は小学校またはその管理機関が行うこととし、断続的な不登校やその傾向が見られる児童生徒も対象になり得るとしています。
また、学びの多様化学校で特別の教育課程を実施するにあたっては、不登校児童生徒の実態に配慮し、その児童生徒の学習状況にあわせた少人数指導や習熟度別指導、個々の実態にあわせた支援、学校外の学習プログラムなどを活用して指導の工夫をすることが望ましいとしています。
現在、学びの多様化学校に指定されている学校は、令和5年8月現在、全国に公立14校、私立10校の計24校ありますが、永岡桂子文部科学大臣は、不登校対策の会議で全国300校をめざすと述べています。

