「非認知能力」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、「非認知能力」が注目されています。そもそも非認知能力とはどのような能力のことなのか、注目されるようになった背景、育成方法とあわせて解説します。
執筆/小学館「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
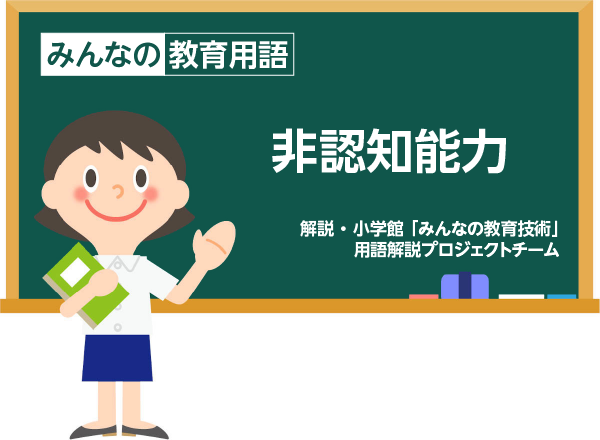
目次
「非認知能力」とは
計算力や語学力といった学力テストなどで測れる能力のことを「認知能力」と呼ぶ一方、コミュニケーション力や意欲、忍耐力など、数値での測定が難しい能力のことを「非認知能力」と呼びます。
OECD(経済協力開発機構)によると、非認知能力は「社会情動的スキル」であると位置付けられ、3つの要素を軸としています。
●目標の達成:忍耐力・自己抑制・目標への情熱
●他者との協働:社交性・敬意・思いやり
●情動の制御:自尊心・楽観性・自信
社会情動的スキルは認知的スキル、つまり認知能力と切り離して考えるのではなく、相互に作用し影響を与え合うものであるとしています。
さらに、文部科学省は小学校教育につながる幼児期の学びの特性として、非認知能力を主に3つの観点からまとめています。
①自分の目標を目指して粘り強く取り組む
中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会-第2回会議までの主な意見等の整理-
②そのためにやり方を調整し、工夫する
③友達と同じ目標に向けて協力し合う
非認知能力とは物事に対する姿勢や取り組み方、他者との関係の構築など、日常生活や社会活動において重視される能力を指します。これらは主に4歳~5歳の幼児期に大きく発達し、学童期・思春期に伸びていきます。
なぜ非認知能力が重視されるのか
最初に非認知能力の重要性を提唱したのは、2000年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカ人・経済学者のジェームズ・ヘックマン教授です。彼は自身の研究の中で、子どもたちが社会経済的に成功をおさめ、ウェルビーイングな生き方につなげるためには、学力やIQを伸ばすことよりも目標達成を諦めない力や自制心といった非認知能力を育成することが重要であると述べています。
非認知能力の発達が顕著に見られる幼児期から小学校高学年までの学童期の早い段階で育成することによって、その後の人生を生き抜く力の土台がつくられます。特に小学校低学年の教育は幼児期の教育と小学校中学年以降の教育とをつなげる重要な役割を担い、ここで学習する姿勢の基礎を形成することが認知能力の育成にも生かされるようになります。

