提言|赤坂真二 マスク世代の子どもたちのために、今、学校がすべき2つのこと 【「マスク世代が奪われたもの」を取り戻す学校経営 #1】

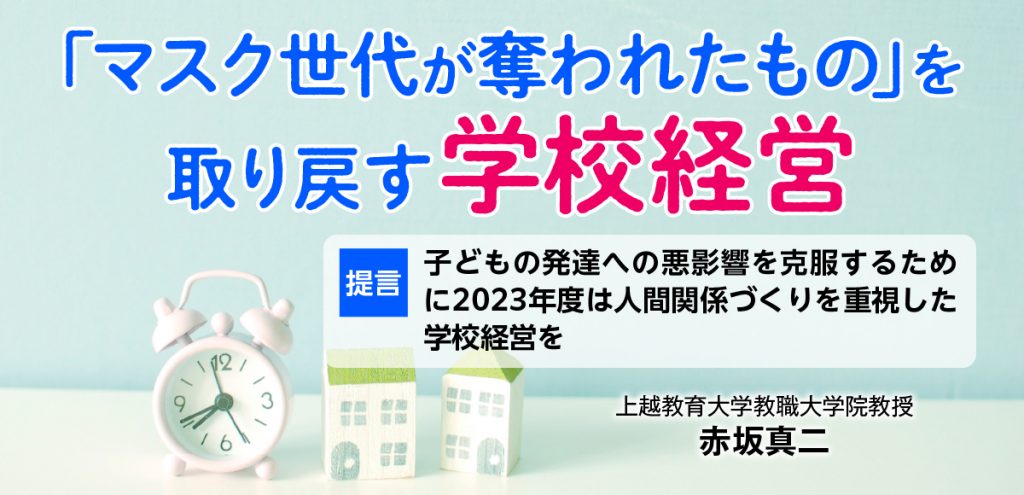
コロナ禍は小中学生の子どもたちにどんな影響をもたらしたのかを知り、2023年度に、学校は何をする必要があるのかを考える7回シリーズの第1回目です。コロナ禍での学校生活は、子どもたちの発達にどんな悪影響を及ぼしたのでしょうか。元教員で、学級経営の重要性に注目して研究活動を続けてきた上越教育大学教職大学院の赤坂真二教授に聞きました。

赤坂真二(あかさか・しんじ)
新潟県生まれ。19年間の小学校での学級担任を経て2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。2018年3月より日本学級経営学会、共同代表理事。『学級経営大全』(明治図書出版)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|赤坂真二 マスク世代の子どもたちのために、今、学校がすべき2つのこと(本記事)
目次
いじめ、不登校が過去最多を更新
2023年5月8日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行し、新たな日常が始まりました。
学校は今、新年度が始まったばかりですが、「子どもは自然にコロナ前の状態に戻るのではないか」と楽観的に考えている先生方が多いように見えます。本当にそうでしょうか。私はそれほど単純な話だとは思えないのです。コロナ禍が子どもにどんな悪影響を及ぼしたのかを明らかにし、学校として対策を講じるべきだと考えています。まずはいじめ、不登校、自殺の件数の推移を見てみます。
文部科学省が2022年10月に公表した「2021年度(令和3年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小中学生のいじめの認知件数は、休校措置や三密(密集・密閉・密接)を避ける指導もあって、2020年度は前年度よりも減ったのですが、2021年度は、小学生が50万0562件、中学生が9万7937件となり、いずれも前年度より増え、過去最多となりました。
不登校については、2021年度は小学生が8万1498人、中学生は16万3442人でした。注目したいのはその増加率です。前年度の数値に比べ、小学生は28.6%、中学生は23.1%も増加しています。小中学校を合わせると約5万人増え、過去最多を更新しました。これは急増と言えるのではないでしょうか。2020年度の1学期には休校期間後に分散登校が行われ、不登校の子どもたちの一部が学校に戻ってきた事例も見られたのですが、結局、2021年度は24万人を超えてしまったのです。
自殺の件数の推移については、厚生労働省の自殺対策推進室が公表している警視庁の自殺統計に基づく2022年度の暫定値をご紹介しますと、小学生は17人、中学生は143人でした。2019年は小中合わせて130人でしたが、2020年は160人へと急増し、2021年159人、2022年は160人と、コロナ禍では高い状態が続いています。
このように、小中学生のいじめ、不登校の件数は過去最多を更新し、特に、不登校の児童生徒が急増しているという現実があります。自殺の件数も高い状態が続いています。コロナ禍は確実に、子どもたちに悪影響を及ぼしているといえるのではないでしょうか。
では、その悪影響とは何かというと、人間関係への影響、学習面への影響、心理面への影響、身体面への影響などが考えられます。これらは独立して存在するわけではなく、関連して子どもに悪影響を及ぼしています。この4つの中で、最も深刻なのは、人間関係への影響だと私は考えています。
マスクが子どもの発達に与えた悪影響
子どもの人間関係に悪影響を及ぼした最大の要因として、マスクの常時着用を挙げたいと思います。大人社会では顔の表情が見えなくても、コミュニケーションにさほど問題はないかもしれませんが、そもそも学校は、コミュニケーションにおいて顔の表情が重視される場所なのです。
朝、教室で担任の先生がマスクで鼻と口を隠したまま、「おはようございます。みんな元気かな?」と言うのと、顔を全部見せて、ニコニコしながら同じことを言うのでは、先生と子どもとの感情の交流は全く違ったものになります。実際に、子どもたちがよく笑う教室では、先生もよく笑っています。子どもは先生の表情を見ながら、先生の言葉に伴う感情も一緒に学んでいるのです。
さらに、子どもは、友だちの表情や口の動きを見て、相手の感情を理解する「共感性」を発達させていきます。共感性とは、社会と関わっていく時に不可欠な能力です。共感性がなければ、人と関われないからです。しかし、コロナ禍では共感性を高める機会がマスクによって、徹底的に削られました。つまり、マスク生活は、人とつながるための手立てである共感性を子どもから奪い、しかも、これから共感性を学ぼうとしている子どもたちに、3年間もそれを強いたわけです。
マスクのほかにも、ソーシャルディスタンス、黙食も、子どもからつながりを奪い、結果として感情交流が削られてしまいました。

