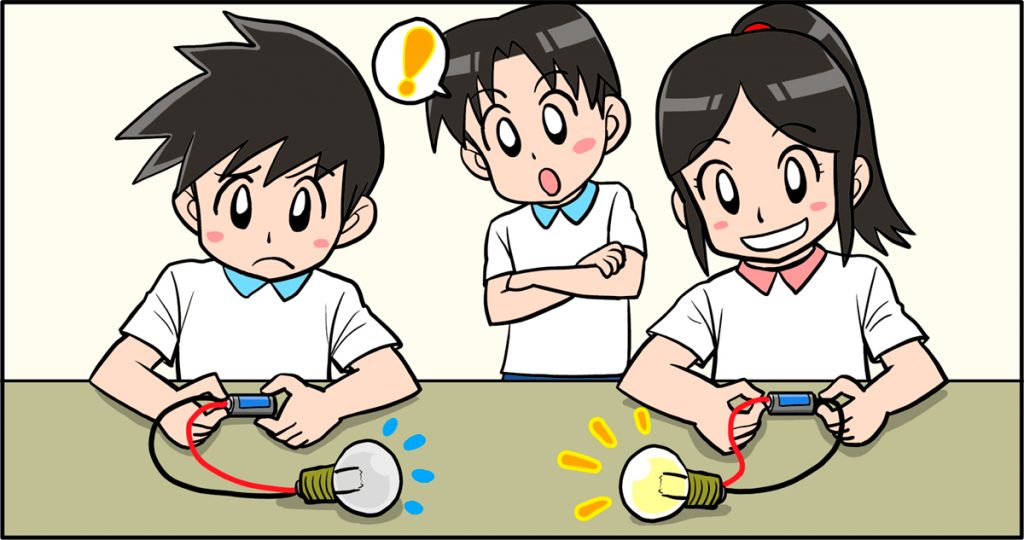理科の学習内容にあわせた、実験グループの効果的な編成方法【理科の壺】

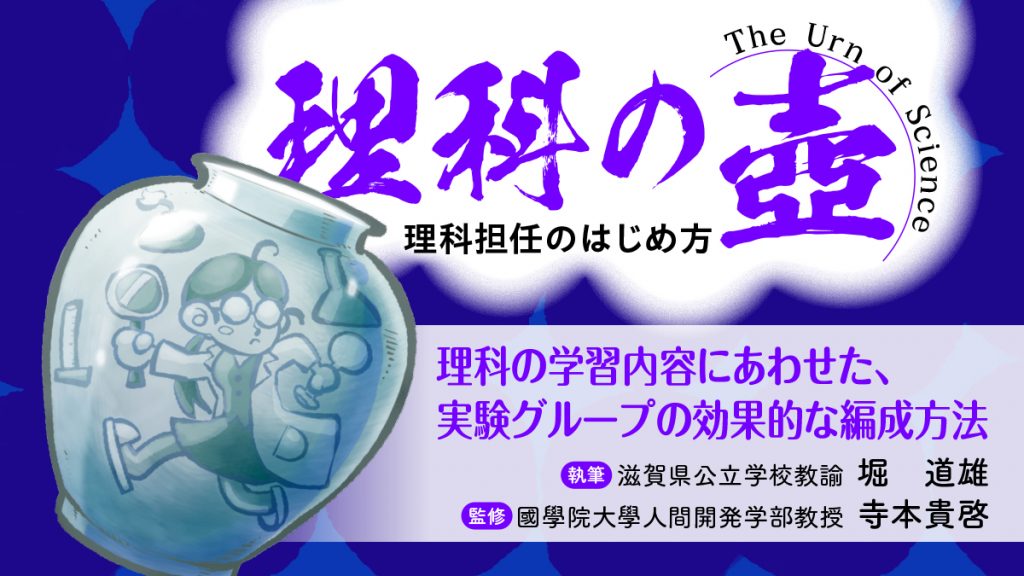
理科の授業をする際、学習内容にもよりますが、3・4年生は主に教室、5・6年生は主に理科室で授業をする学校も多いのではないでしょうか。その際、グループ作りはどうされていますか? 教室であれば、机をくっつけてグループを作りますし、理科室でしたら座れる椅子の数で決めるなどあると思います。今回はそのようなグループづくりについてです。学習内容でグループ編成を考えていきたいですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/滋賀県公立小学校教諭・堀 道雄
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.グループ編成は学習内容で変えてみよう!
理科の学習では、グループで観察実験などをし、問題解決する場面が多くあります。
ただ、グループ活動においては、「子どもによって活動への貢献度が偏ってしまう」「学習を自分事にできない」「全員が活躍できるようなメンバー編成に悩む」などといった声も、よく聞きます。
理科の学習でのグループは単元や場面に合わせてその都度、編成する必要があります。今回は、どの子も協働的に活動できるようにするためのグループ編成のコツを紹介します。
⑴ 大人数でのグループ編成はなるべく避ける
何人でグループを作るのが適切か、ということで悩まれる先生も多いと思います。
結論から言うと、これがベスト、という人数はありません。
単元によって最適な人数は違いますし、場面やクラスの環境、理科室の机配置、実験器具の数なども影響するので、その時々に合った人数を考えていく必要があります。
ただ、1グループあたりの人数が多すぎると、それぞれの役割が薄くなってしまいますし、観察実験の際に手持ち無沙汰の子どもも出てきてしまいます。原則は最大でも4人。さらに3人だとなお、活動の密度は濃くなるのではないでしょうか。1グループに5人以上いるような状態は避けたいところです。
⑵ 1人1実験をするときもグループの編成を有効に使う
単元によっては、一人一人が実験をする、いわゆる1人1実験ができる単元があります。その場合も、グループを編成することで協働的な学びを実現させることができます。 例えば、第3学年「電気の通り道」では、乾電池や豆電球、導線などは1人1セットずつ揃えることができます。
豆電球の明かりがつくかどうか、ということを個人で試すだけでは、協働的な学びは生まれません。
個人で実験をしつつも、グループで活動する(例えば、グループでの話合いの時間をもつ、理科室の同じ机で実験をするなど)ことで、周りの子どもの活動の様子を見て解決の糸口を見いだすことができるようになります。結果の共有や考察の話合いだけでなく、実験中についてもグループでの交流を促すことにより、解決に悩んでいる子どもや自信がもてない子どもも、より主体的に参加できるようになります。