AI型教材「Qubena(キュビナ)」を活用した「個別最適な学び」への挑戦【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画#08】
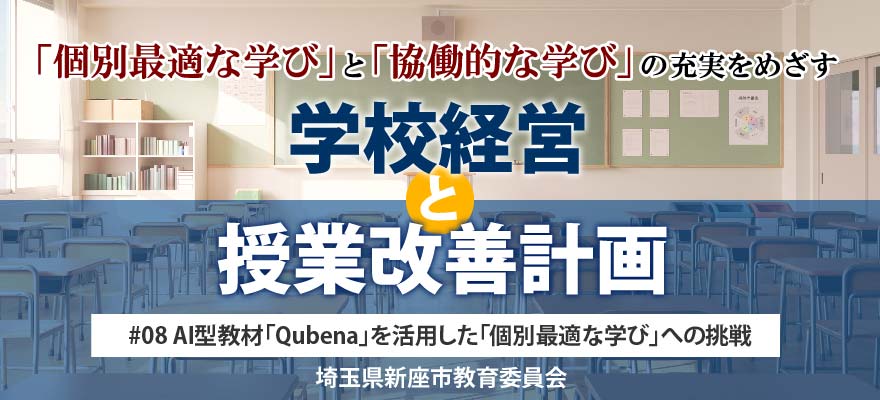
埼玉県新座市では現在、「にいざGIGAスクールNEXT5.0」と銘打ち、AI型教材「Qubena(キュビナ)」など、様々なICTツールを活用して、学習の個性化、指導の個別化、多様な他者との協働を実現するための取組を続けている。これまでの手応えや今後の展望などについて、指導主事の相場健氏と吉田泰生氏に話を聞いた。

埼玉県新座市教育委員会
新座市教育委員会学校教育部教育支援課指導主事の相場健氏(写真左)と吉田泰生氏(写真右)。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の8回目です。記事一覧はこちら
目次
市内の小中学校23校で、AI型教材Qubenaを導入
2022年度から新座市の全小中学校に導入されているAI型教材「Qubena」は、ウェブブラウザ上で動くウェブアプリケーションで、小学1年生から中学3年生までの5教科(算数・数学、英語、国語、理科、社会)に対応した学習教材だ。学習者の解答時間や解説ヒントの閲覧時間、学習履歴などをもとに間違いやつまずきの原因を解析し、搭載されている数万問の中から、一人一人に最適化された問題を出題する。
新座市では、GIGAスクール構想のコンセプトの一つ「個別最適な学び」を実現するための手段として、2020年に経済産業省の「未来の教室」実証事業を活用し、市内5校で「Qubena」を先行導入。それが好評だったため、2022年には市内すべての23の小中学校で正式採用に踏み切った。
一斉授業からの脱却を意識した授業が少しずつ増加
Qubenaは、学力の三要素のうち、「何を理解しているか・何ができるか」が問われる「知識・技能」の獲得において、最も効果があると考えられている。これはシンプルで正誤がつけやすい領域=AIの強みが生きる領域だからだ。新座市でも、最初の導入から2年が経過し、授業での活用が進んでいるのは、算数や数学、社会などの教科だという。
「先日、訪問した学校では、算数の授業のまとめのパートでQubenaが使われていました。専用の管理システムによって様々な情報がリアルタイムで収集されているので、子どもたちが問題を解いている間、教員も自分の端末でその状況を確認でき、理解ができていないのに解説画面を読み飛ばしている子どもがいたらすぐに一声かけるなど、指導の個別化の好事例といえるような机間指導が行われていました」(吉田氏)
「まだ全体的に浸透しているという状況ではありませんが、このような形で、一斉授業からの脱却を意識した授業が少しずつ増えており、市教委としてもレベルアップを実感しているところです」(相場氏)
ちなみに、複雑で多様な評価軸が求められる「学びに向かう力」「思考力・判断力・表現力」などは、AIが苦手とされる領域であるが、前述の授業では、計算に自信のある子どもが、より深く「考え方」を学びたいからと電卓を使って問題を解いていたり、すでに理解できた子どもが悩んでいる子どもに教えたりといった光景も見られたという。紙のドリルと違って問題数が決まっているわけではない(指定することはできる)ため、子どもたち自身も得手不得手を認識した後は、ただ与えられたノルマをこなすのではなく、自分自身で学習計画を立て始めるというわけだ。また同様の理由から、自然と協働的な学びに向かう空気も醸成されやすいのだろう。
「今は、こうした効果にいち早く気づいた学校や教員たちが、進んで工夫を重ねているので、市教委としては、アイデア共有の機会創出に努めているところです」と相場氏は話す。ただ、ここでQubenaのアクセシビリティを細かに説明することは、あまり意味がない。というのも、ハイペースなバージョンアップもQubenaの大きな特徴だからだ。
「開発元であるコンパス社は、導入から時間が経った今も、何か足りない機能はないかと、市内の学校にヒアリングしながらアップデートを重ねています。当然、このアプリを導入しているのは当市だけではなく、ほかにも多くの実践や意見を参考にしているはずで、解析の確度も日々向上しているように感じています」(相場氏)

