「自由進度学習」で一人一人の子どもにオーダーメイドな学びを【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画#02】
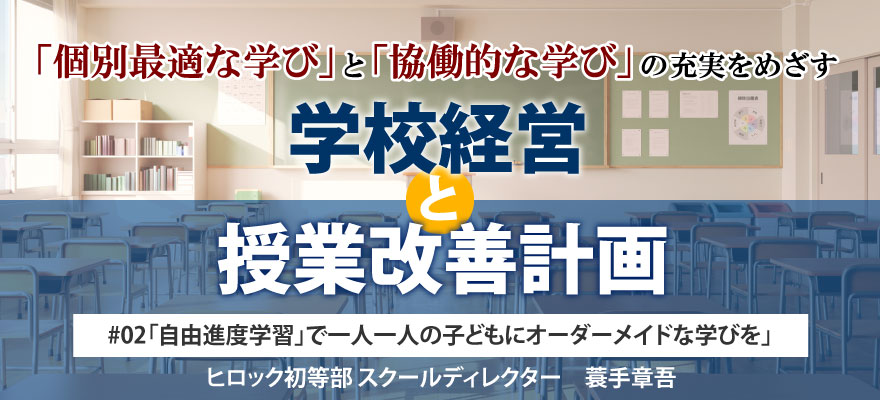
特別支援学校、公立小学校の担任教諭を経て、現在は自身が創設したオルタナティブスクール「ヒロック初等部」のスクールディレクターを務める蓑手章吾氏に、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させる「自由進度学習」の実践や教員の役割、現在の教育現場に求められる変革について語ってもらった。

ヒロック初等部 スクールディレクター
蓑手章吾(みのて・しょうご)
元東京都公立小学校教員。教員歴14年。専門科目は国語で、教師道場修了。特別支援学校でのインクルーシブ教育や、発達の系統性、乳幼児心理学に関心をもち、教鞭を持つ傍ら大学院にも通い、人間発達プログラムで修士修了。2022年4月に世田谷に開校したオルタナティブスクール「ヒロック(HILLOCK)初等部」のスクールディレクター(校長)を務める。著書に『子どもが自ら学び出す!自由進度学習のはじめかた』(学陽書房)、『個別最適な学びを実現するICTの使い方』(学陽書房)など。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の2回目です。記事一覧はこちら
目次
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実とは
近年、GIGAスクール構想の取組によって教育現場にもICTが導入されてきましたが、「一斉授業」の教育スタイルはおよそ150年前からほとんど変わっていません。
「協働的な学び」は、グループ学習や探究学習のように、一斉授業との相性がよくICTも必要としないため、充実化が謳われる以前からコツコツ実践されてきました。一方、「個別最適な学び」は、従来の一斉授業からの大きな転換が必要であり、教員が抱くこれまでの学習観などをがらりと変えてしまうため、今でもなかなか進んでいないのが現状です。
ただ、「個別最適な学び」は教員にとっても子どもにとっても、より学びやすい環境を作るものであり、もっと重視していくべきです。今までは40人ほどの子どもに対して、教員1人が手作業で記録をとったり、課題を出したり、丸つけをしたりしていましたが、ICTの導入によって同時に複数の作業を行えるようになり、子どもたちも一人一人により合ったレベルおよびスピードで課題に取り組めるようになりました。
「個別最適な学び」を進めることは、子どもの孤立を生んでしまう危険性も孕んでいます。だからこそ、コミュニケーションやコラボレーションといった「協働的な学び」との一体的な充実が必要なのです。私が取り組んできた「自由進度学習」は、「個別最適な学び」はもちろん、「協働的な学び」にも有効に機能します。
「個別最適な学び」を実現する「自由進度学習」―机間指導の実践
私が自由進度学習をはじめるきっかけとなった原体験は、特別支援学校での教員経験です。カリキュラムなどほとんど存在しない特別支援学校での教育は、まさに「個別最適」への挑戦の連続でしたが、実践した分だけ子どもたちからレスポンスが返ってくるので、強い手ごたえを感じました。また、環境を調整したらできるようになるのだと「個別最適な学び」の重要性について腹落ちすると同時に、すべての子どもが一緒に学べるインクルーシブ教育の可能性を見いだしました。その経験が現在の「自由進度学習」の実践につながっています。
自由進度学習とは、その名前のとおり、授業の進度を子どもたち自らが自由に決めることができる学習法です。具体的な進め方としては、45分の授業時間のうち、はじめの10分間に簡単なミニレッスンを行い、その後の25分間は自主学習や子どもたち同士で学び合う時間とします。そして、残りの10分間でその時間の学習を振り返ります。学習の目標も自分で定め、タブレットや教科書、プリントなど、学び方も自分で選ぶことができます。
自由進度学習の指導にあたっていちばん大切にすべきことは、「一人一人を見る」ということです。そもそも自由進度学習は、前提として「一人一人を見る」ために行うものです。教員を楽にするためにやるわけでもなければ、テストの点数を上げるためにやるわけでもありません。あくまでも、一人一人をよく見て、子どもたちが何を感じ、何を考えているのか、というのを教員自身が学ぶことが重要です。
特に実践してほしいのが「机間指導」です。今どんな問題を解いているのか、その子のレベルに合っているのか、どのくらい集中しているのかなどを子どもたちのそばに行き、一人一人確認します。さらに細かくいえば、「間」に注目してほしいです。子どもたちが、どの過程のどの部分がわからないのか、どういった方略を練っているのかといった「間」をよく見取りましょう。
例えば、計算問題を解いていたら、間違えるポイントは10個あるうちの1個くらいという段階の子がいたとしても、一斉授業だとその子がどこでつまずいたのかわからず、もう一度最初からやり直しさせたりします。しかし一人一人をよく見取っていれば、一人一人に寄り添った机間指導の中で「繰り上がりが正しくできていなかった」などのポイントを正確に指摘できます。的確なアドバイスがもらえれば、子どもは最小限の労力で「できた!」を実感でき、学習が楽しくなります。
自由進度学習では、その教員と子どもが通じ合う瞬間が多く生まれます。子どもたちの学んでいる姿とその熱を必死に見取り、教員も共に成長していくことが「個別最適な学び」および「新しい教育観」への気づきをもたらしてくれます。

