「学びのユニバーサルデザイン」と「個別最適な学び」【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画 #01】
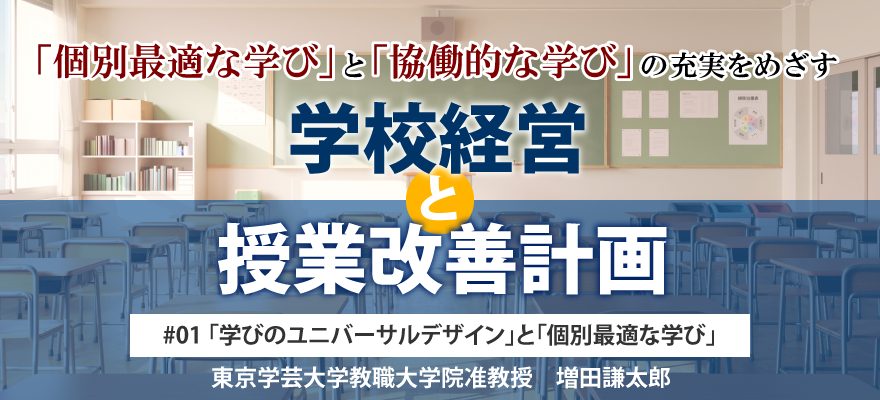
特別支援学級の担任教諭を経て、現在は東京学芸大学教職大学院准教授を務める増田謙太郎氏に、特別支援教育の立場から「学びのユニバーサルデザイン」と「個別最適な学び」の実践における教師の心構えについて伺った。
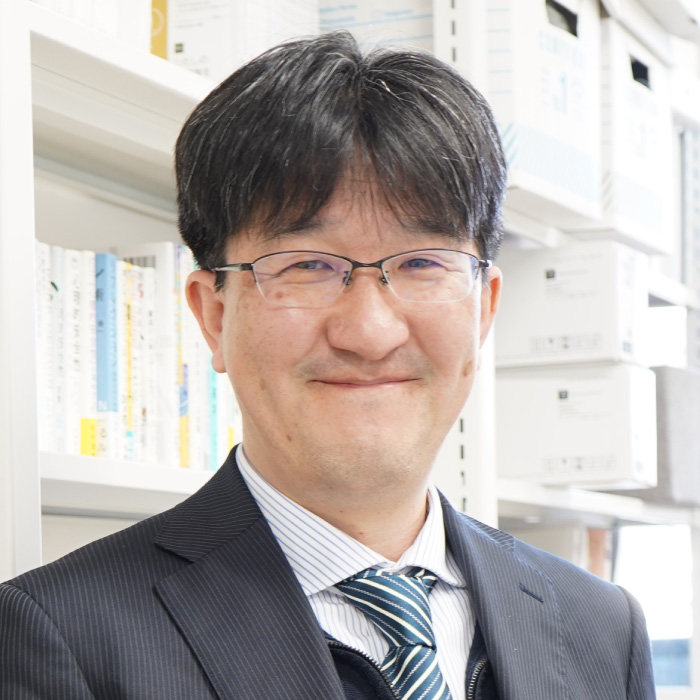
増田謙太郎(ますだ・けんたろう)
東京学芸大学教職大学院准教授。東京都出身。東京都公立小学校教諭(特別支援学級担任)、東京都北区教育委員会指導主事を経て、2018年4月より現職。専門はインクルーシブ教育、特別支援教育。著書に「『特別の教科 道徳』のユニバーサルデザイン 授業づくりをチェンジする15のポイント」(明治図書出版、2018年)、「学びのユニバーサルデザインUDLと個別最適な学び」(明治図書出版、2022年)などがある。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の1回目です。記事一覧はこちら
目次
「学びのユニバーサルデザイン」と「個別最適な学び」の共通点
「学びのユニバーサルデザイン」(以下「UDL」)の大きな特徴となるのが、「オプション」という考え方です。「みんなでこれをやりましょう」というような画一的な指導ではなく、代替手段をあらかじめ授業の中で設定しておくことで、助かる子どもがいるという考えです。特別支援教育の立場から言うと、画一的な授業と特別支援教育は非常に相性が悪い。学び方の選択肢がいくつかあり、クラスの中で一人一人の子どもの選択が認められるようになっていけば、特別支援教育の充実や、合理的配慮の提供にもつながっていきます。UDLはイコール特別支援教育のことではなく、すべての子どもたちを対象としていますが、特別支援教育に有効な方策であることは確かです。画一的・一律的な授業をどう解体していくか。そのカギとなるのがUDLなのです。
UDLと「個別最適な学び」の関係を厳密に言うと、UDLは個別最適な学びにおける「指導の個別化」と「学習の個性化」のうち、「指導の個別化」にあたるといえるでしょう。ただ、両者の考え方は非常に酷似しており、ほとんど同じといってよいと思います。シンプルに言うと、どちらも「教師が認める」という考え方です。例えば、ある子どもが「紙と鉛筆は使うのが難しいからタブレットを使いたい」と言ったときに、教師がこれを認められるかどうか。UDLと個別最適な学びは子どもが主体となる考え方のため、「教師がタブレットを『与える』」という発想ではなく、「子どもがタブレットを使いたいと言ったときにそれを『認める』」という発想なわけです。
特別支援教育が現場に浸透して15年ほどが経ちますが、ただでさえ教師の多忙化が問題視されている中、様々な個性をもつ児童生徒たち一人一人に応じた授業をしなければならない状況となり、現場からの悲鳴が聞こえてきます。教師がすべてお膳立てをする「与える」授業だと、教師が忙しくなる一方で、子どもは口を開けて待っている、いわゆるお客様状態になってしまいます。そこで、発想の転換として個別最適な学びやUDLの「認める」という発想が役に立ちます。
「認める」には教師の専門性が要求される
ただ、この「認める」行為には、教師の高度な専門性が要求されます。例として、算数・数学の授業で考えてみましょう。算数のテストで、計算が苦手な児童が「電卓を使いたい」と言ったときに、それを認められるでしょうか。これを判断するのはとても難しいのですが、例えば、図形の面積を求めるテストであれば使ってもよいと考える教師は多いです。なぜかというと、そのテストは計算力より図形の面積を求めることがねらいだからです。一方で、計算力を試すテストでは電卓の使用は認めにくいですよね。このように、その授業や活動のねらいは何なのかを判断する力をもって、認める・認めないラインを見極めていく専門性を、現役教師の方には高めていってほしいと思います。
冒頭にUDLの特徴として挙げた「オプション」は、教師が「認める」ことによって生まれますが、これには2つの方法があると考えています。一つは「最初から選べる型」。最初から学び方の選択肢aとbを提示し、子どもが選ぶ方法です。例えば、作文をするときに最初から紙と鉛筆で書くか、タブレットで打ち込むかを選べるというようなことです。もう一つは、私は「スタンダードとオプション型」と呼んでいるのですが、基本は皆が紙と鉛筆を使うけれど、それが難しい子どもにはタブレットの使用を認めるということです。両者は少しニュアンスが異なりますよね。どちらの方法を教師が選択するかは授業によっても変わりますが、今の日本の学校の授業には後者の「スタンダードとオプション型」が合っているのではないかと思います。最初から選べる式だと、選ぶことに慣れていない子どもは戸惑いますし、教師にとっても、2つの選択肢を最初から提示しておくための下準備の負担が増えるためです。
学びのユニバーサルデザインにおける「オプション」
①最初から選べる型
最初から選択肢aとbを提示し、子どもが選ぶ
(例 a…紙と鉛筆を使って書く b…タブレットで入力する)
②スタンダードとオプション型
基本は皆a、それが難しい子どもにはbを認める

