Q2 自分の授業力向上に生かすための研究授業の見方は?(前編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#3】

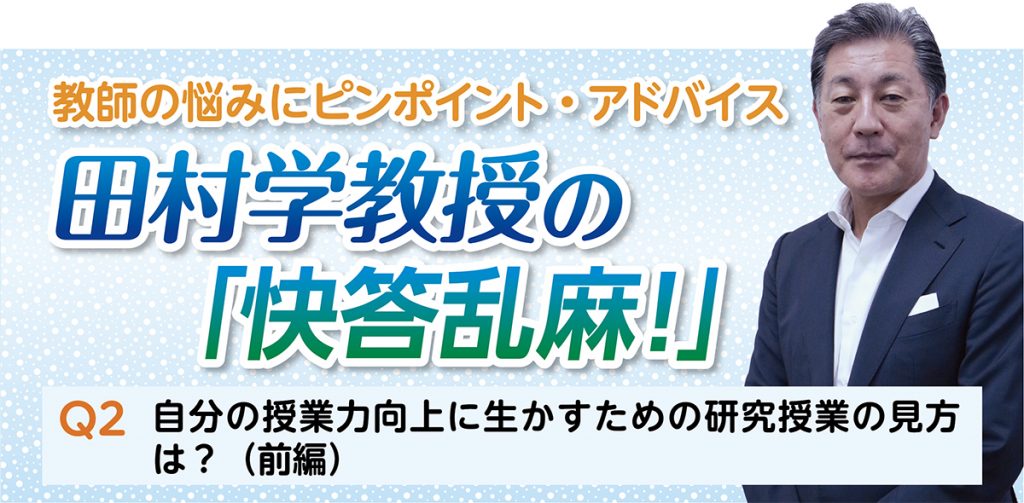
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、研究授業の見方・授業研究の方法について「快答」していただきます。
※
Q2 コロナ禍以降、中止、縮小傾向だった研究会が、昨年から徐々に再開され、研究授業を参観する機会も増えてきました。毎回、研究の協議にも参加して学んでいるつもりですが、それがはたして自分の力になっているのか今一つ実感が湧きません。そこで教えていただきたいのですが、研究授業を見るときに、何をどこからどのように見て、どう記録・活用すれば、自分の授業力向上に生かすことができるのでしょうか?(小学校・20代)
子供の思考や感情の変化を見とるために、教室の横前方から授業を見る
A 授業研究は、Lesson Studyと呼ばれますが、日本の教員研修のスタイルが世界でも取り入れられたもので、「スシ」や「テンプラ」と同じように、「ジュギョウケンキュウ」という日本語をそのまま使う人もいます。つまり、海外からも教師の力量を形成するうえで意味のあるものとして、高く評価されているわけです。それは、教師として確かな力を付けていくためのインフラのようなもので、日本の学校の先生にしてみれば当たり前の仕事の一部だと思うのですが、国際的に見てもとても価値のあるものなのです。
ただ、その授業研究のあり方については、何に力点を置き、何を見、何を語るかについて、学習指導要領の趣旨に沿って少し考え直してみる必要があると思います。例えば、私自身が若い頃の経験で言えば、授業をどうつくるかを考えていくために、教師が行う一つ一つの所作やふるまい、語りや提示、板書などに目を向ける傾向がありました。そして、それが適切か不適切かを議論することが多かったように記憶しています。もし現在もそれと同様であるとすれば、見直す必要があると思うのです。
授業中、いくら先生が適切に語ったり板書したりしたところで、それを学び手である子供たち自身がねらい通りに受け取っていなければ意味がありません。つまり、子供たちにどのような学びが生じているか、ということこそを吟味しなければ意味がないのです。それは、子供たちの資質・能力の育成という目標を考えればごく当然のことでしょう。ですから、授業中の先生の行為に目を向けることも必要ではありますが、第一優先は、子供の学びがどうなっているのかを、子供の姿として捉えるということになります。
そうすると、子供の思考や感情の変化を見とっていくために、表情の変化や動作を確実に見とることのできる場所から授業を見ることが必要です。ですから、自ずと教室の横前方から授業を見ることになってきます。実際の研究授業の最中、多くの先生が立って見ている教室の後ろ側は、子供の後頭部しか見えませんから適切な場所とは言えないでしょう。さらに言えば、たまに研究会で見かける廊下に出ている人は、何も分からないということになります。もちろん、後方でも子供の声は聞こえてきますが、その時にも、どんな表情をしてどんなふるまいをしているかということが、子供の思考や心情を見るうえでとても大きいと思います。そういったものを捉えることができるかどうかが、授業後の協議をしていくうえでの重要なポイントになるのです。
つまり授業研究会というのは、授業をしている先生の力量を確かめたり、腕試しをしたりする場というよりも、むしろ授業参観者の力量こそが問われる場であるべきなのだと思います。先にもお話ししたように、昔は「この先生のこういうところが上手」「ここが課題」というようなお話がありました。そうした評価も一定程度あってもよいとは思いますが、もっと評価されるべきなのは参観者がどれくらい子供の学びをしっかり見とることができて、それが協議会の場で語られているかということだと思います。


