「通級による指導」とは?【知っておきたい教育用語】
「通級による指導」を受けている児童生徒数は約16万5000人(文部科学省、2022年)で、10年前の約6万人から2.5倍以上に急増しているという調査報告があります。また、そのうち小学生は約14万人ということですから、現在の、あるいはこれからの学校教育のあり方を考える上で、「通級による指導」は見過ごすことのできないものです。その目的や指導の仕組み、人数増加の背景、学校現場が抱えている課題などについてみていきましょう。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
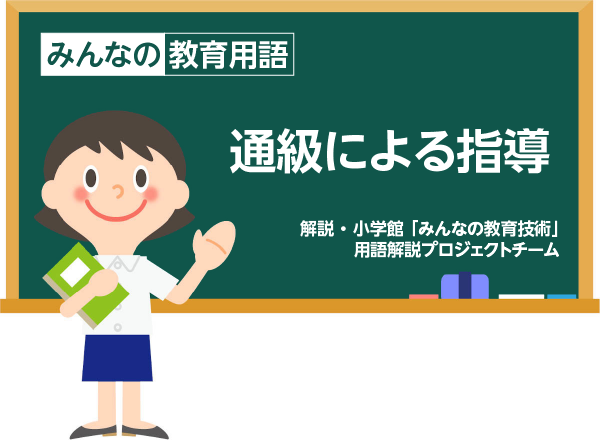
目次
「通級による指導」の目的と法的根拠
「通級による指導」は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の通常の学級で学校生活を送りながら、その一部で特別な指導を必要とする児童生徒が利用する特別支援教育の形態の1つです。
学校教育法施行規則第140条では、通常の学校において、次の障害に応じた特別な指導を行う必要のある場合は、個別に特別な教育課程を編成して教育を行うことができるとされています。
- 言語障害者
- 自閉症者
- 情緒障害者
- 弱視者
- 難聴者
- 学習障害者
- 注意欠陥多動性障害者
- その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当な者
これらの障害のある児童生徒が、障害による学習や生活上の困難さを改善・克服するために、個々の教育ニーズに応じた指導を受けることができる仕組みとなっています。具体的には、通常の学級で授業を受けたり活動をしたりしながら、一部の時間、通級指導教室で指導を受けることになります。
その形態としては、自校通級と他校通級があります。当該児童生徒の障害に対応する通級指導教室が自身の学校内に設置されているかそうでないかで、その形態が決まります。他校の通級指導教室に通う場合は、往復の時間や交通手段についても配慮が必要です。その地域の地理的な状況や発達段階等によっては、保護者の送り迎え等も必要となる場合もあります。
いずれの場合も、通級による指導を担当する教員が、関係教職員や保護者等と相談しながら、児童生徒の障害特性に応じた指導目標や指導内容、指導時間等を決めます。
通級指導教室での指導内容と指導時間
通級による指導を受けるには、自治体の教育委員会が定める手続き(自治体によって異なる)を踏む必要があります。園や学校との相談を経て、保護者が教育委員会に申請し、その必要が認められると当該児童生徒の通級による指導が始まります。この過程で、指導の内容や方法、時間等が検討されます。
指導内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考にして「自立活動」の内容を取り入れたり、特に必要があるときには障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導が扱われていたりします。また、通級による指導の時間は、小中学校で年間35単位時間から280単位時間までが標準として設定されています(文部科学省告示、平成5年)。一般的に学校の授業日数は年間35週で数えられていますので、1人の児童生徒が通級による指導を受けられるのは、週1単位時間から週8単位時間ということになります。高等学校は週7単位時間となっています。

