先師・先達に学ぶ(その2) ー森信三先生と寺田一清氏(下)ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第51回】

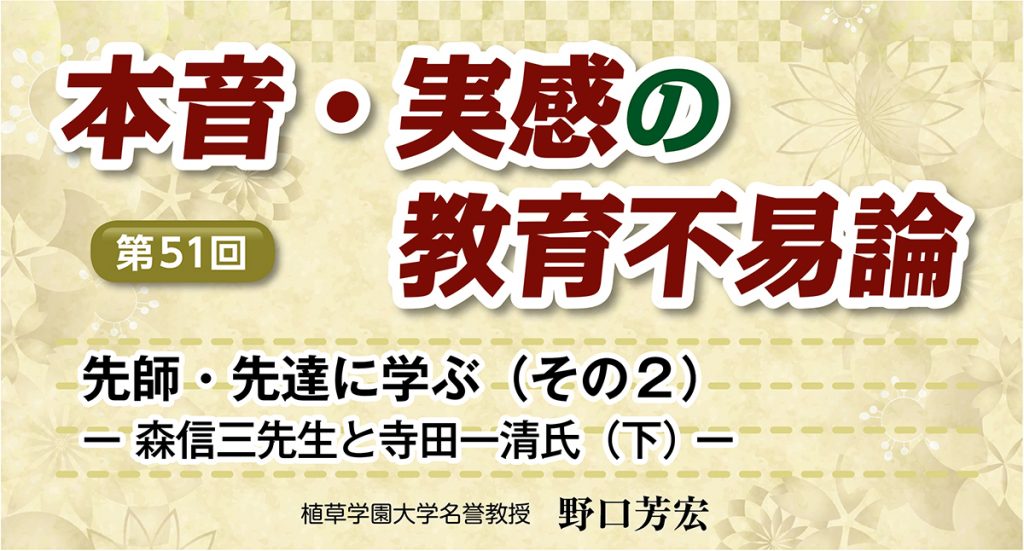
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第51回は、【先師・先達に学ぶ(その2) ー森信三先生と寺田一清氏(下)ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
4 寺田一清氏の生き方
前回、寺田一清氏のことについて若干触れたが、もう少し述べておきたい。前述したとおり寺田一清氏は大阪の呉服店の経営者である。教育者ではないが、若くして現在の麗澤大学の前身である東亜外事専門学校に学んだ経歴を持つ。就学中に体調を崩して中退、大阪の商家を継いだ方で、もともと学究的な素養の持ち主であったことは想像に難くない。
私は、偶然、幼児教育の研修会の場で直々に出合う縁に恵まれた。その折に森信三先生が飯菜別食を実践する方と伺った。米には米の味、菜には菜の味がある。一緒に食べてはいけない、というお考えだったようだ。寺田一清氏も思う所あってそれを実践しているとも伺った。
正直の所、その時の私はこの考えには疑問を抱いた。例えば握り寿司は飯菜同食だからこそ旨いのだし、混ぜ御飯も然りである。その採否はそれぞれの人の自由に委せてもよいことだとは思うが、寺田氏は直ちに森先生の考えに従っている。それほどの絶対的信頼の下に結ばれていたのだと、師弟の縁の深さという点については脱帽、敬服の他はない。
そうであるからこそ「初めて面会を果たした時の森信三先生の話に感動した寺田氏は、5分とかからないうちに、この人こそ自分の生涯の師と思い定めた。」という文面にも頷(うなず)くことになるのである。
ここで、私は森先生の次の文章を思い出す。不朽の名著『修身教授録』(致知出版刊)の第33講「敬について」の一節である。
礼の本質としての「敬」という問題についてお話しましょう。(中略)
では敬とはどういうことかと申しますと、それは自分を空(むなし)うして、相手のすべてを受け入れようとする態度とも申せましょう。相手のすべてを受け入れるとは、これを積極的に申せば、相手のすべてを吸収しようということです。(483ページ)
寺田一清氏の、森先生に対する態度は、まさにこの「敬」の体現に他ならない、と改めて深く思うのだ。一方このような私の書きぶりについては「それは盲従ではないのか」という批判を持つ人もあるだろう。現に私もそうであった一人なのだ。
現在の日本の教育界の潮流は、森先生の説く「すべてを受け入れようとする態度」に対しては懐疑的、批判的な傾向にあるのではなかろうか。例えば次の文言をどのように諸賢は受けとめられるだろうか。
特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければならない。
価値観というものは、そもそもその当否、善悪を問わず「特定」であろう、と私は思う。「特定でない価値観」とはどういうものを言うのだろうか。
上の文言中の「主体性をもたず」の主語は「子供」であろう。無知、未熟、未完成な子供の「主体性」にどれほどの「価値観」を期待できるのだろう。これでは、いわゆる「子供中心主義」で、子供をまるで天使のように崇める過剰美化とは言えないか。
森先生の言われる「相手のすべてを受け入れようとする態度」とは、まさに「対極にある」考え方とは言えないか。上段の引用文は、文部科学省発行の解説『特別の教科 道徳編』の2ページに書かれているものだ。森信三先生は、上の引用文に続けて次のように述べている。
尊敬の念を持たないという人は、小さな貧弱な自分を、現状のままに化石化する人間です。(中略)将来教師となって最も大事な事柄は、まず生徒たちが、尊敬心を起こすようになることでしょう。(前掲書483ページ)
寺田一清氏は、このような森先生のお考えを全身、全霊で受けとめられ、遂に名実共に高弟となって終生を森信三教育学を世に広め、知らしめた。寺田一清氏は、森教育学における「敬」の全(まった)き体現者と言うことができるだろう。
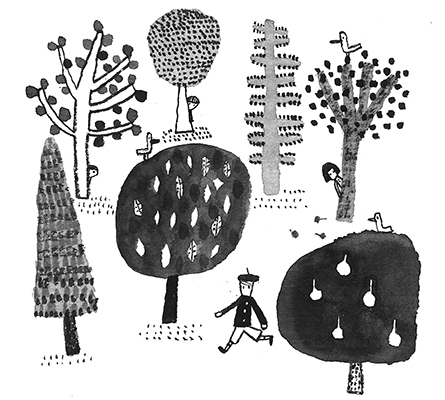
5 寺田一清氏の「ハガキ道」など
「ハガキ道」という言葉はあまり耳馴れない方が多いと思う。「ハガキ道」の創始者坂田道信氏は森信三先生の講演を聞いて早速ハガキを書くことを実践し始め、その継続によって自分の人生が一変したという方である。29歳で森先生に出会い、43歳を迎える頃にはハガキを書く仕事が8割ほどになった由。いつの間にか坂田氏のハガキ実践は「ハガキ道」と呼ばれるようになる。年賀状だけでも1万5千通を超えるというから大変な影響も与えていることが分かる。
坂田氏のハガキ道の伝道は多くの道友を増やして今に続いているが、寺田一清氏もそのお一人で、私と初めてお会いした折も翌日にはもうお礼のハガキが届いて驚いた。また恐縮した。ショックに近い感動だった。
ハガキ道の道友は「複写ハガキ」という特製の葉書を使用する。葉書サイズのカーボン紙綴りの間に葉書を差しこんでカーボン紙に本文を認めると、青色のカーボンインクで葉書に本文が転写される。本文はカーボン紙に残っているので発信の記録は全て残る。これは坂田氏の考案によるものらしい。私は道友の方から一冊拝受したのだが、筆不精の失礼を重ねている体たらくで汗顔の至りという他はない。寺田先生からのお便りは今も大切にしている。
森先生は、御自分の教育学を広めるべく昭和31年、60歳の還暦を機に『実践人』を創刊する。この創刊号はタブロイド判8ページの新聞のような刊行物だった由。この頃から、ハガキの返事を必ず書くこと、躾の三原則などの主張を積極的に始められたようである。昭和39年、68歳の折には『実践人』は第100号、立派な月刊雑誌として多くの読者に愛読され、昭和43年、72歳の折には月刊誌『実践人』の読者は2千人に及んだそうである。寺田一清氏の森信三先生との直接の出会いは、先生69歳、『実践人』100号を発刊された頃のことである。
昭和50年、先生79歳の折に「実践人の家」(一般社団法人)を設立、落成し、『実践人』の刊行をはじめとして森先生の教育思想、教育活動の本格拠点となる。寺田一清氏はここの常務理事となって中核的な活動をされるようになる。ハガキ道、複写ハガキなどの普及にも大きな好影響を与えることになる。
寺田一清氏の編による森信三先生の著書はかなりの数に上るが、中でも『森信三先生 不尽叢書』全5巻(新書判、平成21年刊)は著名である。この頃にはまだ寺田清一という本名で活動していたが、後にペンネームとしては本名を逆にした「一清」を用いるようになった。なお、『不尽叢書』全5巻の刊行は、㈱登龍館からなされている。寺田一清氏とずっと書いてきたが、氏は森先生の学問、思想、人柄などを書物からだけでなく直々に接して学ばれ、それらを元にした御自身の著作も多く残している。また、各地の講演会にも招かれ、多くの講演活動もされている方である。そのことを踏まえれば当然のこと寺田一清先生と書くのが礼というものであろうけれど、氏は大層気さくな方であったので、親しみをこめて氏という呼び方をさせて戴いた。了解を乞う。
あの名調子の講演にも、笑顔にも、声にも出合えなくなってしまったことが本当に残念である。冥界の極楽の地で、森信三師と会って毎日のように歓談されているであろう姿を思い浮かべて楽しむこととしたい。
蛇足ながら、「師弟愛」という言葉があるが、『広辞苑』をはじめどの辞書にもない。複合語だからなのだろうが、言葉としてはかなり広く使われている。「師弟間の愛」という意味だが、「師弟」という言葉は今では死語に近い。「先生と教え子」は偶然の出合いであるが、「師弟」の出合いは必然の出合いであり、師を選び、師を求めての出合いである。先生は教え子を選べないし、教え子は先生を選べない。そこから愛が生まれることもあるが、それは一般的には担任の期間に限られ、担任が終われば別人に移っていく。それに対して師弟愛は長く続くのがむしろ一般だ。「生涯の師」などと弟子から慕われ、また師匠もそのような愛を以て弟子を育て、愛を傾ける。森信三先生と寺田一清氏の愛は、まさにその典型であり、模範とも言えるであろう。

