温泉理論で読み解く、あれもこれも思考からの脱却【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第15回】
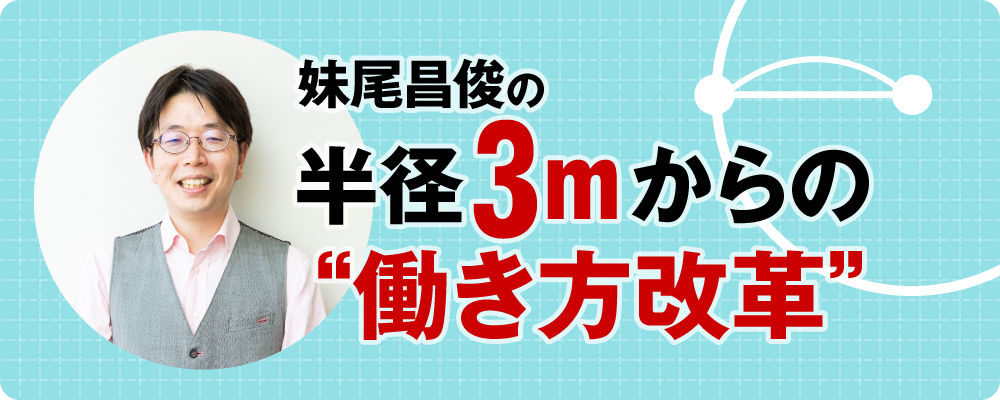
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事・妹尾昌俊
目次
伝統だから、前からやっているからで続ける?
前回は、学校を取り巻く様々な教育活動について「それってなんのため?」と問い直していくことを提案した。目的と目標を確認すると、いまやっている手段が妥当なのかチェックできるからだ。
中教審の働き方改革の答申、ならびにこれを受けた文科省の通知では、登下校指導や集金業務、部活動、清掃指導などの14の業務について仕分けをして、改善案を提案している。ただし、14業務はあくまでも一部であり、これを参考にしつつ、他にも応用していけるとよいと思う。答申の中にもこんな一節がある。
教職員間で業務を見直し、削減する業務を洗い出す機会を設定し、校長は一部の教職員に業務が偏ることのないように校内の分担を見直すとともに、自らの権限と責任で、学校としての伝統だからとして続いているが、児童生徒の学びや健全な発達の観点からは必ずしも適切とは言えない業務又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務を大胆に削減(※)……。
(※注)学校としての伝統だからとして続いているが、児童生徒の学びや健全な発達の観点からは必ずしも適切とは言えない業務又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務(例えば、夏休み期間の高温時のプール指導や、試合やコンクールに向けた勝利至上主義の下で早朝等所定の勤務時間外に行う練習の指導、内発的な研究意欲がないにもかかわらず形式的に続けられる研究指定校としての業務、地域や保護者の期待に過度に応えることを重視した運動会等の過剰な準備、本来家庭が担うべき休日の地域行事への参加の取りまとめや引率等)について大胆に見直し・削減してこそ、限られた時間を授業準備に充てることができ、一つ一つの授業の質が高められ、子供たちが次代を切り拓く力を真に育むことにつながると考えられる。(p.31)
※「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成31年1月25日。中央教育審議会)より
この注の部分は、「ここまで言うか」というくらい具体的なことを畳みかけている。もちろん、中教審がここまで言うことには賛否はあろうかと思う。本来は中教審や文科省がゴジャゴジャ言わなくても、この注釈で例示されていることのほとんどは、校長の裁量と責任で果敢に見直していけることだ。「細かいことまで口を出すな、おせっかいめ!」というご意見もあろう。 だが、そこまで国に言わせるほど、まだまだ学校の伝統や慣習ということで、残っているものも多いのではないだろうか。
この答申が出てから、はや3年半が経過している。各学校での業務の仕分けや見直しは進んだだろうか。新型コロナの影響で、学校行事や研究会などは縮小、負担軽減が進んだところも多い。だが、そろそろコロナ前に戻そうという動きもあると聞く。
学校の働き方改革は慣性の法則への挑戦
私は講演などでそう述べている。学校がよかれと思い始め、続けてきたものの中には、いったん始まると止まらない、続けることがともすれば目的化しているようなものもないではない。時にはこの慣性の法則に逆らうことが必要だ。
もちろん、ほとんどの伝統、慣習も、何らかの教育上の効果はある。子どもたちのために全然ならない、なんてものはほとんどない。だが、「あれもこれも」やる余裕はあるだろうか。

