それって、何のためでしたっけ?【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第14回】
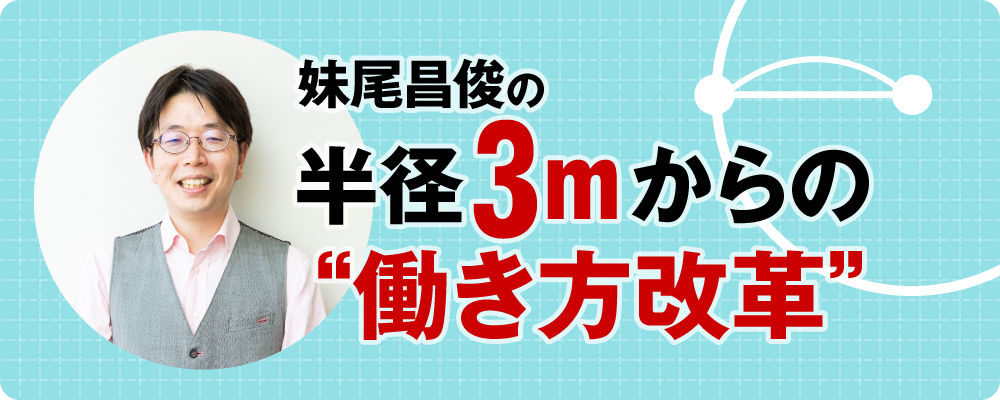
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事・妹尾昌俊
目次
働き方や業務の見直しで頻出の反対意見
働き方改革や業務改善に関連して、せっかく何かを見直そうという声やアイデアが出ても、多くの場合、反対意見に出くわす。保護者等からの反対もあろうが、それよりも手前で難関なのは、身内、つまり、当の教師からというケースも多いのではないだろうか。
実際に私がある学校(複数)で聞いたこととしては、行事(陸上大会、マラソン大会など)をやめたい、見直したいというとき、あるいは少子化と教師の負担増に伴い部活動の一部を休部にしたいというとき、決まって出てくるのは「そんなことをしたら、楽しみにしている児童生徒がかわいそう」「子どもたちの活躍の場がなくなるのは残念」「やれるうちは、やったほうがよい」といった意見だ。
もう少し翻訳すると、「児童生徒のためになる」「教育効果があるのに」という理由での反対だろう。気持ちはよくわかるが、子どものためにということで思考停止せずに、よく考えてみる必要があると思う。
実際、私が講演、研修をするときは、「子どものためになるから、教育効果があるから、やめるべきではない、減らすべきではない」といった論調に「あなたなら、どう答えますか」というワークをよく入れている。読者のみなさんなら、どう答えるだろうか?
部活動は何のため?
部活動を例にとって考えてみよう。少し前にある県の教育委員会からの依頼で、県立高校校長等向けに、あるグループワークをやってもらった(下記参照)。別の機会には私立学校の教職員向けにも似たワークを行った。読者のみなさんもご自身で考えてみてほしい(校内研修等で議論してみることをおすすめする)。
[部活動の在り方について考えるワークショップの例]
①そもそも、部活動は何のためのものでしょうか? 主たるねらいは何ですか?
②その目的ないし目標は、部活動でないと実現できないことでしょうか?
③部活動に入っていない生徒はどうします?
④部活動に大きな意義、効果があるとしても、いまの時間、負担でいいでしょうか?
★教員の負担や24時間という視点から、どんな問題があるでしょうか?
★生徒の負担や24時間という視点から、どんな問題があるでしょうか?
私を含めてコンサルタントが大事にする思考法であり、ここでもポイントとなっているのは、目的と目標を確認するということだ。このワークでは①の問いが該当する。
このこつが使えるのは、別に部活動に限らない。例えば、こんなふうに。
・運動会は何のためのものでしたっけ? (保護者を喜ばせることがメインじゃないですよね。)
・修学旅行って、修学になっているのでしょうか。遊園地などに行くのは楽しいと思いますが、どんな学びにつながっているのでしょうか?
・この授業研、公開研のそもそものねらいは? 指導案が書けることじゃないですよね。

