リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #6「快」のコミュニケーションができる子供たちに|岩田慶子先生(兵庫県公立中学校)

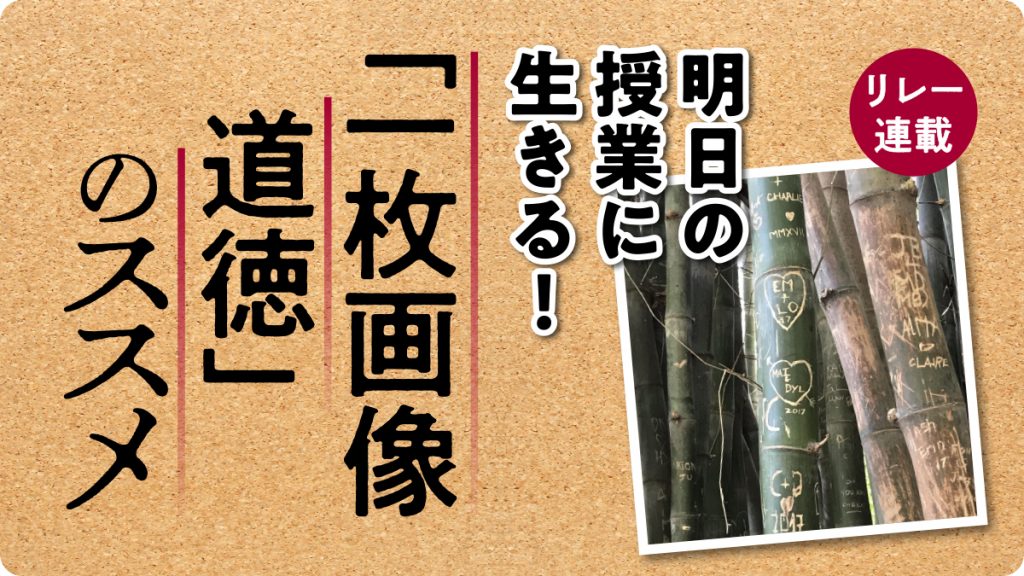
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促していく……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第6回は、岩田慶子先生のご執筆でお届けします。
執筆/兵庫県神戸市立星陵台中学校教諭・岩田慶子
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
はじめに
先週の山崎先生の「一枚画像道徳」から、「自分なら、どう考える?」と、とても大切なバトンをいただきました。
中学1年生では、公共心や公徳心をテーマにして「自分なら?」と考えることが多くなります。なぜでしょうか。「中学生になると社会的な責任が大きくなるのだ」という自覚が芽生えるからです。
多くの教材で、登場する善悪の「悪」はハッキリしています。「公共の福祉」に反する行動が「悪」になります。その「悪」について、生徒の思考を促そうとしても、「だめだね。こういうことしないようにしようね」で終わってしまう…。深まりがない…。どうすればよいだろうかと、道徳の指導案をつくりながら頭を悩ませていました。
そんな時、オンラインセミナーで知り合った北海道の藤原友和先生から「一枚画像道徳」のご提案をいただきました。1枚の画像から、「ただの悪」ではなく、「どうしてこういう行動に走ってしまうのだろう?」「こういう行動を止めさせるために、どんなコミュニケーションが有効だろう?」と、人間の行動を裏付ける心理にまで迫れたら……!! ワクワクが止まらなくなりました。
1 授業の構想〜子供たちの発想が向かう先へ〜
対象:中学1年
主題名:落書き防止ポスターを作ろう
内容項目:C-(10) 遵法精神、公徳心
法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。
以下の写真を提示します。

発問1 この竹を見て、どんなことに気付きましたか。
予想される生徒の発言を挙げてみます。
●竹に、落書きされている。
●英語で落書きされている。
●ハートマークの中にイニシャルが二つ描いてあるのは、日本語で言うと相合傘マーク?
●人の名前や、日付も書いてある。
●削ったような跡がある。
説明
ここで、次のように説明します。
●この写真は、オーストラリアの「ブリスベンシティー植物園」という市立(公立)の植物園で撮ったものです。
●「ブリスベンシティー植物園」は、Google Mapで調べると、10,487人の人が評価した5段階評価で4.7の高評価です。(ここで、生徒の端末で実際に検索させてもよいですね。)
●Google Mapの「クチコミ」には、このようなコメントが寄せられています。
<高評価を付けた人のコメント>
●街の中心部から歩いてすぐの場所にあります。園内には歩数計の看板があり、散歩の気分を盛り上げてくれます。ここにたくさんの動物が住んでいるのを見るのは魅力的です。とても静かで、人混みはそれほど多くありません。
●美しく、広々としていて、とてもよくレイアウトされ、世話をされています。座ってリラックスできる場所がたくさんあります。都心にいるとは思えないほどの静けさ。
●美しい庭園を散歩するのに最適な場所です。都会の中で失われた緑。美しい植物、花、木。散歩や休憩に最適な環境です。
<低評価を付けた人のコメント>
●人々は、生きた木に次々と何かを彫り込み、切断しています。正直なところ、本当に悲しい場所でした。人々が敬意や責任を感じない場合、物事がどれほど悪化するかを示す完璧な例です。木に穴を開けないという良識がないのなら、木は柵で囲うべきでしょう。自然の美しさと人間の醜さが共存している。もう二度と行きたくない。見ていて心が痛くなった。
●庭のさまざまな部分に、より多くの標識が必要です。
●適度に手入れの行き届いた庭園ですが、それを維持するためにもっと多くのことをする必要があります。
生徒たちは、実際に行って実物を見た人のコメントにハッとすることでしょう。
「落書きをした人が低評価のコメントを読んだら、どう思うかな?」
「悪かったな、と思うかな」
「自分も確かに悪いことをしたけど、自分だけが悪いんじゃない、と思うかも。他の人も書いているから」
「それはなぜ?」
「誰かがやっていたら、自分もやっていいかもって思っちゃうかも」
このような会話が展開されたら、ニューヨークの犯罪を激減させた「割れ窓理論」※1を紹介すると、さらに思考が深まるでしょう。
「割れ窓理論」という言葉を見聞きしたことがある方は、多いのではないかと思います。
「割れた窓ガラス」が放置されているような地域では、犯罪者は「犯罪を実行しても見つからないだろう」「見つかっても通報されないだろう」と思い、安心して犯罪に着手してしまうという理論です。この理論から、ニューヨーク市は「検挙から予防へ」と発想の転換をするようになりました。
つまり、犯罪者に犯罪を起こさせる機会を減らすのです。「割れ窓」を「割れ窓」のまま放置しないような地域では、犯罪者も警戒、躊躇し、実行を踏みとどまります。
このことを今回の落書きの件に置き換えると、最初に竹を彫った者が現れた後に、ブリスベン市が適切な対処法をとることで、2番目以降の落書きを防げたのではないでしょうか。
「これは、ブリスベンやニューヨークだけのことかな?」
「いや、そんなことはないはず」
「日本にも、同じような場所があるね」
このような発言から、世界遺産の熊野古道の樹木や、厳島神社の鳥居などへの落書きなどの例が挙げられるでしょう。
さらに調べると、他の場所の落書き問題も、次々と出てくる可能性があります。授業冒頭に示した1枚の写真から、さらに身近に感じられるような例を、生徒から引き出すことができます。
そして、そのような場所に憧れ、時間、金銭、労力をかけて訪れたにもかかわらず、心ない者の落書きによって一気に興ざめしてしまう気持ちを、より身近に感じることができるでしょう。
「落書きする人は、自分がここに来たっていう印、証を残したくてしょうがないんだね」
「どうしたら、落書きしたいと思っても踏みとどまることができるかな?」
発問2 この竹に落書きをしないように呼びかけるポスターを作ります。あなたなら、どんな言葉を書きますか。
●落書きは、犯罪です。
●あなたの落書きに、竹が泣いています。
●あなたが落書きしているの、全部見ていますよ。
「うーん、ありきたりかなあ」
「どれも、どこかで見たこと、聞いたことがあるよね」
「見る人の心に響かないかも」
「それにさ、落書きしようなんて夢にも思っていない人がこういう言葉を見たら、落書きを見る前にもう嫌な気持ちになってしまわない?」
このような発想が出てきたら、しめたものです。落書き防止のポスターは、落書きをしようとしている人だけが見るわけではありません。公園に憩いや癒しを求めて来た人、世界遺産を見たくて見たくて、やっとの思いで訪れることができた人……そういった人々が目にしても不快にならないようにするには、どんなポスターにすればよいでしょうか?
例えば、公衆トイレや店内のトイレに入った時に目にする貼り紙で、気持ちよく感じられるのは「きれいに使っていただき、ありがとうございます」といったものではないでしょうか。使う前に既に感謝されてしまっています。これを目にすると、「感謝されちゃってるから、そりゃあきれいに使わなくっちゃ」という気持ちにさせられませんか。※2
これを落書き防止に応用すると、「竹を大切に鑑賞してくださり、ありがとうございます」といったところでしょうか。
こういった例をヒントに、どんな立場の人が見ても「快」なポスターを考えてみると、次のようなフレーズが出てきます。
●思い出は、竹ではなく心に刻みましょう。
●あなたの自然を愛する気持ち、うれしいです。
●あなたの思いやりのおかげで、美しく伸びていけます。ありがとう。(by竹)

