「子どもの権利条約」とは?【知っておきたい教育用語】
1989年の国連総会にて採択された、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)。どのような目的で、どんな内容を定めているのでしょうか。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
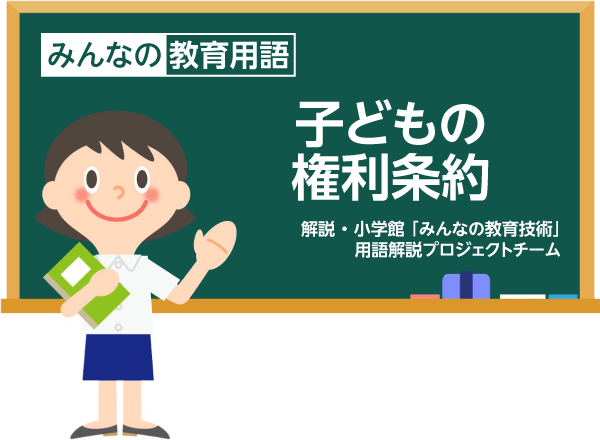
目次
「子どもの権利条約」とは?
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障することを目的に定められた条約です。18歳未満の子どもに対して、大人と同様に一人の人間としての権利を認め、成長段階における保護や配慮が必要となる具体的な事項を規定しています。日本は、条約が発効した1990年に署名。1994年に批准を行いました。
国が子どもの権利条約を締結することは、子どもの権利を守るための第一歩。すべての締結国は、子どもの権利がどのように履行されているのか、「子どもの権利委員会」に定期的に報告書を提出する義務があります。締約国は、最初は条約に加盟してから2年以内、その後は5年ごとに報告を提出することが義務付けられています。委員会は各報告書を審査し、「最終見解」という形で、締約国に対する懸念や勧告を表明しています。
子どもの権利条約の4つの原則
子どもの権利条約には4つの原則があり、条文の保障する権利と合わせて考えることが大切です。
・生命、生存および発達に対する権利
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。
・子どもの最善の利益
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考える。
・子どもの意見の尊重
子どもは自分に関係のある事項について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮する。
・差別の禁止
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由によっても差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。
子どもの権利条約は18歳未満の子どもの権利を定めています。一方で、18歳以上の人々に対して権利が守られなくなるわけではない点もポイントです。人はみな生まれながらに基本的人権をもち、その権利が年齢により制限を受けることがあってはなりません。条約で保障されている権利はいずれも、普遍的な権利であるという点を頭に入れておく必要があります。

