「主権者教育」とは?【知っておきたい教育用語】
18歳選挙権の実現に伴い、主権者教育がさらに注目されています。その目的や方法について理解しておくことが必要です。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
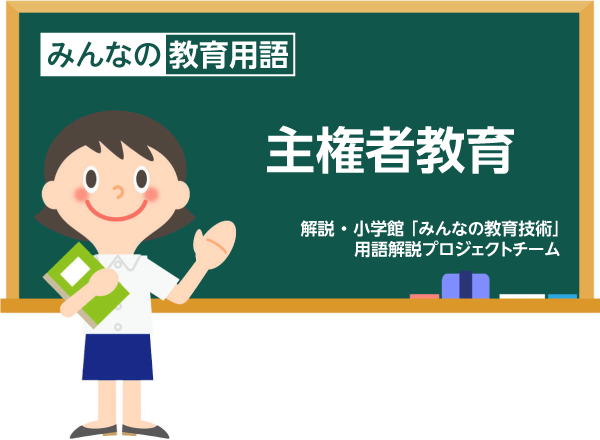
目次
「主権者教育」登場の背景
主権者教育とは、「国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成していくこと」( 総務省「主権者教育の推進に関する有識者会議とりまとめ」2015年)とされています。
平たく言えば、子どもたちが政治や社会のことに関心を持ち、それを「自分ごと」として考えた上で選挙などに主体的に参加する態度を養う教育ということです。
政府において主権者教育に係る議論がはじめに行われたのは、2009年に教育再生懇談会の下に設置された「主権者教育ワーキンググループ」です。
その後、2015年に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、2016年から施行されることで、公職の選挙権を有する者の年齢が満18歳に引き下げられました。高等学校段階の生徒の中にも選挙権を有する生徒が在籍することになり、2015年に政府は「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(初等中等教育局長通知)を発出しました。
通知では、「習得した知識を活用し、主体的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくこと」「政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象を扱うこと」「生徒が自分の意見を持ちながら、異なる意見や対立する意見を整理し、議論を交わすことを通して、自分の意見を批判的に検討し、吟味していくこと」等の重要性が示されました。
主権者教育の方法
上述の流れを受け、今般の学習指導要領では、国家・社会の基本原理となる法やきまりについての理解や、政治、経済等に関する知識を習得させるのみならず、事実を基に多面的・多角的に考察し、公正に判断する力や、課題の解決に向けて、協働的に追究し根拠をもって主張するなどとして合意を形成する力、よりよい社会の実現を視野に国家・社会の形成に主体的に参画しようとする力を育成することが重要とされました。
また、これらの力を教科等横断的な視点で育むことができるよう、教科等間相互の連携を図っていくことが重要であるとして、小学校・中学校の社会科、高等学校の地理歴史科、公民科等はじめ、家庭科や特別活動等における指導内容の充実が求められました。

