『校内研究』にどう向き合うか

よい学校とは何か? と言われたら、教員の授業技量が高いことは、その条件の一つになると思います。
そして、授業技量を上げるために、ほぼ全国の学校で行われている「校内研究」。4月下旬ごろは、今年度の校内研究の全体提案があり、中心となる研究主任は、「校長の学校づくりの『夢』のセールスマン」として、すてきなプランを出してくれているのではないでしょうか?
いかにもキラキラした、やる気ある先輩たちの世界。ひよっこの自分なんかまだまだ…なんて思ってる若手の先生も多いのではないでしょうか? いえいえ、そんなことないんですよ! 今回は、そんなお話です。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
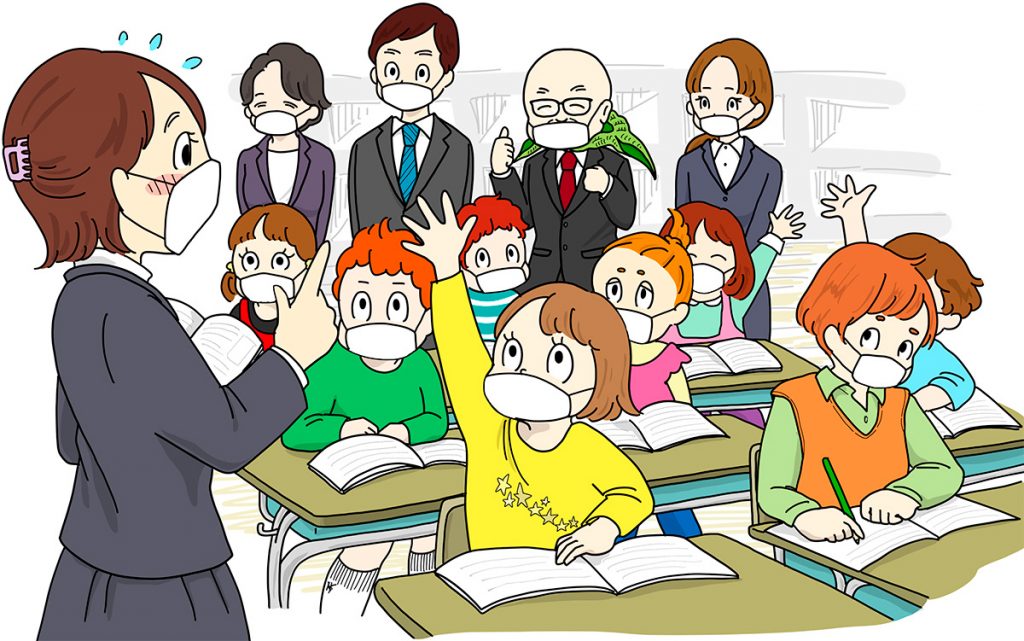
目次
1 将棋の「歩」からの出発
突然ですが、初任者の先生や若手の先生は、将棋でいえば「歩」です。わたしが小学生の頃、大雪で校庭で遊べず、休み時間に将棋をさしていると、担任の先生が対局してくれながら、いろいろ教えてくれました。
「相手の駒をとったら、とっておくのもいいけど、早く使って活躍させたほうがいいよ。」
「『歩』は早めに『と金』にした方が有利になるよ。」
などなど、その後の将棋のさし方やある意味その後の人生において役に立つ考え方を聞いたことを思い出します。
ところで、ちょっと難しい病気でお医者さんを選ぶとき、「○○の手術何件実施」など、数でその医療機関の信頼情報を得ることがあります。何件の手術実績があるから専門のドクターがいるようだ、じゃお願いしてみようかと考えていきます。
授業力向上、授業技量アップを考えたら、たくさんの研究授業をこなし、目が利く先生にみていただきアドバイスを受け、修正してどんどん高めていきたいものです。これは、お医者さんの手術件数と共通するところがあるように思います。多くの研究授業を経験をした先生が授業力は伸びていきます。
ですから、「校内研究」が進んでいく中で、機会があればどんどん授業提供者に立候補して、研究授業を経験してほしいです。成功しても多少失敗してもそれはそれで勉強になります。「失敗は成功よりもよい経験値を得られる」とも言われます。1年間に何本研究授業やそれに類する授業をしたかをきちんと記録して実績として残しておけばいいのです。研究授業とまではいかなくても、ちょっと気合いを入れた授業づくりをし、その授業を校長先生はじめベテランの先生に参観していただきアドバイスをいただくということもいいと思います。「研究授業○本実施」という自信につながっていきます。
昨年度の勤務校では、各学年部で若手の先生が「はい、やります!」と3秒で手を上げ、「じゃ、お願い。」と5秒以内に授業者が決まっていました。
2 校内研究とは
「校内研究」は、別に「学校研究」ということもあります。これは学校建築研究など広い概念をともないます。ですから、わたしたちが取り組んでいるものをもう少し極めると本来は、「学校の教育実践研究」というワードがしっくりくるかもしれません。
この「学校の教育実践研究」ですが、わが国の長い歴史の中で、さまざまな方法でやられてきました。それらを概観すると位置づけ(形態)論としては以下のようにとらえることができそうです。
① 学校経営における重点化(重点教科、重点領域)
学校では年間1000時間ほどの授業や学校行事、その周辺部のさまざまな指導を行いますが、すべて全力疾走ではなかなかできにくいです。そこで、今年度はここに重点をおいて学校づくりをしていくぞという教科や領域、テーマを設定して取り組みます。
② 新しい教育(授業)の考え方の探求
日進月歩のわが国の教育界。最近はギガスクール構想から授業スタイルもだいぶ変わってきました。今まで培ってきたものを基盤にしてどんな授業を目指すかを探求していきます。
③ 授業力向上のための研修
最近は、若い先生が増えてきたこともあり、個々の授業力向上に着目したスタイルの校内研究も増えてきました。児童生徒と同じような学び合いで授業力向上をめざします。
そして、目的論からすると
① 教職員の授業力向上
前述したとおり、授業力は「歩」より「香車」「桂馬」。それより「金」「銀」、さらには「飛車」「角」級だとなおさらいいですよね。自ら授業をする、授業をみて自分の授業に生かす、さらにはさまざまな論点を議論することで授業力を伸ばします。
② 児童生徒の学力向上
「校内研究」の成果の指標のひとつが、実践の成果としての児童生徒の学力向上です。指標としては、点数の伸びがあげられますが、テーマにもとづいた児童生徒の成長した姿も大きな評価指標となります。
③ 学校経営の活性化のために
校長先生は、まさに学校づくりの中で教職員や児童生徒のがんばりを後押しする戦略として、「校内研究」をとらえています。「校内研究」に全職員で取り組むことで学校が活性化していきます。
といったことでしょう。
位置づけ(形態)論、目的論の①~③のどれに重きをおくかは学校の課題によって違いますが、ほぼこの3つが絡み合っているのではないかと思います。そこに、さまざまな手法が出現してきて工夫が凝らされています。
以前は、負担だなあ、負担だろうなあと思いつつどうにか授業者が決まり、授業者が授業を提供(公開)し、参観者からいろいろな意見を頂戴し、最後に助言者がまとめ、役職にある方がお礼をいうという一連の流れがありました。これは、形式先行でちょっとたいへんでした。
最近は、リフレクションや付箋紙やボードによる意見交流など参観者が積極的に関わって授業者を盛りたて学び合うというスタイルが多くなってきて、授業提供者としてもだいぶ楽しみが増えてきたように思います。多くの学校では授業提供者がいちばん得をするように考えています。

