「こども家庭庁」とは?【知っておきたい教育用語】
2022年2月25日に設置のための法案が閣議設定され、話題を集めている「こども家庭庁」。どのような目的で創設され、今後どのような役割を担っていくのでしょうか。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
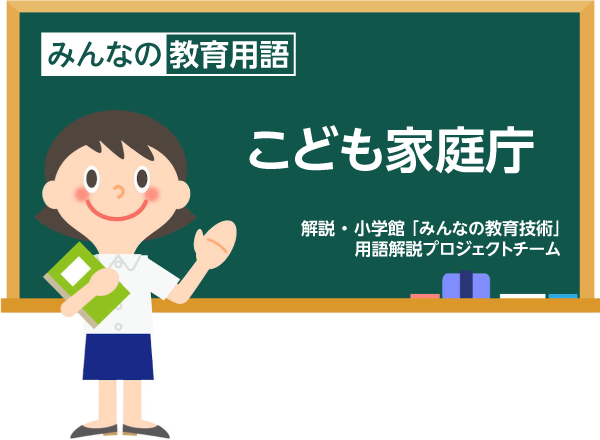
目次
「こども家庭庁」とは?
こども家庭庁は、すべての子どもが、自立した個人として、平等に、健やかで、幸せな状態(Well-being)で成長することができる社会の実現をめざし、子どもや子育て当事者の視点に立った政策立案や、子どもや家庭の抱えるさまざまな課題に対する包括的支援を行うことを目的に、2023年4月1日に設置される国の行政機関です。ここでの「こども」とは、年齢にかかわらず、「大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの心身の発達の過程にあるもの」と定められています。
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~」では、創設の目的として、常に子どもの最善の利益を考え、子どもに関する取り組みや政策を社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、次の基本理念を定めています。
●こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案
●すべての子どもの健やかな成長、Well-beingの向上
●誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援
●こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援
●待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換
●データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクル(評価・改善)
「こども家庭庁」創設の目的と役割
こども家庭庁の目的は、これまで文部科学省、厚生労働省、内閣府などの各府省に分散していた子どもに対する行政業務やこども政策に関する総合調整権限を集約し、司令塔としての役割をもたせることにあります。その結果、制度や組織による縦割りの壁、年齢の壁などを越えた切れ目ない包括的な支援を実現させることをめざしています。
例えば、内閣府の子ども・子育て本部や厚生労働省の子ども家庭局は移管され、廃止となります。一方、幼児教育や義務教育の振興や、学校におけるいじめ防止や不登校対策はこれまで通り文部科学省が、医療の普及および向上や労働者の働く環境の整備などは厚生労働省が担い、こども家庭庁と密に連携を取りながら進めていくことになります。

