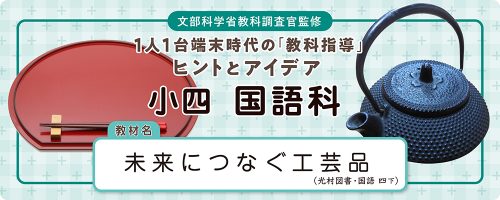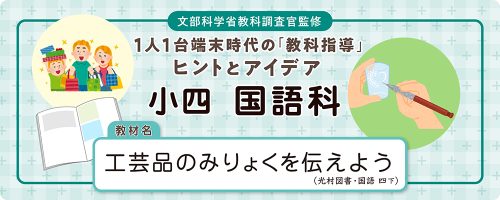小2算数「長さ」指導アイデア(4/7時)《1mぴったりの長さをつくりましょう》
執筆/富山大学人間発達科学部附属小学校教諭・羽柴直子
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県公立小学校校長・中川愼一
目次
本時のねらいと評価規準
(本時4/7時 長さの単位「m」を知り、1m=100cmの関係を理解した後)
ねらい
身近な物について、長さの見当を付けたりその長さを確かめたりすることを通して、物の長さについて考える。
評価規準
身の回りにある1mに相当する長さの物に着目し、そのいくつ分にあたるかを見積もり、身の回りの物の長さについて考えている。(思考・判断・表現)

問題
1mぴったりの長さをつくりましょう。
1mという単位を使ったら、長い物でも小さな数で表すことができましたね。身の回りの物をつないで1mぴったりの長さをつくることはできそうですか。
教科書を縦に4冊つなげたぐらいかな。
机を2つ縦につなげたぐらいかな。
つくった長さが本当に1mになっているか、1mものさしで確かめてみましょう。
教科書の縦の長さ4冊分だと、1mよりも消しゴム1個分ぐらい長いね。
机2個分の縦の長さだと1mに届かないよ。あとグー1つ分でぴったり1mになるね。
1mがだいたいどれぐらいか分かってきたよ。地面から僕の肩の高さぐらいだよ。
子供たちは、自分の体の一部や身の回りの物の長さを頼りにしながら、1mの長さの感覚をつかんでいきます。そのような状態になったところで、「教室にある物の長さを、1mを基にするとどれくらいになるのか調べてみましょう」と投げかけます。
学習のねらい
1mをもとにして、ものの長さを調べよう。
見通し
- 1mをつくる活動や、前単元の手や指で10cmをつくった経験を生かして見当を付けよう。
- 見当を付けた長さが正しいかどうか、1mものさしを使って測ってみよう。
自力解決の様子
A つまずいている子
あてずっぽうで予想をしている。
B 素朴に解いている子
1mより長いか短いかで予想している。
C ねらい通りに解いている子
1mをつくる活動や手や指で10cmをつくった経験を生かして予想している。
学び合いの計画
イラスト/松島りつこ・横井智美
『教育技術 小一小二』2021年1月号より