GIGAスクール時代の板書の役割とは?|樋口綾香のGIGAスクールICT活用術㉓

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 今回は、ICTの活用が進む中での「板書」の役割について考えます。
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
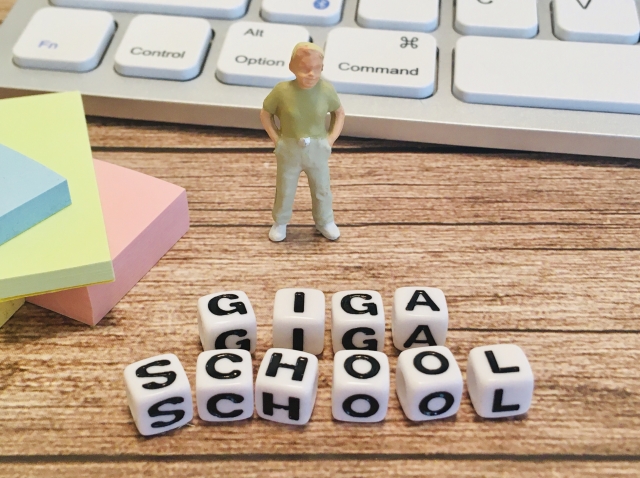
目次
はじめに
私の勤務校では、昨年の6月から積極的にタブレットを活用し始め、11月には1人1台のタブレットが行き渡りました。それからおよそ1年間、「毎日授業内で使うこと、毎日タブレット課題を出し、持ち帰ること」を学校全体で実践してきました。
とにかくタブレットに慣れよう、使ってみようという時期を乗り越え、今は、「効果的に」「選択的に」使う方法を見極めて授業で使用しています。
そんな中、この1年間での研究授業を通して、いろいろと考えさせられたことがあります。
それは、「板書には何を残すか」「教師の役割に変化はあるか」「ノートとタブレットはどう棲み分けるのがよいか」「教科の特性とICTの特性は、どのように関連するか」といったことです。
今回は、これらの中から「板書には何を残すか」について、私の考えを述べたいと思います。
板書の役割
板書は、子供たちの学習活動を支える役割をもっています。
- 何を学ぶか(学習課題の把握)
- どのように学ぶか(思考表現の場)
- 何ができるようになるか(学習内容の理解)
これらを子供たちに保証するために、板書をすることで学びやすい環境をつくり、効果的な指導へとつなげます。
しかし、ICT活用が進むと、授業の後半になっても板書に何も書かれていない、あるいは活動の流れだけが示してある、ということが増えました。
このような状況で、子供たちの学習活動は本当に保障されているのでしょうか。

