【指導のパラダイムシフト#14】指名のパラダイムシフト


池田修先生×藤原友和先生による好評連載。第14回のテーマは、「指名のしかた」です。 授業における指名は、目的に合わせてその方法を使い分けなければなりません。今回はまず、指名法を9種類に分類し、細かく解説していきます。
執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。
目次
第14回のテーマは「指名のしかた」
教師主導型の授業は、指導言を使いながら進めていきます。これは、大西忠治氏が整理したもので、指示、説明、発問の三つを指します。簡単に言えば、指示は、学習者の動作に対する命令。説明は、事物について詳しく明らかにすること。発問は、説明できる内容を、質問の形に変えて学習者に問い学習者の答えを引き出していく方法です。
この三つは、これまでの授業づくりにおいて、基本的な事項として理解されてきています*1。今回は、この中の発問に関わって、指名のしかたについて考えてみましょう。
Q1. 次に示すのは、訂正の必要な教師の指名のしかたです。どこがおかしくて、なぜおかしいのかを考えてください。
Q2. また、どうやればいいのか、実際の指名のしかたを考えてみてください。
訂正の必要な指名方法の例
授業は、小学校3年生、社会科の地図記号の学習のようです。
「さて、みんな、実は地図記号は新しいものが最近加わったのを知っているかな? 最近といっても、君たちはまだ生まれていないか(^^)。
この地図記号は2006年にできたんだけど、なんの地図記号か分かるかな?」

「そうだなあ、窓側の人に聞いていこうか。野田さん?」
「分かりません」
「そう。では、今井さん?」
「分かりません」
「そう。では、小川くん?」
「犬小屋?」
「さすがに、それはない(^^)」
「藤田さん?」
「老人ホーム?」
「はい、正解です。では、これはなんでしょうか? これは、2019年に加わりましたね」
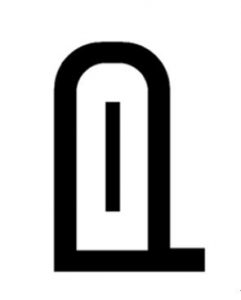
「山川くん?」
「知りません」
「吉川さん?」
「分かりません」
「渡辺さん?」
「ドラクエウォークで休憩できるところ」
「違います(^^)。 山田さん?」
「分かりません」
「誰か分かる人いないですか?」
「はい」
「石川くんどうぞ」
「自然災害なんとかだったと思います」
「をを、すごい。そう、自然災害伝承碑です。みなさん、分かりましたね」
あなたの考え
A1.
A2.
どこがおかしい、なぜおかしい
授業を見ていて、一番がっかりするのがこの種の指名方法です。私は、これを「正解を拾ってつないでいく授業」と呼んでいます。
授業の流れを見てみると、先生は児童に順番に指名をしているようです。そして、児童が分からなかったら、その児童を飛ばしていきます。そして、次も分からなかったら、その児童も飛ばしていきます。どんどん飛ばしていって、正解を言う児童までこれを続けます。老人ホームについても、自然災害碑についても同じように授業を進めています。
この授業の様子からは、地図学習を一通り終えた後の、発展課題のようにも見えます。そうであっても、これは違うと私は考えています。
これは、何が問題なのでしょうか。
この指名のしかたで授業を進めていくと、この答えを知らない児童は、知らない、または、分からないとだけしか言うことができません。
授業は、児童たちが、知らない、分からない、できない状態でいるのが当たり前の状態です。ですから、「知らない、分からない」と答えるのは当然なのです。そこから「知った、分かった」に引き上げるのが指導なのです。
ところが、この「正解を拾ってつなぐ授業」では、「知らない、分からない」の児童はそのままに置き去りにされます。そして、「知っている、分かっている」児童を探して答えを言わせて終わりにしています。
ちょっと考えればすぐに分かることですが、この「知っている、分かっている」児童は、授業の前にどこかでこの知識を手に入れてきていたわけです。となると、この授業は、授業なのでしょうか?
知らない分からない児童は、そのままになっています。また、知っている分かっている児童は、授業外でその知識を得ています。先生がしたのは、正解を知っているであろう児童に、適切なタイミングで答えが出るように順番を考えて指名しているだけではないでしょうか? 「みなさん分かりましたね?」と確認していますが、それはまあ、知っている児童から言われたので分かったと言えば、分かったのでしょうけれども、単なる知識を知っている児童が披露しただけではないかなあと思うのです。もう一度言います。これは、授業なのでしょうか?
では、どうしたらいい?
まずは、指名の種類を理解することです。そして、目的に合わせて指名のしかたを変える。また、その指名によって出てきた児童の発言に対して、適切な対応をしていく。つまり、ファシリテーションとフォローです。これが発問を中心とした授業を行う際には重要になります。
まず、指名の方法について考えてみましょう。ざっと9つの方法があると考えています。
- 無指名(自由発言)
- 挙手指名(挙手発言)
- ノート確認指名(ノート発言)
- 籤引き指名
- 列指名
- 座らせ指名
- 児童による指名
- 教師の意図による指名
- 小グループで話し終えた後指名
それでは一つ一つ見ていきましょう。
- 無指名(自由発言)
教師が、発言の目的や目標を与えた後、児童に任せるスタイルです。教師は、児童を指名することはありません。児童は、お互いの発言を聞きながら、自分で発言するタイミングを図った上で発言します。かなり高度なスタイルです。 - 挙手指名(挙手発言)
一般的な方法でしょう。教師が発問をし、それに答えられる児童、答えたい児童は手を挙げて、教師の指名を待ちます。学習者の理解度や意欲を簡単に確認することのできる方法でもあると言えます。しかし、挙手する児童が固定してしまったり、手が挙がらなくて授業が進まないこともあります。また、低学年などでは大人数が挙手をするため指名する人数が限られてしまうという弱点もあります。 - ノート確認指名(ノート発言)
発問をした後、ノートに児童の考えを書かせ、それを教師が机間巡視して確認します。その後、どの順番で指名するのがいいのかと教師が構成した後、児童をその順番で指名していきます。少数意見の児童から指名するのがいいでしょう。また、教師の予測(予定)していなかった考えを書いている児童の答えは、ぜひ取り上げてください。思わぬ展開になって授業がエキサイティングになることが多いです。 - 籤引き指名
割り箸などに出席番号を書いておいて、それを筒に入れて、籤を引くように引き、そこにある番号の児童が指名を受けるというものです。教師の意図を入れず、ランダムに指名するには適しています。一度引いた籤を元に戻すか、戻さないかでも違いがあります。低学年は発言したい児童が多いものです。まだ発言していない児童にチャンスを与えるために、1回発言した児童の籤は、籤の束に戻さないほうがいいでしょう。また、籤に些細な違いがあると、じつは児童は結構見ているので、先生、贔屓している! と言われることもあります。贔屓などしていなくてもです。 - 列指名
縦の列、横の列で順番に指名します。班を指名して、その班員全てに聞くという形もあります。これは、単純に答えのサンプルを集めたいときに使うことが多くあります。賛成、反対、その他と考えを言わせて、なぜなのかの理由を言わせる。そのようなときに有効です。また、答えさせたい児童がいるとき、直接その児童を指名してしまうとプレッシャーがかかりすぎるときなどにもこの列指名を使います。指名したい児童が含まれている列や班を指名することで、弱めることができます。 - 座らせ指名
全員起立させておいて、自分と同じような発言をした児童がいたら、座ると言うものです。そうすると、最後に少数意見が残る形になります。ユニークな発想が尊重される場面では、この少数派を残す「座らせ指名」は有効です - 児童による指名
発言した児童が、次の発言者を指名できます。集中砲火を防ぐため、また、一度も指名されない児童を生み出さないために、一度指名された児童は2回指名されることはないとか、3回までは指名できるなどのルールを決めておく必要があるでしょう。 - 教師の意図による指名
児童の興味関心、知識や能力に応じて(この発問に答えられるのは、この児童だろう)と予測を立ててする指名です。これが自然に行われれば、そのクラスを生かしたその担任ならではの授業展開になると思われます。しかし、下手をすると贔屓だと思われることにもなります。「今日は何日だから、出席番号が~番の人」というのは、偶然でやることもあります。しかし、偶然を装っておいて特定の児童を指名するという、教師の意図を反映した指名も可能になります。児童の出席番号を予め調べておいて、その日付に行うということができるからです。 - 小グループで話し終えた後指名
個人で考えさせ、小グループで話し合わせた後、そのグループの考えを示すように指示します。個人のカラーが薄まるので、あまり人間関係のできていないときなど個人を前面に出さないほうがいいときや、小さなコミュニケーションをたくさん行わせたいときなどに使います。ノート発言と同じように机間巡視で内容を確認し、構成して指名していきます。
おっと。予定の文字数を超えてしまいました。
今回はここまでです。この後、続きます。
*1 今後、学習者主体の授業になっていくと、指導言と同じように「評価言」が大事になってくると考えています。これについては、また稿を改めて考えてみたいと思います。

