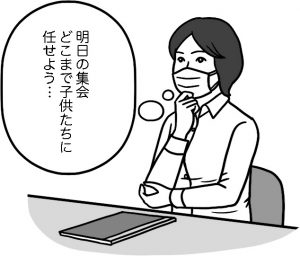子供とのコミュニケーションで学級の荒れ・乱れ防止【二学期後半】
クラスが乱れがちな11月。今年度の後半を子供たちと楽しく過ごすために、クラスを落ち着かせる「子供との関わり方」について考えます。ここでは、二学期後半に気を付けたいことをまとめました。
お話しを伺ったのは…
神奈川県公立小学校校長・小嶋千里
岐阜県公立小学校教諭 杉本大昂

目次
クラスの荒れに気付いたときは子供との関わり方を見直す機会
11月、学級の乱れを感じると、担任の先生は不安な気持ちになるでしょう。同じように子供たちのなかにも、不安な気持ちを抱えている子や困っている子が必ずいます。「クラスが乱れてきたかも」と感じたときこそ行動のとき。
二学期後半とはいえ、きちんと子供との関わり方を見直したり、新たな活動を取り入れたりして、荒れを防ぐ手立てを打ちましょう。
今は感染症対策で、朝会など全校で集まる機会がほとんどなくなりました。一堂に会す場や学校全体のなかで指導されたり、「〇年生らしく、しっかり整列しよう」「低学年のお手本になろう」といった、自分たちの「あるべき姿」や「なりたい姿」を感じたり、「さすが〇年〇組さん、すばらしい姿勢ですね」とほめてもらったりと、クラスをより大きな集団の中で客観視する機会が減りました。同じように、縦割り活動など異学年との関わりも、これまでと質も量も変わりました。コロナ禍により、「外からの目」を感じづらくなったことは、クラスの荒れにつながる要因として注意が必要です。
(小嶋千里)

荒れの原因を探るには「集団」と「個人」の視点をもって見る
子供たちを漫然と見ていても、クラスの荒れの解決の手立ては浮かんできません。明確な視点をもって観察し、原因を探りましょう。
しかし原因は一つとは限りません。「一人ひとりはよいのだけれど、集団になるとまとまらない」など、「クラス集団として見る」「個人として(特性や背景まで)見る」と、二つの視点をもつことで対応策も変わってくるでしょう。 また中学年も後半となると、4月よりも学級集団がぐっと成長し、初めは担任主導だったことを、子供たちの手に委ねていく部分が増えていくと思います。とはいえ、全て子供たちに任せられるわけではありません。「どの部分をどのくらい任せよう」というさじ加減が学級経営の肝とも言えます。集団へのさじ加減と個へのさじ加減。それは毎日いっしょにいる担任の先生だからこそ感じられる加減です。
(小嶋千里)