プロ教師は『声のスピード』で子供に与えるインパクトを自在にする
教師が使いこなすべき”6つの声“③
教師は『話す仕事』、意図的に声を使い分けるのがプロの教師です。――と語るのは、小学校教諭・熱海康太先生。各界の「話のプロ」の技術を授業や学級経営に活かす「教師が使いこなすべき6つの声」とは? その教育的効果と効果的な使い方について教えていただきました。話を聞かない(聞けない)子供たちにも伝わる「声」を手に入れる極意を、「教師が使いこなすべき”6つの声”」全3回の連載でお届けします。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
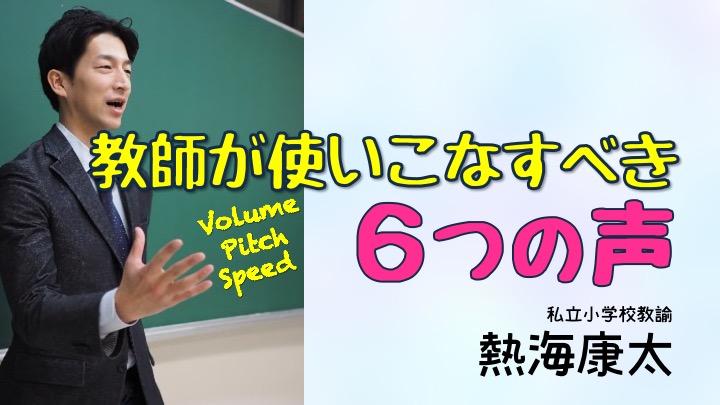
目次
「速い声」と「遅い声」
教師が使いこなすべき声は、6つあります。
そのうちの「大きい声」「小さい声」「高い声」「低い声」の効果や留意点については、第1回、第2回の記事がありますので、読んでいただければ幸いです。
ここでは「速い声」「遅い声」について、解説していきます。
早口は基本的に、説明には不向きとされていますが、それをあえて使うことで指導のねらいが達成しやすくなる場面があります。
使っている人が少ない話し方だからこそ、「速い声」をバリエーションとして備えることは、あなたの秘密兵器になる可能性があります。
少し遅めに噛み締めるように話すことは、子供たちの理解を促す上で王道の方法です。
ただし、それをなんとなく行うのと、効果を意識して行うのとでは、教育的効果は大きく変わってきますので、きちんとそのメリットを理解しておきたいものです。
「速い声」の効果
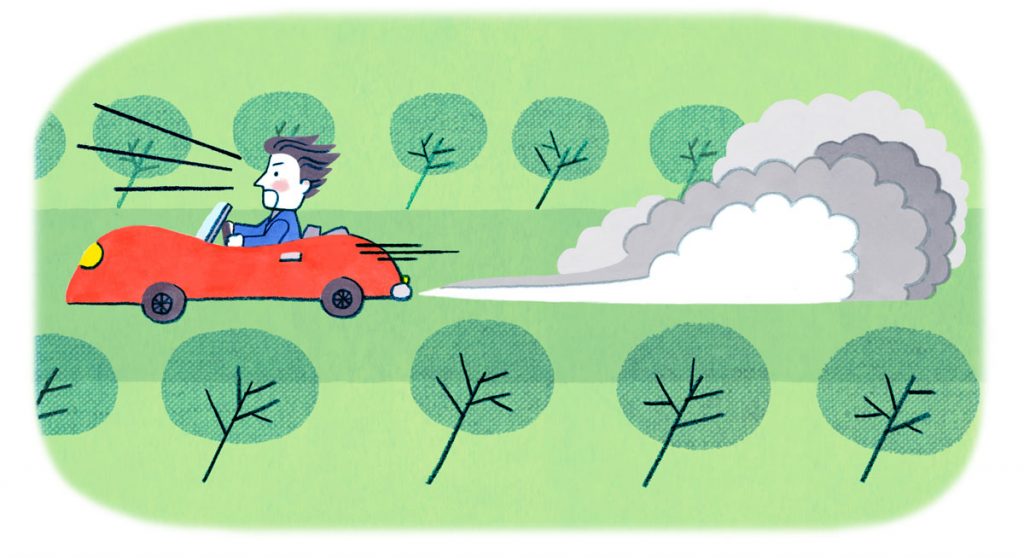
世界は高速化しています。
子供たちがよく見ているアニメも数十年前と比べると、実に多くの情報量が詰め込まれています。
早口というと、依然「慌てていて理解しづらい」「緊張しているのかな」と、どこかネガティブなイメージを抱く人もいる一方で、お笑いコンビのキングコングさん、メンタリストのDaiGoさんなどは、速い話法でも注目され、頭角を現しました。
速いスピードで話すことは、特にこれからの時代には、武器になることが多いのではないかと考えています。
考える隙を与えずに一気に情報を伝える! キレ者の「速い声」
実際に、速い声で話すメリットは多いです。
まず、速い声で話すには言葉を詰め込まなくてはならないですし、その分だけ頭を回転させる必要もあります。
ですから、分かりやすい「賢さ」を表現することができます。
台本も見ずに、早口で、多くの情報を伝える人には、その内容の精査の前に、「速くてなんだか単純にすごいなー」という感想を持つことがあるでしょう。
お笑いコンビのキングコングさんの漫才を見たことがあるでしょうか。始めのほうは、通常の漫才と同じようなスピードで展開されていきますが、中盤から終盤にかけてどんどんスピードアップしていき、最高速で幕を閉じます。
面白さも当然感じているのですが、それ以上の正体不明な満足感に包まれます。
よく考えれば、作りこまれたネタ、そのスピード感を用いようとするセンス、これを完成させるための膨大な練習量など多くの要素が考えられると思います。
ただ、それをなんとなく感じさせながらもじっくり考える暇を与えることなく、とにかく圧倒することで、凄さが全く言語化されていない「速くてなんだか単純にすごいなー」という感想を感じさせるのです。
メンタリストのDaiGoさんは自身の配信するYouTubeにおいて、「考える暇を与えることなく」という部分を、新しい説明のデメリットを解消するために使っていると言っています。
人は、生命の維持のために、変化を嫌う生き物です。
ですので、新しい画期的な情報を与えられたとしても、何とか、現状維持の方向に自身の考えを持っていきがちだと言われています。この処方箋になるのが、速い声だと言うのです。
新しく画期的な情報を、じっくりじっくりとかみ砕くように語ると、反対の意見を考える暇を与えてしまいます。
逆に言葉の洪水の如く、早口で情報を与えることで、その隙を与えないのです。
情報量を意図的に絞り、ポジティブな思考の道筋を作る「速い声」
これを学校現場に転用するのであれば、騙すようなねらいで使うのではなく、「あえてはっきりと伝えないことでポジティブな思考の道筋を作ってあげること」になります。
プライドの高い子や繊細な子に対しての助言については早口でサラッと伝えたとしても、その子の心の中にはしっかりと残っています。それを、逆にじっくりと伝えてしまうと、「悔しい」という別の感情が児童の思考を邪魔してしまうのです。
そうならないために、伝え過ぎない(マイナス感情を必要以上に抱かせない)ということが重要なのです。信頼が厚いカウンセラーは、こぞって早口だというのも、この辺りが理由だと考えられています。
ただ、子供たちにじっくり理解させたい場合は、やはり「大きい」「ゆっくり」が大切です。速い声の部分は、小さい声と同じように、アクセントになるように活用すべきでしょう。

