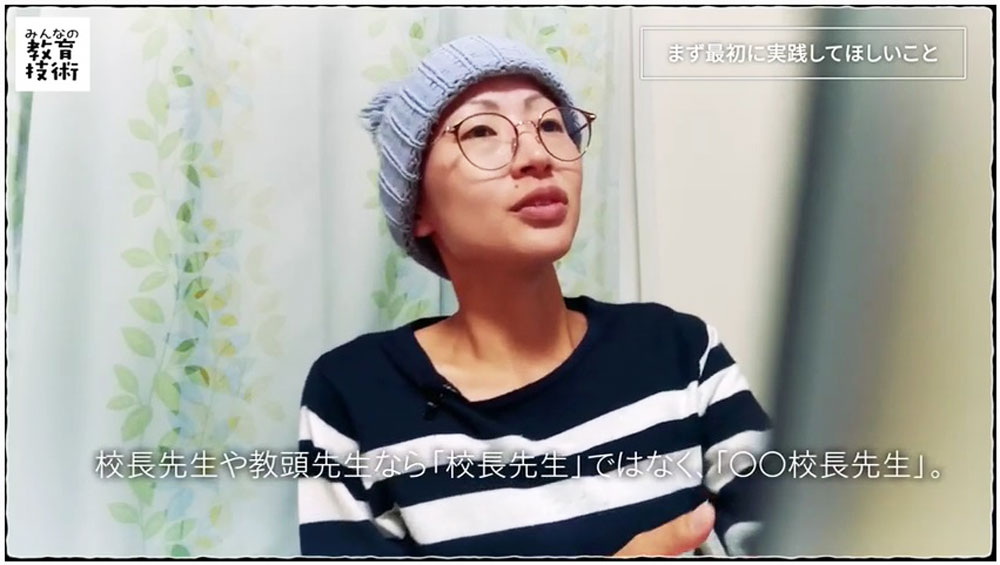職員室を居心地よくするために実践したい“大切なコト”【動画】

多くの若手教師から慕われる小倉美佐枝先生が、連載記事「令和2年度新任教師のリアル~実習と通常授業の間にある大きな壁~」を読んで、アドバイス!
今回のテーマは“職員室”。気持ちよく過ごせる場所にするため、ミサエ先生が日々実践しているコトとは⁉ 人間関係でお悩みの先生方、ご一読ください!
目次
忍法!そこにいていないの術
職員室といえば、先生方が共に過ごす場ですよね。長い時間、一緒にいるわけですし、いろいろなことがあります。
この対談記事にあるように、口調の強い先生がいて少しビクビクしてしまう。その先生のピリピリした雰囲気が職員室内に広まっていく…。子供たちの教室でもそんなことってありますよね。人と人がつきあうということは、うまくいかないことがあるというのが大前提です。
職員室がピリピリムードになった時、私はいつも、“忍法!そこにいていないの術”を使って、いないフリをして仕事をしています。とはいえ、つい他の先生に話しかけてしまうので、多分この術は効いていないと思いますが(笑)。
また、もし当該の先生と接する際は、今は触れてはいけないなと思うところは触れないようにして、違う内容の話を投げかけたりしています。
私はどちらかといえばポジティブなので、今日一日をどうにか過ごして、明日また元気に過ごせる職員室にしたいなぁと思うんですよね。
みんな仕事がしんどいのも一緒だし、忙しいのも同じ。そこを「どうやったら楽しくなるかな」と、考えながら関わっているつもりです。
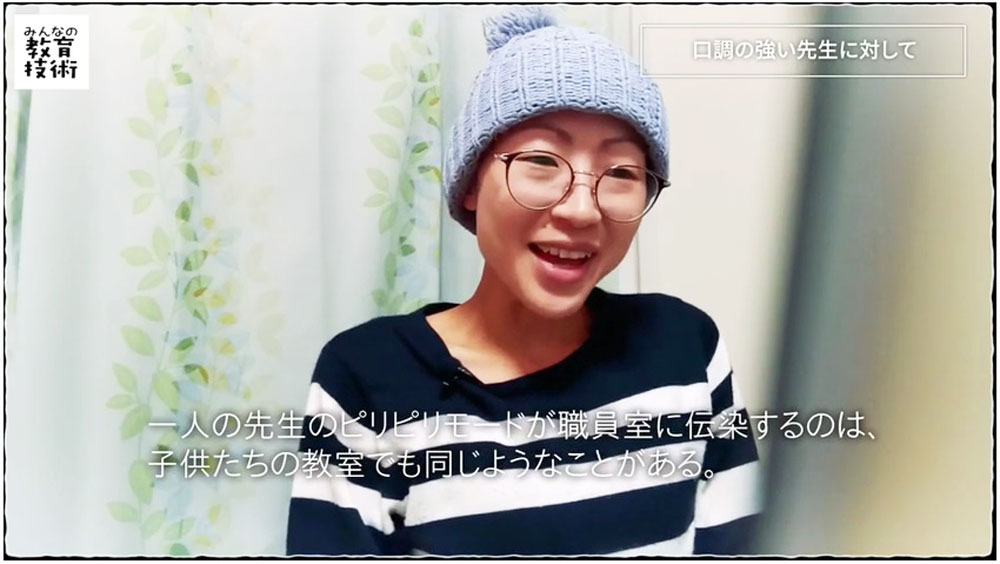
名前で呼ばれたらきっと嬉しいはず
若手の先生に私からアドバイスするとしたら、「しつこいくらい、周りの先生方と交流しておいた方がいい!」ということですかね。それも職員室の中だけではなく、事務室や保健室、給食室の方たちとも積極的に関わってほしい。
これは戦略的ではあるのですが、若手の頃ってうまくいかないことも多いじゃないですか。何かをしたいと思っても、ベテランの先生に比べたら信頼もまだ薄いですし、「やってみなよ」といつでも快諾を得られるわけでもありません。
やっぱり信頼って関係性の中で築き上げられていくものだと思います。だから積極的に関わって交流を深めて、「まぁ、ミサエ先生ならいいかな」と認めてもらえるチャンスを自分で作ります。 自分のことをよく知ってもらうために、私は自分から関わっていきますね。
関わる上で何よりも、名前を真っ先に覚えるようにしています。そして会話や挨拶でも「〇〇先生、この間~~~」と、名前を言うように心がけています。
特に名字ではなく、下の名前を呼ぶようにしています。校長先生や教頭先生なら「校長先生」ではなく「〇〇校長先生」と名字もつけ加えます。時には校長、教頭の役職をつけないで呼ぶときもあります。
なぜって、名前で呼ばれたら嬉しいじゃないですか。これって嫌われないためにではなくて、私はかわいがられるために実践しています(笑)。
“嫌われない”という言葉に対してその対処法を考えたとき、“しない”がつく言葉が多いかと思います(例:怒らない、反論しない…等々)。
“しない”という言葉は禁止や抑止という意味合いが強いし、それを悪化させないためということもあると思います。私のなかではちょっと前向きじゃない気がするのです。
だから私はなるべく“する”という思考に切り替えて、明るく、楽しく過ごせるためにどうすればいいかを考えて行動しています。