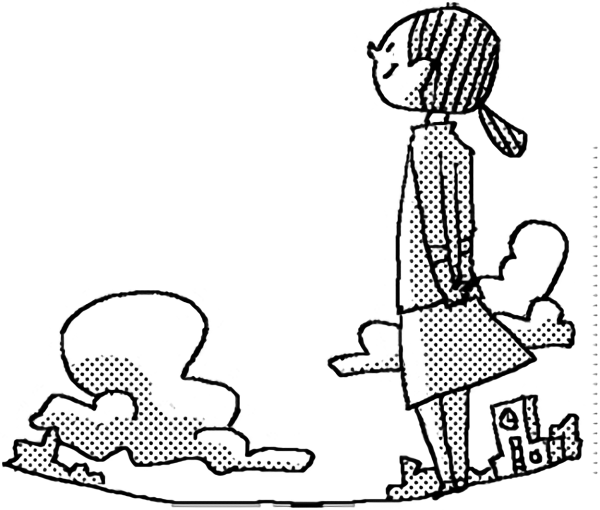担任教師のやる気を引き出す!校長・副校長・教頭の職務のポイント

校長、副校長、教頭の管理職は随時、年度当初の学校経営目標に向かっているか、また軌道修正の必要性があるかなどを確認する必要があります。 埼玉県川口市立公立小学校校長・熊谷茂樹先生に、担任教師のやる気を引き出す管理職の職務のポイントをまとめていただきました。
目次
校長の職務のポイント
現場に足を運び、自分の眼で見る
これまでに授業中だけでなく皆さんは何回教室を訪問したでしょうか。学校経営の基盤は学年・学級経営です。その現場に足を運び、自らの眼で見ることは、最高経営者である校長の仕事です。
見て、感じて、かかわる
教室に一歩足を踏み入れれば、学級の空気感・雰囲気を感じることができます。誰もいない教室であっても同じです。4月当初から床にごみが落ちている、黒板が汚れている、掲示物がはがれている、机が乱れ、ロッカーが乱雑な教室は、教師と児童、児童相互の人間関係に乱れが生じる兆しです。給食や清掃指導の時間帯は空気感・雰囲気を感じ取る絶好の機会です。
今月は課題のある学級に足しげく通い、具体的な改善策を担任に指導することになります。学年主任や副校長・教頭に担任に指導するよう指示します。校長が直接指導します。「荒れ」が顕在化してからでは遅いのです。範となる経営があれば、それを皆で共有するための策を講じます。5月――校長室に籠もっている時間はありません。
基本は「ほめる」こと
学校として、学年として朝の会、帰りの会、給食や清掃指導、学級掲示のガイドラインがあります。これを「指導できて当たり前」にせず、「できていればほめる」のです。担任に直接声をかけます。「この学級のここがよい」を校長だよりにして配布します。課題があり、指導した後は改善を見届けます。そしてほめます。見事に整っている清掃用具ロッカーを撮影し、校長だよりでほめるのは、乱雑な教室を経営している担任への指導資料にするためです。
学級経営で重要なのは集団マネジメントです。高圧的な指導や同調圧力を求めるマネジメントは必ず綻びます。児童が相互に認め合い、支え合うための取り組みがあれば、そのスキルではなく、それを支える教育的愛情の「イズム」を絶賛したいものです。