GWは読書で危険な旅へ!隂山英男先生の「ヤケド本」とは?
どこにも行けない今年のGW。旅に出るかわりに、自分の人生を変えてしまいかねない危険な本に手を伸ばしてみるのはいかがでしょうか? 「僕は読み出すと止まらなくなるところがあって、最近は少しセーブしているんですよ」 読書とは、死ぬほど活字を追いかけることだと語る隂山英男先生に、いまの教育哲学の礎になっている本について、教えていただきました。
(『小一教育技術』2014年6月号より再構成しています)
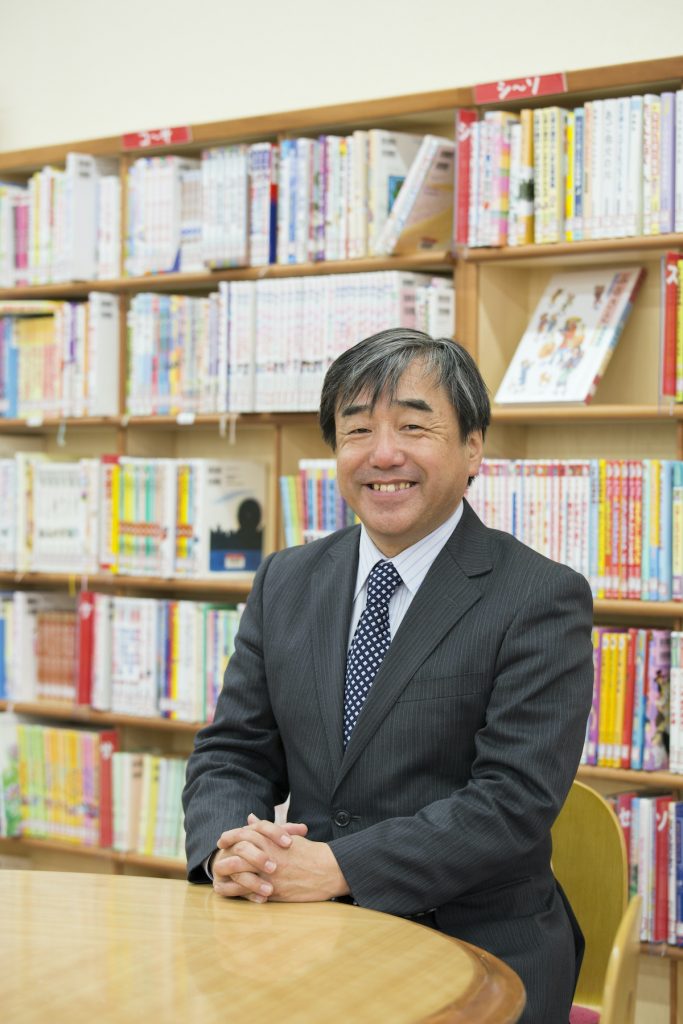
目次
読書とは「止まらないもの。中毒」
僕は人生で2回ほど読書中毒になったことがあるんです。変な言い方かもしれないけど、自殺したくなるくらい活字を追いかけてしまうような感覚でした。
一度目の読書中毒は、17、18歳の頃。僕は、小説よりも詩集を読むことが多かったですね。「永遠というもの。
大学入試は倫社で受験したということもあって、哲学書はものすごく読みました。サルトル、ハイデッガー、ニーチェ、キルケゴール……等々。西洋哲学の本は、面白かったし、いろいろなことを考える材料にはなったけれど、最後までピンとくるものがなかったんです。
「人が人を幸せにする」ある意味傲慢な教職という仕事の意味を考えた
そんな時、三木清さんの『人生論ノート』に出合いました。
その中に、『日本人のいろんな哲学の中に幸福論がない』という一説があるんです。それは、後に僕が教師になってから今までずっと底流にあるテーマをくれた言葉でした。つまり、日本の社会は、全てのものが揃っているようでいて、ただ一つ幸福だけがない。それならば、いい教育というのは、子供たちに幸福になってもらうことだ、というね。
また、この時期に一番読んだのは森本哲郎さんの本で、「旅シリーズ」は全部読んだのですが、中でも『生きがいへの旅』で書かれていることは非常に印象深いものでした。当時戦争中だったベトナムの高校生が目をキラキラと輝かせて生活をしていて、当時最も社会福祉が進んでいると言われたスウェーデンの老人たちが、ものすごく寂しい表情で過ごしている、という内容が書かれていて、一体人間の幸福って何なんだろう、という命題を突きつけられたんですね。
何となく心地いいことが幸せのように思い込んでいるけれど、実は、人間ってもっとややこしいものですよね。
最近は、子どもたちと仲良くしようみたいな教育書が多いですが、人が幸せになるというのは、そう簡単なことじゃない。それに、人が人を幸せにするなんて、ある意味傲慢でもあるわけじゃないですか。でもそこを仕事にすることの意義を、この二冊から感じました。

