「てびき」をキイワードに再発見する 伝説の教師 大村はまの国語授業づくり #6 生徒との会話から生まれた「ほめことばの研究」


日本教育史上突出した実践を展開し、没後20年を経た今も伝説として語り継がれる国語教師、大村はま。現役時代の教え子であり、その逝去の二日前まで身近に寄り添った苅谷夏子さんが、今、改めて大村はまの国語授業づくりの「凄み」を語る連載です。今回のテーマは、単元学習「ほめことばの研究」です。
執筆/苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長)
目次
「集める」という暮らし方
伝説の国語教師と呼ばれる大村はまは、その暮らしの日常に「ことばの材料を集める」という習慣が当たり前のように根付いていた。なにも専門的、本格的な「教材」と限ったことではなく、たとえば優れた辞書の編纂者が常にことばにアンテナを立てて過ごすのとほぼ同じような密度で、ことばの実態、ことばと人の暮らしの実際の姿を、興味津々で見つづけ聞きつづけ、集めつづけていた。「取材」といってもいいかもしれない。本はもちろん、新聞の4コマ漫画から店頭で交わされる会話まで、集めれば集めるほど、気づくこと、考えたいテーマ、新たな知見は蓄積し、ことばの世界の興味深さや豊かさは増す一方だったと思う。テレビを観ていても、商店街でも、通勤の途中でも、ふっと目や耳に入ることばの新鮮な一瞬は、子どもたちを率いてことばについて考える契機へとつながっていった。それは理論から出発して発想するよりも多様性や意外性、新鮮さをもっていて、よほど頼りになった。そして、ことばを育てる人として新鮮で多様な材料を持つことは、そのまま教室をいきいきとしたものにする、という現実に裏打ちされた実感があった。これは、伝説の大村はま国語教室から受け止めたいことがらの一つだろう。
大村は著書の中でこういう言い方をしている。
「いい題材に出会うには、ずっとつづけて興味をもって求めているということが大切ではないかと思います。網がずっと張ってあるので、ある日の材料がひっかかりますけれど、ひっかかる瞬間に合わせて網を張るということは、まずできないでしょう。」
「網の目が粗くては、とらえたものも粗いだろうと思います。」
ある日、網にかかった心躍るようななにかは、いつわらざる喜びと共に教室で披露され、生徒を惹きつける。このことは、おそらく国語教育というジャンルに限ったことではないだろう。理系でも、歴史や社会といった分野でも、もちろん外国語などでも、決まった内容の学習という固い枠組みの中に新鮮な空気を呼び込むのは、教師がその手で集めてきた、教師本人も嬉しくなるような「とっておきの材料」が加わる時なのではないだろうか。それを大村は「今日の新鮮な一滴が必要」という言い方で伝えようとしている。
生徒も集める人になる
ずっと網を張ることの苦労と大切さ、だからこその収穫の喜びと手ごたえを知っている大村は、その実感をもとに、生徒たちにも「集める」ことを促した。たとえば新しく知ったことばを集める、好きなことばを集める、読みたい本を集める、新刊書の広告を集める、ふと気になった表現を集める、好きになれないことば、問題だと感じることばを集める、作文の題材を集める、広告に躍る外来語を集める、自分のテーマを決めてそれにまつわるあれこれを集める……そんなふうに、大村教室の生徒はよく何かを集めて過ごした。
集める、ということは、やろうと思えば少しずつでも実行できるし、目に見える形で成果が積みあがるから、達成感も得られた。勉強しなさい、よく考えなさい、という指示よりは、〇〇を集めてみようと言われる方がよほど明るく受け止められた。収集ということは、一度味わいを覚えると楽しいものだ。クラスを率いる大村自身が根っからの「集める人」だったからこそ、生徒の収集を見守る人として最適だった。見守られながら、励まされながら、一緒に喜び合いながら、大村教室の生徒たちも「集める人」としてがんばった。そしてしばしば生徒の集めた資料は、優れたプランの元で新しい単元の材料となり、魅力的な研究(そうだ、大村教室の生徒は自分たちのやっていることを、「研究」という意識でとらえていた!)に結晶していく、それを構想するのは大村の得意とすることだった。外から与えられた整然とした既製品の材料で学ぶのとは、まったく別の味わいが、教室に生まれた。


「ほめことばの研究」その着想
さて今回、取り上げるのは、1974年2月に卒業を控えた中学3年生が取り組んだ「ほめことばの研究」という単元だ。この単元は、前年春、いよいよ高校進学を一年後に控えていろいろ心配もし始めた新3年生と大村の休み時間の会話から始まったという。進学の際の資料として中学校から指導要録とか内申書などと呼ばれるような書類が用意されるが、その中に一行、担任がことばで記入する人物評定という欄がある、という話が出て、次のような会話が交わされたそうだ(以下は全集『大村はま国語教室』第9巻より)。
大村(略)ひと言書くことになっているんですよ。空欄にしておくことはいけないということになっているんです。
◯ ぼくなんか、とっても、いろんなこと、書かれていると思う……・
〇 そんな、一つ一つのこと、書くんじゃないんでしょう?
大村 まさか。(略)ほんとうにひと言ですよ。それに、そんなところに、一生にかかわるようなまずいことを、だいたい書かないものですよ。「気が強いな」と思えば「しっかりしている」と書くし、「少し気が弱いな」と思えば「やさしい」と書く。ですから、そこはだいたいがほめことばになるんです。
このことばが、みんなの関心を呼び起こした。「私の短所をほめことばで言うと?」「ぼくをほめことばで言ってください」としばらく賑やかであった。
話題が話題を呼んで、「わたしたちは、自分のことをどういう人と言われたいものだろうか、どういう人と言われたらうれしいだろう」ということになった。
〇 おもしろい人。
〇 おもしろい、なんて言われたいの?
〇 みんなを明るくする人よ。
〇 そういう場合はいいけれど、前にね、先生から、おとなはね、ちょっと変わってる、へんな人だと思っている人のことを(略)「おもしろい方です」って言うという話をきいたことがあるよ。
〇 でも、ユーモアのある人、ということもあるんでしょ。
〇 明るい人、です。
〇 あと、やさしい人、です。
〇 あら、「やさしい人」は「気の弱い人」と言うことでしょう?先生
大村 いえ、そういうこともある、という話ですよ。ほんとに「やさしい人」が、もちろんありますよ。
〇でも、ほんとにやさしいとつい……。
私はこの子どもの言いかけた意味がよくわかった。そしてこの雑談から、一つの学習を展開したいような、それができそうな気持が湧いてきて、胸の高鳴りを感じた。子どもたちは、なお次々といろいろのことばを出している。(略)
こうして、生徒たちの「こう言われたい」と思う好きなほめことばを中心に、「ほめことばの研究」という単元が立ち上がったのだった。
全集から引用した上記のやりとりは、録音ではなく、おそらく大村の記憶から書き起こされたものだ。非常に耳のいい、そしてことばを記憶に刻む力に優れた大村であったから、この会話はかなり実際に近いものだったと思われる。
ここに見えるのは、ことばをめぐってちゃんと目が覚めている人たちの正直な、くつろいだ、心からのやりとりだ。本気で話す気のない、建て前や役割上の決まったセリフのような会話ではない。たとえば、「ちょっと変わった人のことを『おもしろい方』というような言い方をする」とか、「やさしい人は『気の弱い人』ということ?」とか「ほんとにやさしいとつい……」と言い淀むなど、ことばにしっかりと目と心が向いて、考えようとしていることがわかる。こういう姿勢を、大村は立ち話の中でも生み出していたことがよくわかる。ことばに関して、大村はフランクであり、正直だった。それが国語教室を下支えしていたことがよくわかる。
そして、こうした流れが教室全体に共有され、「ほめことばの研究」のいわば生きた「てびき」になった。「てびき」はこのようにふと生まれるものでもあった。
「ほめことば」を集める
こうして構想された「ほめことばの研究」という単元のため、大村は夏休みの宿題として「ほめことばを集める」という課題を出した。日常生活の中から、自分がこうほめられたらうれしい、あの人をほめるのにこのことばがぴったりだ、というような表現を集めていく。用紙を準備しておいて、気づいたときにさっとメモを取るようにする。大村教室で鍛えられて3年生になっていれば、一つの課題を持って「集める」姿勢になることはできたはずだ。ただ、残念ながら40日ほどの夏休みの間、生徒たちは一堂に会する機会はなく、一人一人で動くしかない。教室で「集める人」どうしで交流したり、励まし合ったり、刺激し合ったりすることはできなかった。もっと大事なこととして、ボスである大村の期待の眼、見守り、励ます姿はそばになかった。それは大きなマイナスになっただろう。それでも生徒たちは、宿題を無視するわけにもいかず、「ほめことばを集める」という課題があることをどこかで意識しつづけ、アンテナは張っていたことだろう。
アンテナが立った時点で、たとえそれが夏休みゆえに少し遊び惚けたアンテナであったとしても、気にしているというだけで、ことばの見え方は微妙に変わってくる。これは、他のどの課題であった場合でも同じことだが、「集める人」には「集めていなかった時」とは違うものが見えてくる。そして、集めれば集めるほど、徐々に目が利くようになる。集めるのがどのような対象であっても、一旦、目が向き、集めるという姿勢に立ったとたんに対象は背景から徐々に浮き上がって見えてくる。気にしなかったときとは別物に変容する。そして、集める人は少しずつ見る目が育ち、新たな着眼点が育ったりして、一つ成長するのではないか。
ためしに、この連載を読んだあなたには、今から二日間でいいので、身の回りの「ほめことば」を本気になって集めてみていただきたい。おそらく読者の多くは教員をなさっておいでだろう。そして、教育の世界では「ほめること」は大切なこととされ、実際に何かにつけては子どもをほめていらっしゃるに違いない。けれども、どんなことばでどんなふうに、どんなタイミングでほめているか、それをはっきりと意識することはあまりないのではないだろうか。世の中で使われているほめことばは、意外に多いのか、少ないのか、ありきたりのものにしか出会わないのか、予想以上にほめことばは身近にあるのか、役立たずのほめことばもあるのか、一見ほめことばに見えなくても実際には確かにほめているということばもあるのか。どんなことばが相手の心にしっかりと届くのか。紙を一枚用意してほめことばを虚心に集めていくうちに、おそらく少しずつ、自分の使うほめことばの有り様になにがしかの気づきや感慨を持たずにはいられないのではないだろうか。「集める」ということにはそういう作用がある。だから、大村はまは生徒たちによくいろいろなモノを集めさせ、時間もかけ、「励ます」「楽しみに見守る」というエネルギーも注ぎこんだ。「集める」ことで自ら気づくことがきっとあるからだ。「集めていない人」にはわからないものをいつの間にか得ていく。
3年生の3学期に、いよいよこの単元の実践が始まる。 生徒たちによるほめことばの収集に、大村も少し加えたというが、
「網羅しようとはしなかった。これは専門的な、学問的な研究ではなく、ことばについての関心を高め、ことばに対しての感覚を鋭くするのが目的だからである。(略)とにかく、みんなの生活のなかで拾ったものでないと、その語の感じがとらえられておらず、それを説明して理解させるようなことばでは、今度のこの研究はできにくいからである」。 (前掲書より)
この目的意識や対象、方法の絞り込みはいかにも大村はまらしい。専門的な研究でないことを明確に見極め、目的にちょうどいい形に確かに据えている。そこには足りないというネガティブな意識も、未熟という無念さもなくて、目の前の生徒たちにちょうど適していることへの安心が大事にされている。
「ほめことば」を分類整理する
集まったほめことばは、大村と国語係の手によって分類され、そのうち一定以上の数の集まった6種類だけを取り上げることにした。時間の都合上、またグループ編成の都合上、全部取り上げることは無理だからだ。その6種類は次の通りだ。
第1群 努力している はりきっている がんばっている ファイトがある 打ちこんでいる 熱心だ ~の鬼 勉強家 努力家 がんばりや 一生けんめいやっている
第2群 りこうだ 賢い 頭がいい さえている 鋭い 勘がいい きれる 聡明 頭の回転が速い ぬけめがない 目から鼻に抜けるようだ
第3群 たくましい 強い しっかりしている たのもしい 頼りになる 勇気がある 勇敢だ 根性がある りっぱだ
第4群 明るい ほがらかだ 明朗だ おもしろい 陽気だ たのしい 愉快だ 快活だ 晴れやかだ にぎやかだ
第5群 やさしい あたたかい 親切だ 思いやりがある 温和だ 穏やかだ 人間味がある
第6群 元気だ はつらつとしている 活発だ いきいきしている 機敏だ 活動的だ はきはきしている てきぱきしている 活気がある
ちなみに扱わなかったものは次のようなグループだ。
A 気品がある 上品だ しとやかだ 礼儀正しい 行儀がいい
B まじめ 誠実 一生懸命
C 純真 すなお 善良 純粋
D あいそがいい かわいい 愛きょうがある かわいらしい 人当たりがいい
E 気持ちのいい きさく さっぱりしている
ランダムに集められたものを分類するという作業は、必ず興味深いものになり、思考の整理を進める上で有用なものだ。大村はさまざまな単元でそれを体験させている。しかしこの単元では時間的な制約などからそこに重きを置くことはせず、国語係と大村とで別途済ませている。このあたりも実践の整理の仕方という点で潔い決断と言えそうだ。
「ほめことば」をランキングする ―個人で、つぎにグループで―
こうして6群に分類された「ほめことば」を材料として、生徒は6グループに分かれ、担当の語群を研究することになった。その方法としては、まずは個人個人で10個ほどの対象となる「ほめことば」をじっくりと眺め、味わい、判断して、個人としてのランク付けをしていく。どのことばがより上位の「言われてみたい、価値の高いものか」「どのほめことばが好きか」という並べる作業をするのだ。小さなカード1枚に1語を書き、机の上で物理的に並べることで思考を見える形にしただろう。そういう作業は考えるということを地道に、しかし着実に支えてくれる。そうやって自分なりのランキングを作っていく。気づいたことはすかさずメモしておく。そして各自が自分のランキングを持ちながら、同じグループの仲間と意見交換をする。一つ一つことばを取り上げながら、自分の感じ取ったことをことばにしていく。たとえばこんな話し合いがあったという。
〇「おもしろい」―これは、ほら、少し変わっている人のことをかっこよく言うことばなんでしょ。
〇 そんなことないよ。「おもしろい」は「おもしろい」だ。ユーモアのある人のことだよ。
〇 この詩のおもしろさはどこにあるか、とか、ああいうのは、味わいが深いという意味だね。「おもしろい人」も味のある人という意味じゃないか。
〇 おもしろい先生―というと、味があるなんていうより、冗談を言ったり、授業中にも何度も笑わせてくれたりする先生のことじゃないか。
〇 おもしろい先生、というときは、絶対ほめことばでしょう。さっき出た、そのなんか変な、なんていう意味にはならない。
〇 「おもしろい」はやっぱりほめることばだと思います。ことに、先生の場合は、四角四面ではなくて、親しみやすい感じ。
〇 おもしろい先生、と続かないときは、少し複雑なわけね。
「おもしろい」が属する第4グループには合計10個のほめことばがある。それをこのように一つ一つ取り上げながら、より好ましいものの順に並べ、グループとしてのランキングをまとめていくわけだ。一つ一つに目を留めながら考えがめぐり、比較し、判断を下していく、その頭の動かし方自体がことばの感覚を磨く実習になっていくのがわかる。
ランキングという作業は、一見とても単純で、時には乱暴な判断を強いられるようにも思えるが、「結論が大事なわけではない」ことをしっかり頭に置けば、一つの思考実験としてたいへん有用であることがわかるのではないだろうか。並べて順位を付けようとすれば、一つひとつを注視せざるを得なくなり、さらには、自分の判断や価値観が問われ、自分の頭の中を覗き込むことになる。ここで忘れてはならないのは、生徒たちが既に時間と手間をかけて「ほめことば」を暮らしの中から集めてくるというプロセスを経ているということだ。ある下地を備えた人たちの集団なのだ。突然降ってわいた課題におずおずと取り組むのとは違うはずだ。そうした中でさらに他の人のつけたランキングと比べることによって、自分のものの見方やことばの社会的側面も見えてくることになる。
その後、グループ外の人を対象に、担当したほめことばについてアンケートを取り、それを集計し、分析し、発表する。分析の枠組としては、ランキングに男女の性差があるか、意味の狭さ/広さに傾向があるか、音から来る差は認められるか、などが想定された。そうやって6つの分野のほめことばについて研究し、発表会が開かれて単元は終わっている。
「集める」「分類する」「並べる(ランキングする)」「話し合いながら並べ直す」「分析する」というこの一連の学習は、そのプロセスのどこにも難し過ぎるところがなく、同時に、ことばに目を向ける体験を蓄積し、感覚を研ぎ澄まし、考えを整理する、という大事な頭の働かせ方を一貫して後押ししている。そしてそのレベルの高さを、ボスとしての大村が目立たぬ形でてびきし、保っていた。
――こうやって本気になって考えたときにだけ、力はつくのだ、と生徒が疲れた様子をみせるたびに大村は優しい顔をして請け合ってくれたものだ。

<大村はま略歴>
おおむら・はま。1906(明治39)年横浜市生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪市の諏訪高等女学校に赴任。その後、東京府立第八高等女学校へと転任。すぐれた生徒たちを育てるが、戦中、慰問袋や千人針を指導、学校が工場になる事態まで経験する。
敗戦後、新制中学校への転任を決め、後に国語単元学習と呼ばれるようになった実践を展開。古新聞の記事を切り抜いて、その一枚一枚に生徒への課題や誘いのことばを書き込み、100枚ほども用意し、駆け回る生徒を羽交い締めにして捕まえては、一枚ずつ渡していったと言う。1979(昭和54)年に教職を去るまで、単元計画をたて、ふさわしい教材を用意し、こどもの目をはっと開かせる「てびき」を用意して、ひたすらに教えつづけた。退職後も、90歳を超えるまで、新しい単元を創りつづけ、教える人は、常に学ぶ人でなければならない、ということを自ら貫いた。著書多数。
2005年、98歳10ヶ月で他界。その前日まで推敲を進めていた詩に、「優劣のかなたに」がある。
<筆者略歴>
かりや・なつこ。1956年東京生まれ。大田区立石川台中学校で、単元学習で知られる国語教師・大村はまに学ぶ。大村の晩年には傍らでその仕事を手伝い、その没後も、大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長として、大村はまの仕事に学び、継承しようとする活動に携わっている。東京大学国文科卒。生きものと人の暮らしを描くノンフィクション作家でもある。
主な著書に『評伝大村はま』(小学館)『大村はま 優劣のかなたに』『ことばの教育を問い直す』(鳥飼玖美子、苅谷剛彦との共著)『フクロウが来た』(筑摩書房)『タカシ 大丈夫な猫』(岩波書房)等。
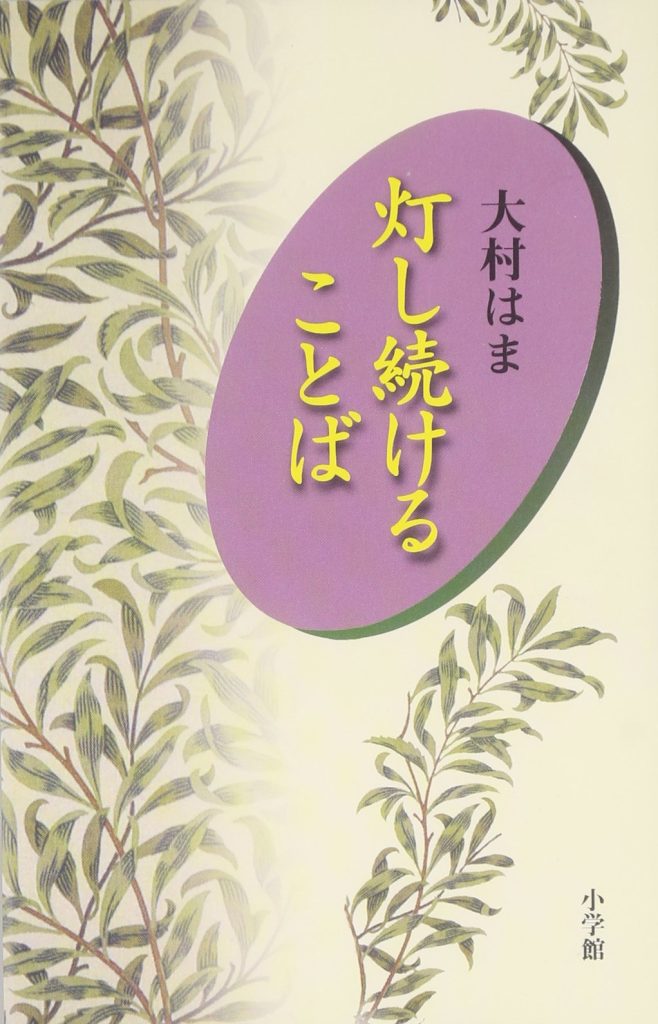
ロングセラー決定版!
灯し続けることば
著/大村はま
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はまの著作・執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てることに人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮されています。子どもにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて読んでほしい一冊です。(新書版/164頁)
大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。

