連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔― #6 国語的な科学、科学的な国語


日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌記者として3年間大村の担当をした記者が、編集者の目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す連載第6回。
執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)
目次
藤原正彦氏、川島隆太氏との対談から
年明け早々大病をして、札幌の病院に入院した。鬼の霍乱などという生やさしいものではなく、ほとんど人生の禊ぎとでも言うべき悪性の腎炎だった。しかしこの時もやはり日頃の性分というものなのか、国語について考えていた。「医療」と「言葉」ということを病床に在って考えているうち、「科学」と「国語」ということをいつの間にか考えていた。
入院していると、いつもは見えない時間が見えてくる。いや、正確にはいつも見ているのではあるが、その意味や輪郭がより鮮やかに見えてくるといったらよいのか? 世の中のパターンが見えてくるとでも言うべきか?
こういう時人は、無意識のうちにも、「科学的」「客観的」な言葉を「国語的」「情緒的」にも聴いているものである。逆に「情緒的」「感覚的」な言葉も、存外「科学的」「論理的」な情報として聴いているものである。つまり「国語的な科学」と「科学的な国語」は、我々の生活の中で、常に割と当たり前に共存しているのだ。ここからは国語、ここからは科学だなどというくっきりとした分水嶺などはない世界と言って良い。
数学者・藤原正彦氏と大村はま先生が対談されたことがある。氏は、新田次郎・藤原てい夫妻の次男であるが、母、藤原ていは、大村先生の諏訪高女時代の教え子であり、満州引き揚げ時代の実体験を描いた小説『流れる星は生きている』で有名。正彦氏も本業の数学の他にエッセイストとしても活躍されていて、『祖国とは国語』『国家の品格』など、そのタイトルを見るだけでも、国語が国造りの基礎だと考えられていることは明白だ。氏による「一に国語、二に国語、三四がなくて五に数学」のフレーズは、当時かなり世に普及した。
対談は、大村先生の誕生の地・横浜にある、ホテルニューグランドのマッカーサーズスイートで行われた。大村先生には少しでも、戦後のゼロ地点からスタートされた当時を思い出していただきたい、そういう出版社側からの配慮でもあった。
対談の朝、当時超過密スケジュールであった藤原正彦氏は少し遅刻されたが、それを詫びつつこう切り出された。
「大村先生はわが母藤原ていの恩師でありますから、国語教育の上では私は孫弟子にあたるわけです。先生の末流を汚すわけには行きませんので、今日はたいへん緊張して参りました。母に恥をかかせるわけにも参りませんし。」その一言で場が急に和んだことを覚えている。
様々のお話があった中で特に印象に残っているのは、藤原氏がこう言われたことだ。
「大村先生はもしや数学のセンスがおありではないかと思うんですね。というのは、何かのご著書の中で読んだと思うのですが、角度の1度は最初の根元のところでは小さいけれど、これが先まで行くと途轍もない広がりになる。だから教育は初めが肝心なんだと……」
それから自然に、数学と国語の関係の話となった。インドの数学の天才ラマヌジャンは、幼少時ほとんど正式な数学教育を受けていないのに、あれだけの数学的才能を開花させたのは、母が膨大な量の叙事詩『ラーマーヤーナ』を暗誦していたことと関係があるのではないか? それから当然、話は正彦氏と母上藤原ていとの関係に及んだが、詩人バイロンの娘が初の本格的な女流数学者であったことや、数学者アンドレ・ヴェイユとその妹の哲学者シモーヌ・ヴェイユ兄妹にも数学的才能と言語的才能が現れていることなどが話題となった。

大村先生はまた、脳の働きにたいへん興味をお持ちだった。
「あの頃東大に、時実利彦先生とおっしゃる脳の方の先生がいらっしゃったでしょ。私、一時懇意にさせていただいて、随分と脳のことを学んだものよ。何でもいいんですが、教案を作るとか、単元の準備をするとかそういう時に、これは脳の働きで考えるとどうか? 脳の働きで考えるとこれとこれは同じ事なのではないか? だとしたら関連づけてやってしまってはどうか?──とこう考えるわけ。
例えば、“話し合い”というのがあるでしょ。あれは、いわばお互いの気持ちを“読み”つつ話し合うのだから、“読み合い”なのではないか。いわば推理や洞察の脳の働きに関係するのではないか? と、こういう風に考えて進めていくわけです。
“読解力低下”の問題などにしても(※当時PISAの調査が日本の子どもの読解力低下を指摘していた)、すぐに『では読解問題をやりましょう』『読書時間を増やしましょう』とくる。しかし“読解”という言葉は、脳の働きから考えると、やや別の意味を持つわけです。」
大村先生は、当時東北大学の川島隆太教授が学習時の脳の活性状態をMRIで分析されていた事実にもたいへん興味を示されていたので、文部科学省の国語施策懇談会の席でご紹介し、お二人の2ショット(下写真)を撮影したこともある。中学の頃、作文の指導などをしてくださった川島治子先生と川島隆太先生の名前を挙げて、「私の人生の初めの方と終わりの方を飾る両川島先生ね。」などと冗談を言っていらしたことも懐かしい思い出だ。
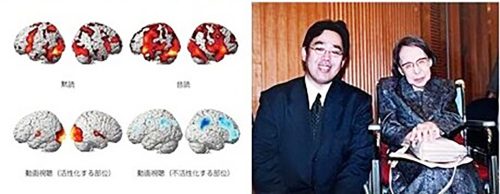
(右)その研究に着手した頃の東北大学の川島隆太教授と大村はま先生。文部科学省の国語施策懇談会にて。
バケツの水を捨てるようにして、書く
大村先生の授業実践の中で、こうした「脳」への視点が生きているのではないかと思われるものを二つだけ紹介する。一つはまず言葉の分類をする時のカードの使用である。分類する言葉をあらかじめ小さなカードに書いておいて、2枚ずつを取り出して見比べる。同じ意味・同じ用法だなと思えば重ね、違っているなと感じれば横に置く。こうすればまず自分の中での言葉の分類はできる。それから後、クラスや教師との質疑応答の中でそれを確認するという方法である。
もう一つは作文指導の方法で、先生はその指導法について語られる際、よく「バケツの水を捨てるように…」という言い方をされていた。掃除当番のある中学校生活が目に浮かぶようだが、生徒にはそんな風に実生活に則したわかりやすいたとえを使って話されていた。
「作文が書けない、書き出せないというのは、まず大抵は書くことが見つからないわけですね。書く素材が浮かんできていないんです。それなのに、これを書こうか書くまいかなどと一度に全体のことを考えるから、まとまるわけはないんです。頭の中から素材を掘り出すこととまとめることとでは頭の働き、頭の使う部分が違うんです。だから、書くか書かないか、いいか悪いかなどは一切忘れて、頭の中にあるものを端から全部カードに書いていくの。小さなカードに思いつくことを次から次に片っ端から。字なんて読める程度であれば多少乱れてもいい、点や丸も不要。とにかくその時は思いつくことに専念してスピードを上げてやっていく。こうして頭の中を出し切って、いっぺん空っぽにしてから、初めてまとめに取りかかるわけです。話が繋がりそうなカードは近くに置き、そうでないのはどんどん捨てていく。
これは私自身の経験から思いついたんです。
バケツの水を捨てるとき、ぐるぐる回すと底に沈んでいたゴミが浮かんでくるでしょ。その浮かんできた時にバッと捨てるとゴミが一気に出て行く(笑)。 そんな風に自分の知らなかったような自分の持っているものが脳の底から浮き上がってくるの。心の底に沈んでいる自分の大切な思想がね。ぐるぐる回していると自然に下の方の砂が上がってくるみたいにそれが目覚めてくるんじゃないかって、その時に生徒に教えたんです。一寸の玉を拾うためには、たくさんの捨てることがあるんじゃないかって。だから教室では、こんな大きなお菓子箱にそのメモのためのカードが年中詰まっていたんです(笑)。」
今から思うと、なんと合理的で、脳科学的な発想をされていたものかと思う。
大村先生という人は、常にこういう風に自分自身の経験に根ざした経験主義、合理主義、現実主義、実践主義を貫かれていて、教育的観念論や観念的教育論のカケラは微塵もなかった。「実践をもって提案する」ことをモットーとされ、常に研究者であることを必須と考えられた。
「研究者であるということは、ひとつの教師であることの資格だと思います。研究心というものから離れてしまった人は、私は、お年が二十代であろうが三十代であろうが、もう年寄りだと思います。」と言われた。
また、脳に関してはこんなことも言われた。
「とにかくまず、よき日本人になってほしいわね。だから、これはいい悪いじゃないんだけれど、外国語を使うと右脳の方が発達するんでしょ? けれど外国の人は、スズムシとか秋の虫なんか鳴いても、ちっともいい音と思ってないんですってね。やかましいって。いいとか悪いとかじゃなくて、日本人は日本人の感覚をやっぱり育てていってほしい。」

理系少女、大村はまの一面
先生は「百ます計算」の隂山英男先生と対談された時にもこんなことを言われた。
「私、数学が好きだったもので、数学の先生ともよくお話をした。……数学が好きだったわ。大好き、今でも。初めはね、博物の先生になろうと思っていたの。アヤメとか菜の花とかバラとか、そういう植物のことなんかおもしろいなと思って。けれど共立女学校の時にね、朝、玄関のところに青い目をしたかわいらしい犬がいたの。何てかわいい犬でしょうと思ったらそれは理科の先生が連れてきた、その日に解剖する犬だったのね。それで午後に理科室へ入ったら、そのワンちゃん、エーテルをかがされて眠ってた。それを見た時、理科をやればこういうこともやらなきゃいけないのかと思ってやめました。その理科の先生を私大好きだったけれども……。でも、本当に可愛い犬だった。」
まだ十代前半の大村先生のエピソードゆえ、やや他愛もない面もあるが、科学的とも言える大村先生の国語の根底には、理系少女大村はまのこんな一面もあったのかと思わせる。
近年、ニュースなどを観ていると、やたら「専門家は…」ということが言われ、専門家のコメントで落ちをつけたがる。しかし、近年起こっている様々の事象を観ていても、実質的にいわゆる「専門家」だけで解決していることは何一つなさそうである。コロナ騒動から一連の地球温暖化騒動、気象現象、山火事、米騒動、メガソーラー問題、クマの出没と駆除、侵略戦争、関税戦争、国連の機能不全……。枚挙に暇がないが、どの問題を考える議論もいわば個々の専門性に埋没していて、専門性相互間の学際的な対話や交流、弁証法が自在ではない。
大村はま流に言えば、日本人は相変わらず「話し合い」が下手であり、それに即した教育が施されていないと言える。すなわち、「科学的な国語」がいまだ熟していないと感じられるのだ。
<著者プロフィール>
よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、石川県金沢市生まれ。
札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。
小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在籍。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。
現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。
大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈有料動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。


