次期学習指導要領の論点整理について一緒に考えてみませんか? 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #21】

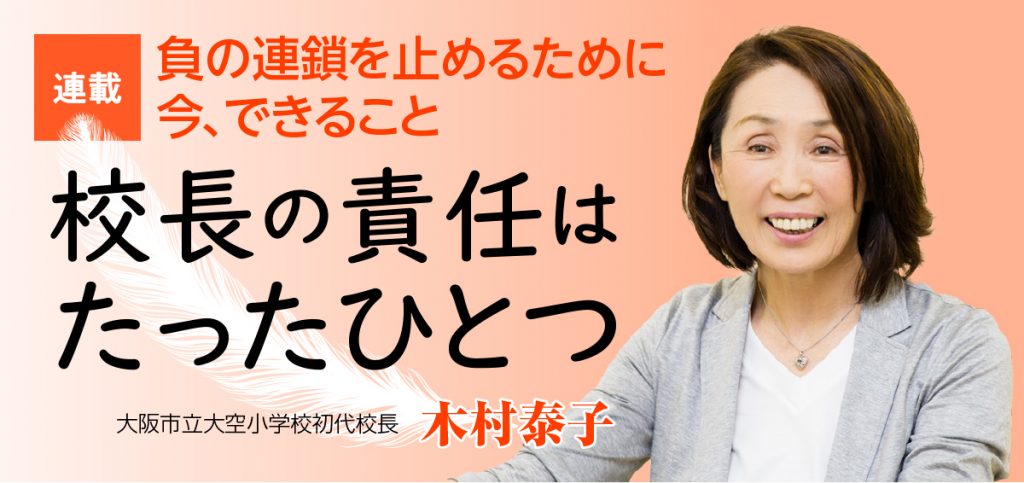
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。第21回は、<次期学習指導要領の論点整理について一緒に考えてみませんか?>です。
次期学習指導要領の3つの基本的な考え方
この夏はほぼ休みなく、全国の教育委員会や学校現場で学ばせていただきました。その経緯を踏まえて痛感しているのは、現場の先生たちが「主体性」と「当事者性」をもって次期学習指導要領の内容を理解し、その上で子どもに向き合えば、「自殺ゼロ・不登校ゼロ」が当たり前の学校づくりができるということです。
次期学習指導要領に向けた基本的な考え方として、中央教育審議会の教育課程企画特別部会から、以下の3点が提起されています。
生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を「みんな」で育むため、
1 「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
2 多様性の包摂(Equity)
3 実現可能性の確保(Feasibility)
の3つの方向性を踏まえて議論を行う。これらの3つの方向性に基づく改善は、教育課程内外のあらゆる方策を用いつつ、三位一体で具現化されるべきものである。
今回示された方向性は、現行の学習指導要領を現場に真に浸透させていくための内容です。それが達成されればどの子も安心して学校に通うことができ、「全ての子どもの学習権を保障する学校をつくる」校長のたった一つの責任が果たせることにつながります。
もちろん本来は現行の学習指導要領が示された時点で学校が変わっていなければならなかったのですが、現実はそうではありません。「子どもが主語の学び」が国を挙げて求められるようになってから6年ほどが経過して、大きく変革した学校ももちろんありますが、残念ながらそうではない学校がまだまだ多い現実があります。
「自殺・不登校・いじめ」過去最多を更新し続けている子どもの事実に真摯に向き合い、「学校を変える」本気の覚悟をまずは校長が持たなくては始まりません。
「1 『主体的・対話的で深い学び』の実装」を問い直す
この「主体的・対話的で深い学び」という文言が打ち出されて約10年が経つにもかかわらず、いまだに教室で子どもが全員椅子に座って黒板のほうを向き、先生が質問したら子どもたちが「はい」と手を挙げ、先生が指名した子が答え、その答えに対してみんなが「いいです」と反応する、という授業が行われている現実があります。この授業が「主体的・対話的で深い学び」ではないことは誰もが分かっているはずです。先生が主語になってゴールというワクをつくり、子どもをその中に入れようと必死で指導する。その中に入れない子に「不登校」「発達障害」とレッテルを貼り、結果的に子ども同士を分断してしまっています。
「主体的・対話的で深い学び」を真ん中に置いたら、どんな授業になるでしょうか。子どもが姿勢を正してじっと椅子に座って一斉に先生のほうを向いていては、子ども同士の対話を保障できるわけがありません。「きちんと座っている」「きちんと手を挙げる」「きちんと答える」ことを最優先に置いた授業は、戦後80年経っても何も変わりません。先生の問いに対して子どもたちが対話を始めれば、「教室がうるさい」「離席している」「規律を守らない」などと、指導を受けることで悩んでいる若い先生たちがたくさんいます。それぞれの学校現場もこのことは共有の困りごととされているでしょう。特に最近の学びを研究してきた若い先生たちが、現実との乖離に困り、悩んで現場を去ることも後を絶ちません。あまりにも残念な事実です。
この負のスパイラルを止めなければ「未来をつくる」学校の使命は果たせません。
「主体的」とは、一人一人の子どもが自分で考え判断し自分で行動することです。
「対話的」とは、子ども同士が自分の言葉で語り合うことです。
「深い学び」とは、子どもたちが10年後の社会で「生きて働く力」につながる学力をその子なりに獲得することです。
従前の授業形態を今なお高く評価している校長や教育委員会が現実に存在していることが不可思議ですね。
まずは校長が自校の子どもたちの授業を評価する目線を変えていかなければ、「主体的・対話的で深い学び」は言葉だけで終わってしまいます。

木村泰子(きむら・やすこ)
大阪市立大空小学校初代校長。
大阪府生まれ。「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに情熱を注ぎ、支援を要すると言われる子どもたちも同じ場でともに学び、育ち合う教育を具現化した。45年間の教職生活を経て2015年に退職。現在は全国各地で講演活動を行う。『「みんなの学校」が教えてくれたこと』(小学館)など著書多数。

