それ、もう“包括的性教育”です!【教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業】#4
小学校や中学校で性教育の指導に長年携わったスペシャリストである、帝京平成大学教授・郡吉範先生による連載「教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業」の第4回目です。この連載では、安心して実践できる基礎的・基本的なことがらやすぐに使えるヒント、ちょっと背中を押す言葉などをお届けします。第4回のテーマは「それ、もう“包括的性教育”です!」。学級活動における性教育とはどのようなことかを紹介します。具体例は、郡先生の経験や現場での実践に基づくものですので、現場でのヒントにしてください。
執筆/帝京平成大学人文社会学部教授・郡 吉範
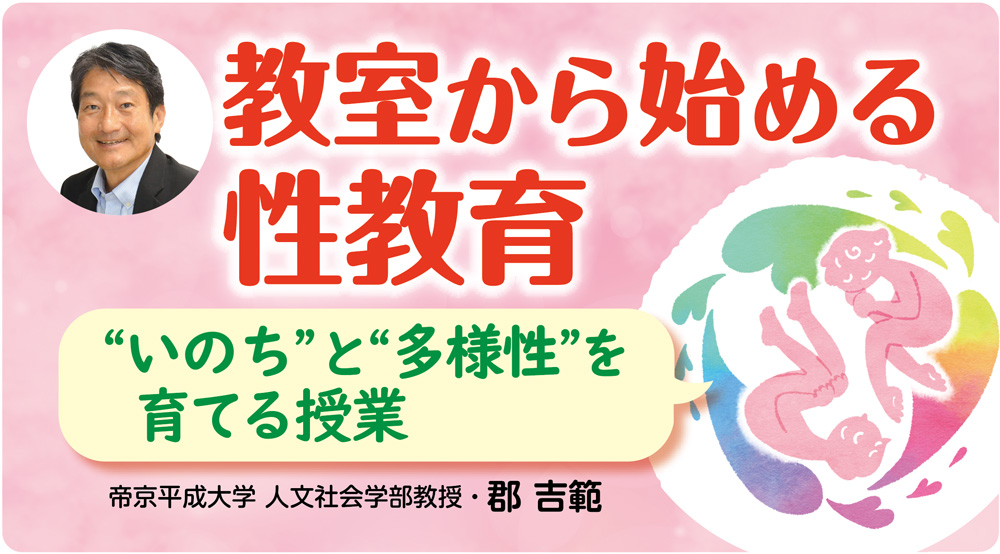
目次
“名前が付いていない”だけだった
ここまで読んできた先生の中には、「うちの学校の取組、意外とちゃんとしてない? これってもう“包括的性教育”ってやつなんじゃない?」
……そう感じた方もいるかもしれません。
――はい、それ、正解です。
実は、学習指導要領や日々の学級活動、教科を超えた連携など、日本の学校ではすでに“包括的な性教育”につながる取組があちこちで行われているんです。ただそこに、「包括的性教育」という名前が付いていないだけ。それなのに、こんな声がいまだに聞こえてくるのも事実です。
「日本の性教育って、身体の話だけでしょ?」
「人権? ジェンダー? そんなの学校で教えているの?」
……ちょっと待ってください。実際にはもっといろんなこと、やっていますよね?
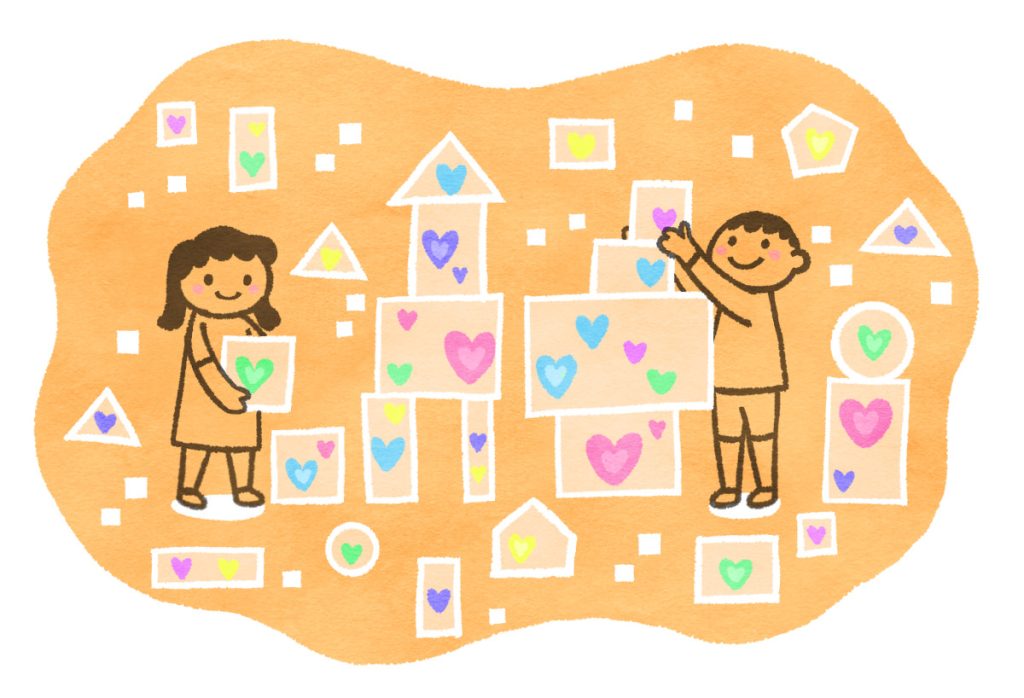
“やっているのに、やってないことにされる”問題
実際には、これまで多くの先生方が、授業や学級活動を通じて丁寧に性教育に取り組んできました。けれども現場のそんな努力が、「やっていない」「遅れている」と受け取られてしまうことが少なくありません。
その背景には、性教育の取組が“見えにくくなってしまう”構造があります。例えば、学習指導要領の中で性教育に関わる内容が複数の教科に分散しているため、全体像が把握しづらいこと。また、かつては教育委員会に提出していた「性教育全体計画」も、現在では任意扱いとなった地域が増えたことで、取組の“見える化”が難しくなっています。
さらに、「どの教科で、誰が、どんな形で実施しているのか」が明確に示されることが少ないため、外部からは取組の中身が見えづらい。そして何より、日々の実践や成果が記録や報告という形で共有・評価される機会自体が少ないのです。
こうした複合的な要因が重なり、結果として――たとえしっかり取り組んでいても、「やっていないように見えてしまう」
つまり、“やっているのに、やってないことにされる”という現象が起きてしまうのです。
実は、私自身もこうした“見えにくさ”の中で、いくつもの違和感にぶつかったことがあります。
• 「これは大事なんです!」と熱く語ったら、相手がスッと一歩引いてしまった。
• 「自分がやらなきゃ」と気負いすぎて、誰にも相談できなくなっていた。
• 「性教育って、〇〇先生の専門でしょ?」と役割を押し付けられてしまった。
当時は、伝え方がまずかったのか、自分の熱量が空回りしていたのか……そんなふうに思っていました。でも今になって考えてみると、これは性教育の全体像や意義が十分に共有されていなかったことから生まれた、自然なすれ違いだったのかもしれません。

