子ども同士のトラブルにどう向き合う?~未然防止の視点とトラブル後の対応ポイント~

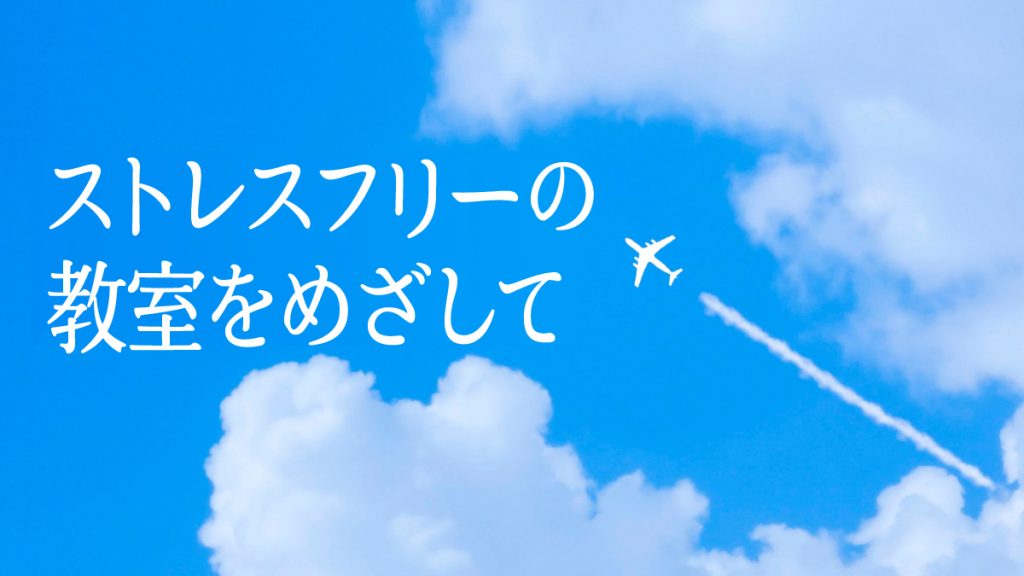
教室の中で、子どもたち同士の小さないさかいやトラブルは日常的に起こるものです。ちょっとした言葉のすれ違いや、遊びの中でのルールの不一致、無自覚な言動による心の傷つき……。それらは必ずしも「いじめ」とまでは言えないものの、関係性のほつれとして積み重なることで、子どもたちの心に影を落としてしまう場合があります。そこで今回は、子ども同士のトラブルに対し、①未然に防ぐための視点と、②起こってしまった後に関係を再構築するための対応について、実践的なヒントをお届けします。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #38
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
未然防止の視点① 信頼の土台は「日常のまなざし」から
子ども同士のトラブルは、突然に起こるようでいて、実は日常の関係性の「隙間」に生まれることが多くあります。その隙間を埋めていくものは、教師と子ども、そして子ども同士の間にある「信頼関係」です。
例えば、教師が子ども一人ひとりの名前をしっかり呼び、目を見てあいさつを交わすこと。何気ない一言に「ありがとう」「よく気づいたね」と返すこと。こうした関わりの積み重ねが、子どもの「自分はここにいていい」「見てもらえている」という感覚を育み、他者に対するまなざしにも波及していきます。
実際、教育心理学の研究でも、「教師からの承認経験」が子どもの対人関係に与えるポジティブな影響が示されています。信頼される経験をした子どもは、他者にも信頼を寄せやすくなります。つまり、教師の日常のまなざしが、学級全体の信頼関係の「土台づくり」になるのです。
未然防止の視点② 関係づくりを目的とした活動の設定
日々の教育活動の中には、意識すれば「関係づくりの場」になる瞬間が多くあります。例えば、当番活動や係活動、班での話合い活動などは、「協力」や「役割」を通じて相互理解を育む絶好の機会になります。
こうした活動においては、「ありがとう」「助かったよ」といった「感謝のやりとり」が自然に生まれることが大切です。先に述べたように、子ども同士に感謝のやりとりを生むためには、まずは教師がたくさんの感謝のメッセージを子どもに送り続けることが大切です。「いつも子どもの足りない部分が目に入ってしまう」という先生もいるでしょう。忙しい毎日ですから、気持ちはよく分かります。ただ、不思議と先生のイライラや焦りは子どもに伝わってしまうものです。先生の気持ちのゆとりは、イコール子どものゆとりです。指導したい気持ちをグッとこらえて、目の前の子どもの良さを認めてあげてください。「今日も(学校に)来てくれてありがとう」「笑顔が素敵だよ」といった言葉も、立派な感謝のメッセージですよ。

