運動会に向けて深めるクラスの絆~協働的な学びを生かす指導のヒント~

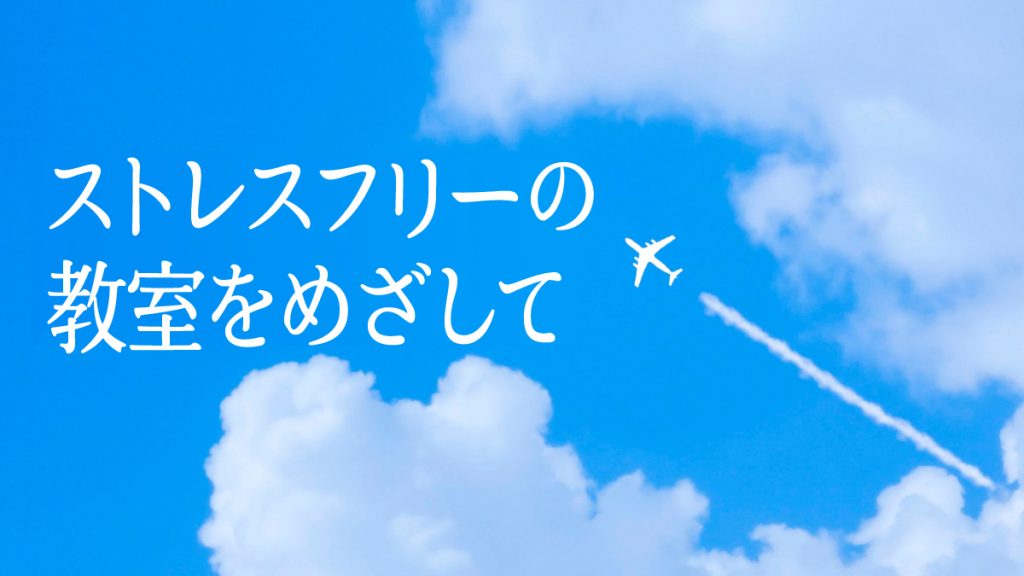
小学校の秋の一大イベントとして、運動会があります。運動会は、日々の体育の学習の成果を発揮する場であり、体力や技術を競うだけでなく、仲間と協力し合い、クラスの一体感を深める絶好の機会です。徒競走や団体競技に全力で挑む経験、応援や係活動で仲間を支える経験は、子どもたちの自己肯定感や他者理解を育む貴重な場となります。
しかし、運動会の本当の価値は、当日の結果だけでは測れません。むしろ、準備や練習の過程で「クラスの絆をどう深めていくか」が学級経営の大きなカギとなります。運動が得意な子も苦手な子も、誰もがそれぞれの役割を発揮できる雰囲気づくりを行うことが、運動会を成功へと導くための最重要ポイントです。そこで今回は、練習から当日、そして振り返りに至るまで、クラスの絆を深めるための指導のヒントを紹介します。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #36
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
運動会の教育的意義って?
コロナ禍では、運動会などの体育的行事も制限され、現在においても種目の削減や半日開催など、その影響が残っている学校もあるのではないでしょうか。しかしどんな形であれ、運動会は、ただ速く走る、力強く競技するだけの行事ではありません。そこには、学校教育において重要な価値が凝縮されています。
教育的意義その1「集団で協力する経験」
運動会は、クラスや学年全体で協働し、一つの目標に向かう体験が詰まっています。特に団体競技や応援合戦は、「仲間のために頑張る」「支え合う」ことの大切さを実感できる場です。自己中心的な思考から一歩抜け出し、集団の一員として活動する感覚を養うことができます。
教育的意義その2「達成感と成長の実感」
努力を重ねて成し遂げた経験は、子どもの中に「自分もやればできる」という自信を芽生えさせます。これは運動が得意な子だけではなく、苦手な子にとっても同じです。勝ち負けや順位よりも、「やりきった」という達成感をクラス全体で共有することが重要です。
教育的意義その3「学級経営への寄与」
運動会を通じてクラスに一体感が生まれると、その後の学校生活や学級経営に良い影響が広がります。練習の中で培われた声かけや助け合いの文化は、教室での学習活動や日常生活にも定着しやすくなります。
クラスの絆を深めるための準備段階
クラス目標の設定
学級会の時間などを活用して、運動会に向けた「クラス目標」を設定しましょう。「最後まで全力!」「お互いを応援!」「準備や係も手を抜かない!」など、全員が共有できる目標を設定しましょう。ここでクラス目標を設定することで、運動会終了後の事後指導に活用することができます。
係決め・役割分担
旗作り、応援用具の制作、記録係など、運動会全体の中では「裏方」とされる役割はとても重要です。なぜなら、運動が得意でない子も活躍できる機会が増えるからです。特に応援係や応援歌作りは、子どもたちの自主性や創造性を発揮できる分野です。教師主導ではなく、できるだけ子どもを尊重して準備を進めたいものです。
「する・見る・知る・支える」
運動が苦手な子には、まず小さな成功体験を積ませることが大切です。よく体育の学習では、「する・見る・知る・支える」という参加の仕方があると言われます。運動をするだけではなく、友達の活躍を見たり、競技の特性を知ったり、係として運営を支えたりすることも、立派な参加の方法です。たとえその子が運動を「する」のが苦手でも、「よく友達を応援しているね」「〇〇さんの放送、とっても上手だよ」といった、多様な活躍を認める声かけを行うと、運動会そのものへの苦手意識の緩和につながります。

