校外学習の班決めを、トラブルなくスムーズに決める方法!~クラス全員が安心できる学びの場を~

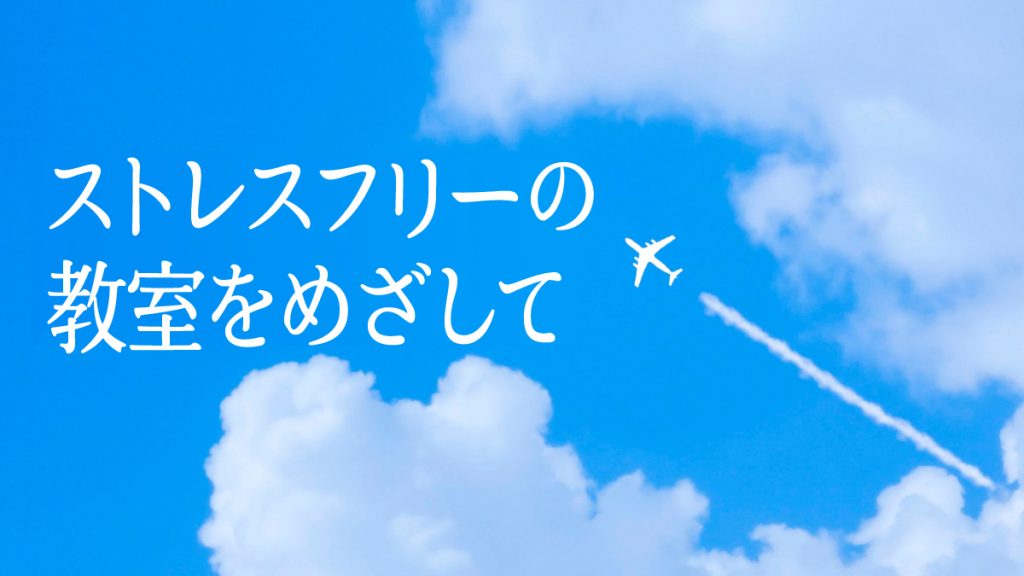
夏休みが明けると、遠足や社会科見学、宿泊を伴う修学旅行など、校外学習の実施が増えてきます。これらの行事は、教室を離れた場所で学びを深める貴重な体験であると同時に、友達との関わりを通して社会のルールやマナーを育む絶好のチャンスです。しかし、教師にとって大きな悩みの一つが「班決め」ではないでしょうか。
班決めは、子どもたちにとって楽しみであると同時に、不安や緊張を引き起こす場面でもあります。「仲の良い友達と同じ班になれるかな」、「一人になったらどうしよう」、「あの子とは一緒になりたくないな」などが大きな関心事となり、場合によっては人間関係のもつれやトラブルの引き金にもなります。特に、小学校高学年では友人関係のグループ化が進むため、班編成をめぐるトラブルが顕在化しやすくなります。
そこで今回は、班決めの背景にある子どもの心理を理解し、スムーズかつ公平感をもった班編成の工夫と、健康面や特別支援的な配慮を含めたポイントを具体的に紹介します。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #35
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
班決めと子どもの心理
班決めは単なる作業ではなく、子どもたちにとっては「集団内での位置づけ」を確認する場となります。そのため、以下のような心理的負担が生じる場合があります。
心理的負担その1「ひとりになったらどうしよう」
「ひとりになったらどうしよう」という不安は、多くの子どもが抱えています。特定のグループに入りたいという気持ちや、仲間外れにならないための焦りが、普段の人間関係をさらに複雑にすることもあります。そのため、子どもが「そろそろ班決めかな?」と感じると、先回りして特定の誰かと事前に「同じ班になろうな!」などと約束しているケースが生じる場合があります。
心理的負担その②「グループの力関係」
グループが決まっても、メンバー同士にいびつな力関係が働いていると、班の雰囲気が悪くなっていきます。自己主張が強い子と控えめな子がうまく共存できない場合、活動そのものがぎこちなくなります。特に、「班長」「保健係」など特定の係を決める場合には、力の強い子がそうでない子に係を押し付けてしまう場合があります。
心理的不安③「健康面・特性上の不安」
様々な理由で体力的にハンディキャップを抱えている子や、アレルギーなどの健康上の配慮を要する子は、「自分のせいで班が迷惑をかけないか」と不安を抱えがちです。また、発達の特性や対人不安をもつ子にとっては、班決めそのものがストレス要因となる場合があります。
スムーズな班決めのための事前準備
事前準備①「校外学習の目的を共有する」
班決めは「遊び仲間を決めるためのもの」ではなく、「学びを深め、互いに支え合うためのチーム作り」であることを、子どもたちにしっかりと伝えることが出発点です。活動のゴールが明確であれば、「仲良しグループ優先」ではなく「協力できるメンバーを組む」という視点に子どもも納得しやすくなります。
事前準備②「教師のサポート」
ここが教師の腕の見せどころです。日常の観察や授業の様子、発言の仕方などを通じて、子ども同士の関係性や相性を把握しておくことが何よりも大切です。特に、孤立傾向のある子、グループに入りづらい子が誰かを事前に把握し、班決めで孤立しないようにサポートします。場合によっては、学年主任や担任外の先生などに班決めの方針を相談し、担任だけでは収集しきれない情報を得ることも大切です。
事前準備③「健康面・特別支援的な配慮」
どんな校外学習であっても、子どもが安全・安心に参加できることが大前提となります。そのため、事前に保護者と連絡を取り、健康面や食事・アレルギー、医療的ケアが必要な子のニーズを把握しておきます。班のメンバー構成や活動計画の中で、無理なく参加できるよう調整します。特にアレルギー関係の配慮は、失敗が許されません。養護教諭や旅行先の担当者とも密に連携し、確実な方法を選びます。決断が難しい場合には、管理職の判断を仰ぎましょう。

