当番活動で責任感と協力心を育む『見える化と段階的自立』

新人教員のための学級安定実践13選③
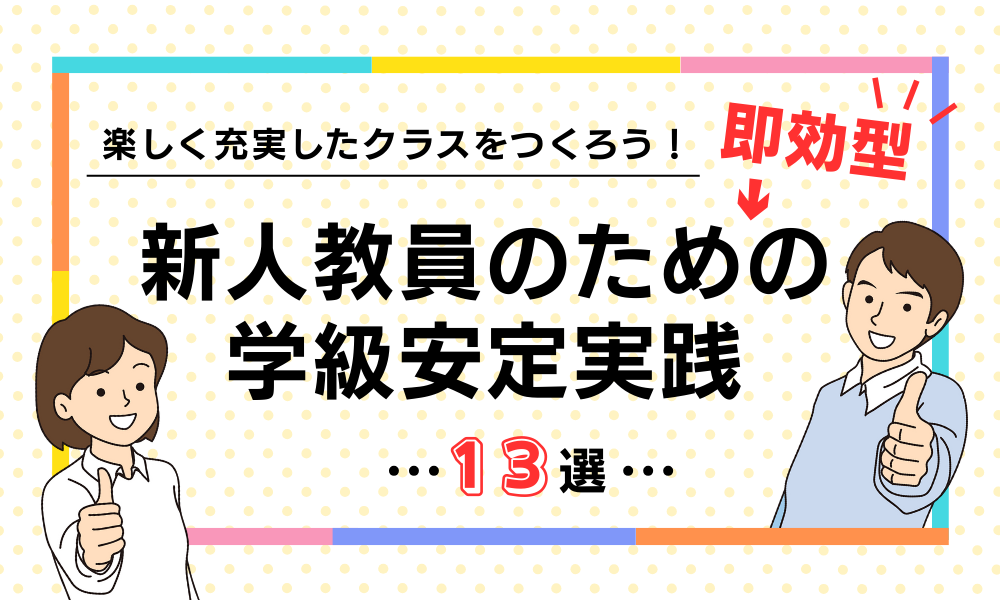
学級経営において当番活動は、子どもたちの責任感と協力心を育む重要な機会です。しかし、単に役割を振り分けるだけでは、子どもたちの主体性は育ちません。ただし、最初の段階では「誰がやるか分からない」状況では、教室は混乱してしまいます。当番活動を通じて子どもたちが自主的に学級を運営する力を養うには、明確な役割分担と段階的な自立支援が必要です。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
当番活動の本質:責任の可視化
当番活動初期導入段階で最も重要なのは「誰が何をいつまでに行うのか」を明確にすることです。ですから、一人一役で割り振るのがやりやすいと考えます。ただし、当番表に名前を羅列するだけでは不十分です。この仕事は、どのような仕事なのか、低学年であればしっかりとやって示すことが大切です。例えば、清掃における雑巾の扱い方などは、洗い方や絞り方、拭き方など全体の前で細かく一緒に行って確認することが大切です。
段階的自立を促す3つのステップ
当番活動で子どもたちの自立を促すには、段階的なアプローチが効果的です。第1段階では教師が具体的な手順を示し、一緒に行います。給食であれば「お手本を一つ作るから、その通りに入れてごらん」「この通路は一方通行です。ぶつかることを防ぐためです」など、やり方やルールをしっかりと固定します。このことにより、不慣れな子どもたちでも安心して取り組むことができます。
第2段階では、子どもたちが一人でできるよう見守りながら、必要に応じてサポートします。この段階では「困ったら声をかけてね」という安心感を与えながら、自分で考えて行動する機会を作ります。ルールも少しずつ柔軟にしつつ、様子を見ていきます。問題があったら全体の場で取り上げて共有をしていきます。
第3段階では、完全に子どもたちに任せ、結果について振り返りの場を設けます。「今日の給食当番はどうでしたか」「明日はもっと良くするために何ができそうですか」といった問いかけにより、子どもたち自身が改善点を見つけ、次への意欲を高めることができます。
この第3段階では、一人一役を少しずつ解除していきます。仕事とメンバーだけを伝え、子どもたちで行う仕事ややり方を決めさせます。ただし、この段階に移行するためには、クラスが十分に成熟している必要があります。
私は、配慮を要する子どもたちが多く、落ち着かないクラスを持っているときは、1年間一人一役だったこともあります。また、5月には第3段階に移行したこともあります。子どもたちの様子をよく捉え、実態にあった方法で少しずつでも主体性を育成する指導を行っていきたいものです。


著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

