ジグソー法を取り入れた「読むこと」の単元【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #45】
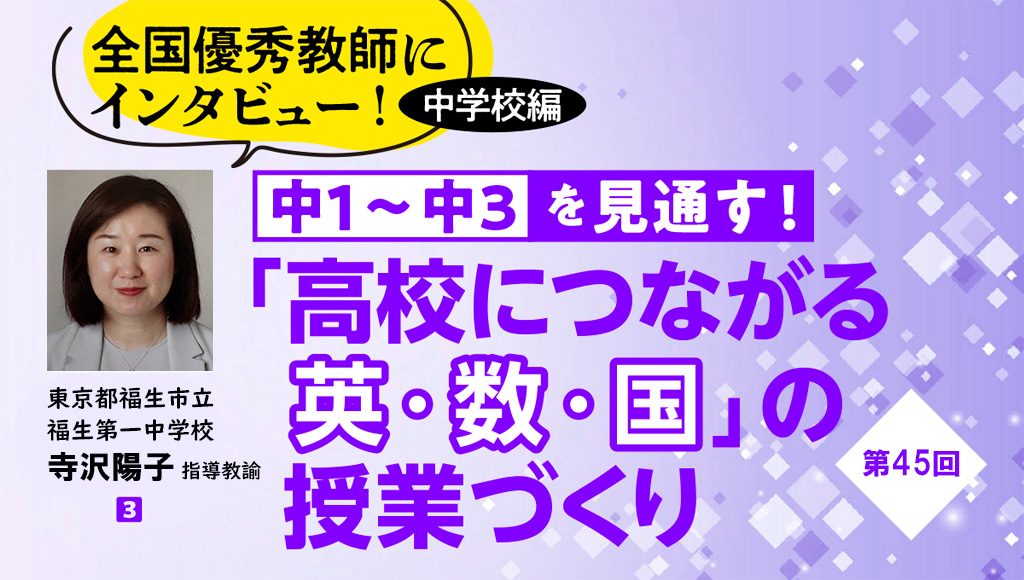
前回は、東京都中学校英語教育研究会がその指導力を高く評価する、福生市立福生第一中学校の寺沢陽子指導教諭(以下、教諭と省略)の単元・授業づくりの考え方や教育観について紹介をしていきました。今回は、その単元・授業づくりの考え方を象徴する、3年生「読むこと」の領域の単元、“A Mother’s Lullaby” の実践について紹介をしていきます。

寺沢陽子指導教諭
目次
読む目的を明確にするためにジグソー法
“A Mother’s Lullaby”は、ジグソー法を取り入れた「読むこと」の単元ですが、ジグソー法を取り入れた理由について、寺沢教諭は次のように話します。
「“A Mother’s Lullaby”の教科書本文は、広島市近郊にある古い巨木が、戦時中のことを回想するお話『かあさんのうた』と、元アメリカ大統領バラク・オバマ氏が同市の平和記念公園を訪れたときのエピソードとスピーチの抜粋を扱ったもので、完全な読みものの単元です。
ジグソー法を取り入れたのは、単純に長い文章を読むことへの負担を減らすという意図からです。そして何より、読む目的を明確にしたかったのです。人がものを読むときには、単純に自分の楽しみのために読むこともありますが、日常生活の中では、何か目的があって読む場合が多いのではないでしょうか。ですから、分けた4人グループの他の3人の友達に伝えるために読むという明確な目的を、それぞれにもたせたかったのです」
そのため、隣同士の2人とその後ろの席の2人の4人でグループをつくり、それぞれが教科書本文を4つに分けたうちの1パートを担当して読み、グループで共有していったのだと寺沢教諭。
「私のクラスでは、席の隣同士は英語が得意な生徒と苦手な生徒が並んで座るようにしています。1つ後ろの席は、その並びが逆になっており、4人でグループをつくると、英語が得意な生徒と苦手な生徒がそれぞれ2人ずつになるようにしてあり、そのグループで手分けして各パートを読んで共有していきました」
どのグループも英語が得意な生徒も苦手な生徒も混在する中で、それぞれの読みをもち寄って、全体の理解を図っていったというわけです。

