全ての子どもが無理しないで行ける「みんなの学校」をつくりませんか? 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #20】

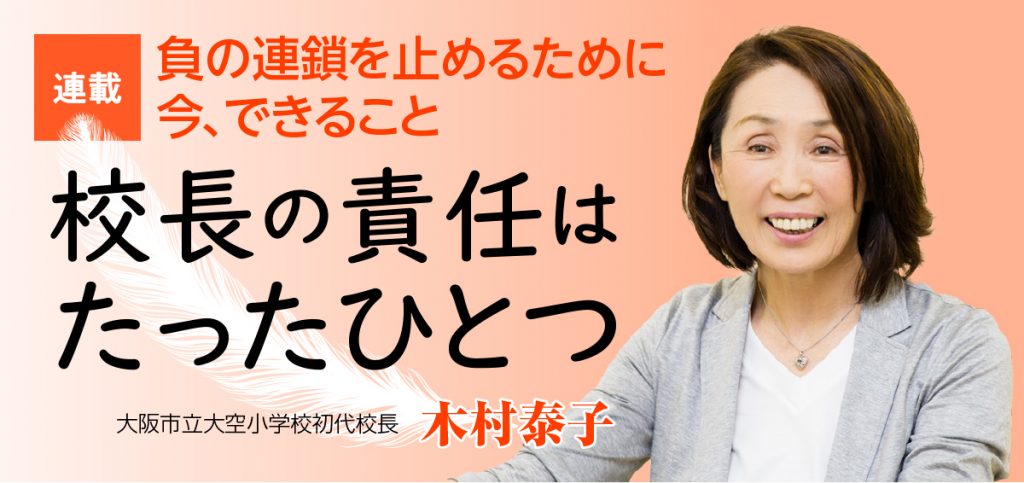
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。第20回は、<全ての子どもが無理しないで行ける「みんなの学校」をつくりませんか?>です。
20周年を迎えた大空小で
2025年6月7日に「大空20祭」が開催されました。2006年の開校から20年を迎えた大空小から学んだことは、「地域の学校」ここにあり! でした。
大空小での9年間は、毎月スクールレターを地域の回覧板に入れていただいて地域中のみなさんに読んでいただいていました。
校長としては毎月、こんなことをやっていますよといった、毎月違った内容で宣伝活動をしなければと思っていたのですが、教職員から「一番伝えたいことについて、これでもかこれでもかというくらい同じことを発信して、ようやく意識してもらえるのではないか」とアドバイスを受けたのです。確かに、この地域にできる学校には誰も行かないと、地域の人たちが20年間にわたって就学予定の保護者から署名を集め、教育委員会を糾弾していた地域です。大きな学校の地域と、新校が予定されている地域の地域格差がはびこっていたことが原因です。学校だけが育っても地域が変わらない限り、子どもの未来にはつながらない!
そこから、毎月毎月同じことを発信し続けました。
地域住民は「土」教職員は「風」
校長や教職員は、転勤や退職があり、何年かすれば地域の学校から移動しますが、地域住民は違います。地域の学校大空小がここにある限り、地域の宝である地域の子どもが育って10年後には地域を支える大人になるのです。教職員は「風」、地域住民は「土」です。
校長が変わったら学校が変わる、などという地域の学校をつくっていてはいけないでしょう。地域の宝は地域の力で育みましょう、と書き続けました。そのうち、地域の人が一人、二人とつながってきました。
地域の学校づくりの主語は「自分」です。
子どもは、自分の学校を自分がつくる
保護者は、子どもが学ぶ学校を自分がつくる
地域住民は、地域の宝が学ぶ学校を自分がつくる
教職員は、自分の働く学校を自分がつくる
自分がつくる自分の学校は全ての人が当事者になります。当事者になれば「人のせいにしない」空気が学校に生まれてきます。
これが「みんなの学校」です。
大人は全ての子どものサポーターです。主体的に学校に来て困っている子どもの横にそっといるだけでいい!
「大丈夫?」
「何困ってる?」
「私にできることある?」
この三つの問いかけだけで十分です。決めるのは子どもです。子どもはみんな違っています。これまで大人に問いかけられた経験が少ないので、黙っている子や「向こうに行け」と怒る子や逃げていく子がいることも当たり前です。どんな子どもが目の前にいても、子どもは大人の前の社会的弱者です。そのうち、子どもからそばに来ます。学校が安心できる場かどうかを決めるのは子どもです。 校長はいかに自校の「環境」を豊かにするかです。「指導」は一瞬で「暴力」に変わります。熱心な教員ほど、教員の自分が主語だ、との考えを変えられなくて困っています。

