英語が自分の世界を広げるための武器になってほしい【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #44】
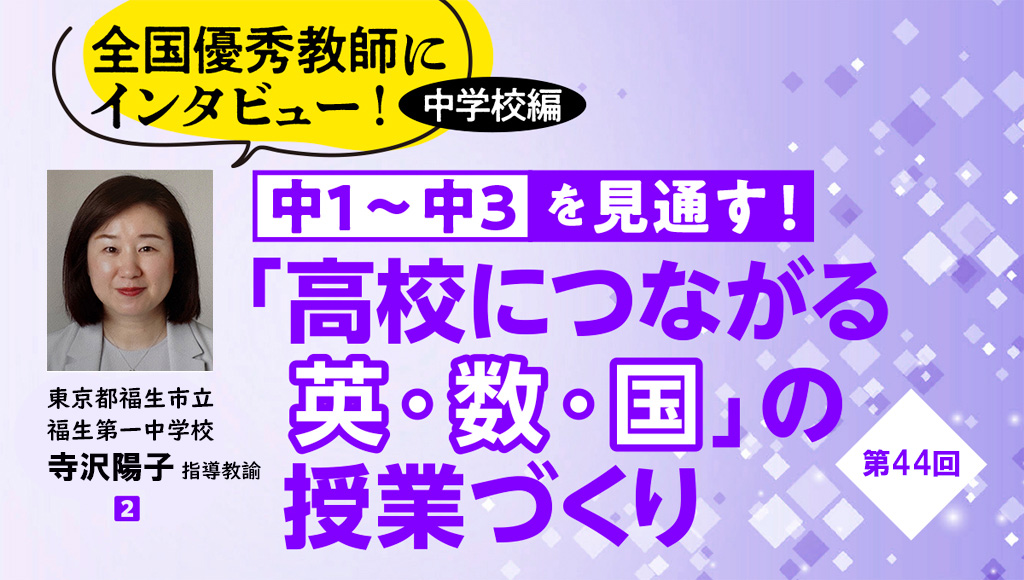
前回は、東京都中学校英語教育研究会が、指導力を高く評価する、福生市立福生第一中学校・寺沢陽子指導教諭(以下、教諭と省略)の3年生の「書くこと」の領域、“Animals on the Red List”の単元を紹介しました。今回は、そのような単元・授業の背景となる、寺沢教諭の単元・授業づくりの考え方について紹介をしていきます。

寺沢陽子指導教諭
目次
私が感じる「楽しさ」とは、「分かる」「できた」を積み上げていく「楽しさ」
まず寺沢教諭は、自身の英語教育に関する考え方について次のように話します。
「私は中学校の教員として、生徒の英語の学習は在学中の3年間で終わるものではないと思っています。中学校を卒業してからも英語に触れてほしいし、生徒たちが将来、社会に出て、生きていく上での多様な武器の中の1つになってくれたらよいと考えています。
もちろん、人にはいろいろな強みがあるし、必ずしも生徒たち全員が英語に関わる仕事に就いたり、英語を必要とする環境に身を置いたりするわけではないでしょう。しかし、幅広い国から多くの外国の方が来訪される今の日本の中で、英語を使うことに臆さず、『何か聞かれたら、ちゃんと答えますよ』『必要があれば自分のことも簡単に説明できますよ』と言えるような大人になってほしいのです。そうして英語を使って、多様な人と関わり、自分の世界を広げてほしいと思っています。
直接的な人との関わりでなくても、何かを見るとか、何かを読む場合に英語を一定程度使えれば、開く扉の数も増えていきます。もちろん、先のような人との関わりでも多様なチャンスが増えるはずです。そのための重要な道具の1つとして、強い武器であればよいと思います」
そのように、生きていく上で英語を使ってみようと思えるようにするために、単元や授業づくりに関して大事にしていることは、まず「楽しい」ことだと寺沢教諭は話します。
「英語を1つの武器にしていくためには、まずは『英語の学習は楽しい』と感じられることが大事です。そのため私は、まず自分自身が生徒だったら、どんな授業を『楽しい』と感じられるか、どんな授業を『受けたい』か考えて、単元・授業づくりを行っています。もちろん、『楽しい』には多様な種類の『楽しさ』がありますが、私が感じる『楽しさ』とは、ただ単に興味関心をひく『楽しさ』ではなく、『分かる』『できた』を積み上げていく『楽しさ』です。ある程度、時間経過と共に集中しながら、理解が深まり、『できた』という実感をもたせられるような単元・授業づくりを心がけています。
英語も日本語同様に言葉であり、言葉は生活の中で使う道具なので、生活や体験に密着していないと言葉を使う必要性が生じません。ですから、その単元で扱う語や文法事項を使う必要性が生じる使用場面や使用目的を考え、その単元で扱う言語活動を考えています。そのような場面づくりが大切で、私は生活の中のふとしたことで、『ああ、これ、あの単元で使おうかな』と考えるなどしています。
もちろん若い教員に、『日頃からずっと英語の授業のことを考えて、仕事中毒みたいに仕事をしなさい』などと言うつもりはありません。しかし、自分の生活の中での経験や思いが単元や授業に生かされ、それが生徒が主体的に学ぶ姿勢につながることがあるので、そういうことを楽しんでほしいと思います。
経験が少ないと、『忙しくなると授業を工夫する余裕がない』ということもあるかもしれません。経験に応じて授業を工夫するための引き出しの数に差があるのは分かりますが、やはり授業は妥協してはいけないところだと思います。教育を取り巻く環境はどんどん変わっていっていますから、少しでも余裕があるのであれば、どんどん教える内容や教え方を工夫し、アップデートしていきたいものです」


日常生活の中からヒントを得て、英語学習での使用場面や使用目的を考えるという、寺沢教諭の授業の様子。

