「学校給食による食育」とは?【知っておきたい教育用語】
文部科学省は、子どもたちの健康と豊かな心を育むために、学校給食の充実と学校での食育の取組を推進しています。子どもたちの食生活の乱れは、肥満・痩身や体力低下、さらには学力低下にもつながるのです。
執筆/文京学院大学名誉教授・小泉博明
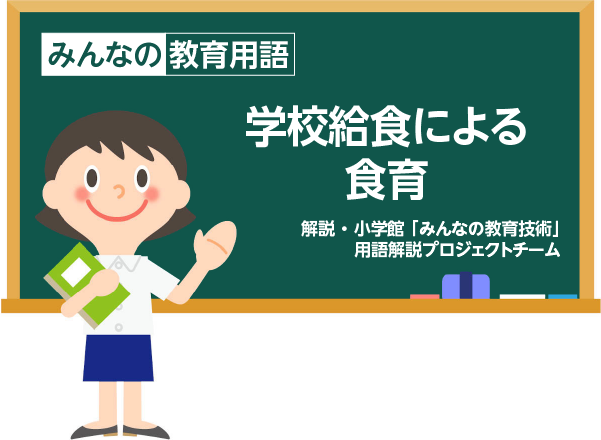
目次
食育とは
【食育】
生きるうえでの基本である「食」に関する知識と選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育てること。とくに学校給食は、食育における「生きた教材」とされ、食に関わる人々への感謝の心をもつことの大切さを教えるほか、地域の伝統的な食文化や、食料の生産・流通・消費などの学びにもつなげている。
偏った栄養摂取(偏食)、朝食を食べない(欠食)、一人で食べる(孤食)など、子どもたちの食生活の乱れは、子どもの心身の発達に影響を与えます。成長期の子どもに対する食育は、子どもが生涯にわたり健康に生きるための基礎になります。子どものときに身につけた食習慣は、大人になってからでは改めづらいです。子どもの頃からの食生活が生活習慣病の予防となります。
食育基本法(平成17年)と食育推進基本計画(平成18年)が制定され、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるために、学校において積極的に食育に取り組むようになりました。とくに、食に関する指導のなかで学校給食の役割が重要となります。食育で身につけることをまとめると、次の通りです。
●食べ物を大事にする感謝の心
文部科学省(ウェブサイト)「食べるが『価値』。」
●好き嫌いしないで栄養バランスよく食べること
●食事のマナーなどの社会性
●食事の重要性や心身の健康
●安全や品質など食品を選択する能力
●地域の産物や歴史など食文化の理解など
食育は、「食べ物を残さないようにしましょう」といった食への感謝の心を育てるだけでなく、栄養バランスや食事マナー、食文化に対する理解など、子どもたちの健やかな食生活、食習慣を形成するための役割も担っています。
学校給食と食育
学校給食は、学校給食法に基づき実施しており、成長期にある子どもたちの心身の健全な発達に資するものです。食に関する理解と適切な判断力を養ううえで、重要な役割を担います。
昭和29年に制定された「学校給食法」は、平成20年6月に改正され、「学校における食育の推進」が新たに規定されました。
学校給食は、成長期にある子どもたちの心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることに加え、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として、給食の時間はもとより各教科や総合的な学習の時間、特別活動などにおいて活用することができます。
とくに給食の時間では、準備から片付けの実践活動を通して、計画的・継続的な指導を行うことにより、子どもたちに望ましい食習慣と、食に関する実践力を養育することができます。また、学校給食に地場産物を活用したり、郷土食や行事食を提供したりすることを通じて、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深めるなどの高い教育効果が期待できます。
なお、学校給食の栄養管理については、「学校給食実施基準」(学校給食法8条)のなかにある「学校給食摂取基準」に基づき、子どもたちの健康の増進および食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出しています。
栄養教諭は、学校給食摂取基準に基づいた献立作成や、食事状況調査、残食調査などによる状況把握の実施によって適切な栄養管理を行い、その内容を指導に生かすことができるよう配慮することが求められています。また、学級担任は、栄養教諭と連携しながら、献立のねらい、栄養管理の状況を理解した上で給食の配食を行い、全体および個別の指導を行うことも求められます。

