子供が自分からどんどん話すようになるワザ~聴き手のあり方が、話し手の心をひらく~

「子供があまり話してくれないので、本当はどう思っているのかが分からない」――担任をしていれば、どんな先生でも感じたことがあるのではないでしょうか。では、子供が心をひらき、自分から話すようになるには、教師はどんな関わりをすればよいのでしょうか。特別支援教育の視点を取り入れた学級経営や、愛のある言葉がけで定評のある山田洋一先生が解説します。
執筆/北海道公立小学校教諭・山田洋一
目次
はじめに
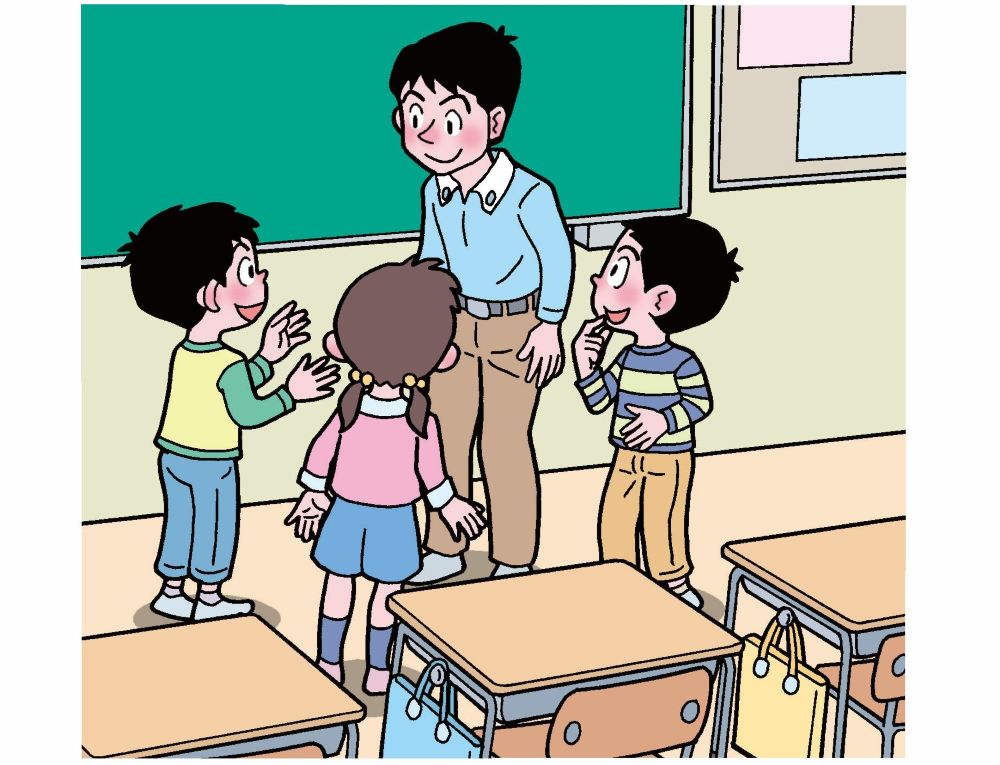
教室における「対話」は、子供にとっての学びを深める手段であると同時に、自己表現の力や人とのつながりを育む大切な営みでもあります。ところが、実際には、「子供がなかなか話してくれない」「反応が薄い」「どう関わればよいかわからない」――そんな相談を、若い教師から受けることが少なくありません。教師として、そうした場面に戸惑うことはむしろ自然なこととも言えるでしょう。
では、子供が「自分から話すようになる」ためには、どのような関わりが必要なのでしょうか。ここでは、その手がかりとなる3つの視点を紹介します。
視点1:話す力の土台は「話したくなる体験」にある
「話す力」というと、つい言葉を駆使するスキルばかりに目が向きがちですが、それ以上に大切なのは「話したい」「伝えたい」と思う気持ちが育っているかどうかです。
いくら国語の授業で「話すこと・聞くこと」の指導を丁寧に行ったとしても、それだけで子供が自然に話し出すようにはならないかもしれません。
特に日常の対話では、「話したことを受け止めてもらえた」「ちゃんと伝わった」と実感できる体験こそが、話す力の原動力になります。「話していいんだ」と感じられる安心感、そして、「通じた」という小さな成功体験、それらの積み重ねが、子供を話し手へと育てていくのです。
そのためには、まず教師自身が「聴き手」としての姿勢を整えることが欠かせません。
「それでどうなったの?」「びっくりしたね、もっと教えて」などの相槌や、「つまり○○ってことかな?」と子供の言葉を受け取って返す工夫は、子供の語りたい気持ちに火をつけます。うなずきや表情といった言葉以外の反応も、大きな励ましになります。
このように、日々のやりとりの中で「話したくなる体験」を丁寧に積み重ねていくことこそが、子供の言葉と思考を育む土台になるのです。

