日本を離れ派遣教師として子どもを教えるということ~UAE・ドバイより~
世界には在外教育施設派遣教師として、異国の日本人学校で教壇に立つ先生方が数多くいます。なぜ日本人学校の教師に? 赴任先の教育現場はどんな感じ? 日本の教育事情との違いは? ここでは、現地で活躍している先生の日々の様子をお伝えします。今回登場するのは2022年に赴任し、つい最近までアラブ首長国連邦・ドバイ日本人学校に勤務していた葛原孝紀先生。海外で教職の研さんを積みたいと考えているあなたへ、先輩教師からのメッセージです。
執筆/三重県公立小学校教諭(元ドバイ日本人学校教諭)・葛原孝紀
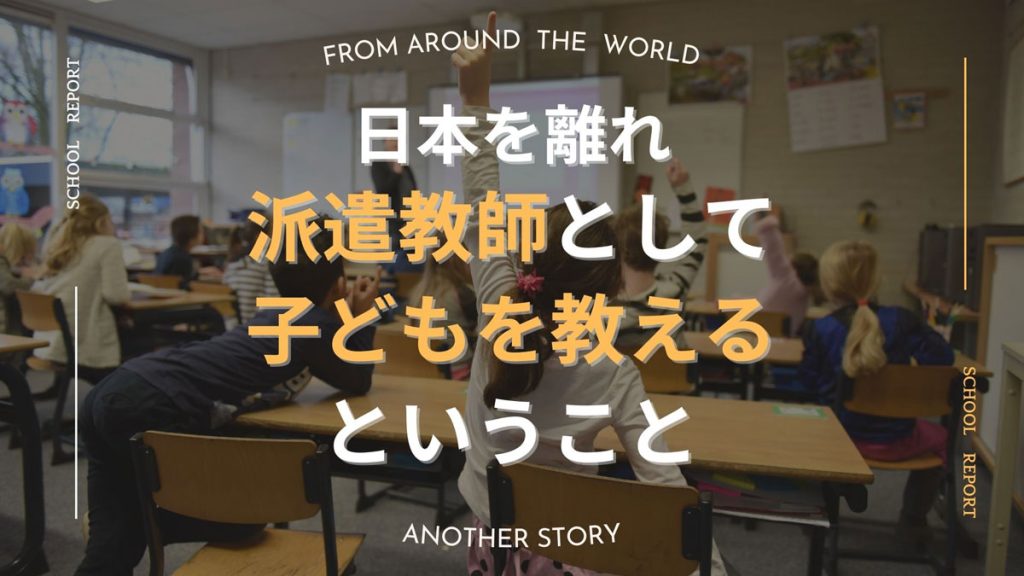
目次
海外に渡航経験のない自分が、日本人学校へ
実は、ドバイ日本人学校に赴任するまで、海外に対して大きな関心もなく、一度も海外へ行ったことがありませんでした。そんな私が、日本人学校を志すようになったのは、日本人学校で勤務経験のある先生方とのご縁があったからです。初めて講師として勤めた学校で先輩教師が「以前、日本人学校で働いていたんだ。本当にいいところだよ。君もめざすといいよ」と話していたことが、今でも記憶に残っています。正直、そのときは「そんなところもあるんだな」程度の認識でしたが、次の学校で初任者の私を指導してくださった先生も、翌年から日本人学校へ赴任することになりました。日本人学校と関わりのある先生方との出会いによって、次第に派遣教師への興味が高まっていきました。
しかし当時は、インターネット上での情報が今ほど豊富ではありませんでした(最近ではXなどのSNSで発信される先生方も増えてきましたが、当時は限られていました)。そんな中で「もし自分が日本人学校で働くことになったら?」という具体的なイメージを持つために、私が最も大切にしたのは、現役で勤務されている先生方から直接お話を伺うことでした。単に学校の雰囲気や仕事内容だけでなく、先生方が現在の職務で求められていること、勤務時間外のプライベートな生活、帯同されているご家族のこと、さらには先生ご自身のキャリアプランや仕事に対するスタンスまで、「一人の人間」としてどのように日本人学校での生活を捉えているのかを、じっくりと聞かせてもらう時間や場を積極的に設けました。
一人や二人の方のお話だけでは情報に偏りが出る可能性があったので、10人ほどの先生方と直接お会いしたり、Zoomなどを活用してオンラインでお話を伺う機会を設けたりしました。このような「人」との交流を通じて、日本人学校が本当に求めている人材像や、そこで働くことのリアルな姿について、私自身の「解像度」を飛躍的に高めることができました。机上の情報だけでは得られない、生きた情報と経験者の視点が、私の日本人学校をめざす道を明確にしてくれました。
その後、新型コロナウイルス感染症の影響で、全国一斉臨時休校になりました。その際も、ICT活用の可能性を信じ、子どもたちの学びを止めないために、企業からタブレット端末などを調達したり、オンライン授業を実施したりと、できることを一つひとつ行いました。日本人学校に勤務している先生からは「現地ではオンライン授業をするための機材もノウハウも足りなく、とても大変だ」という話を聞き、異なる環境で過ごす子どもたちの学びを止めないためにも自身の強みであるICTを活用して力を尽くそうと、派遣教師への受験を決断しました。
日本人学校の採用試験において、私が最も力を入れたのは「自分が日本人学校の子どもたちに、具体的に何ができるのか?」という問いに向き合うことでした。そのためには、これまで積み重ねてきた自分自身の教育実践を一つひとつ丁寧に振り返る作業が不可欠でした。「どんな指導が子どもたちの成長につながったのか」「同僚の先生方に、どのような良い影響を与えることができたのか」といった点を深く掘り下げていきました。
しかし、いざ自分の実践を客観的に整理しようとすると、意外にも難しいと感じました。そこで、私はすでに日本人学校で勤務をされている先生方に、自分の考えやこれまでの実践を積極的に伝え、フィードバックをいただく機会を設けました。その過程で、自身の教育の「軸」となる部分が徐々に明確になっていったのです。この「自分に何ができるか」という軸がしっかりと定まってからは、不思議なほど自信が生まれました。志望動機書であっても、論作文であっても、あるいは面接の場であっても、揺るぎない自信を持って挑むことができたのです。
ドバイ日本人学校の暑い暑い1日
ドバイは、中東のUAE(アラブ首長国連邦)にある1つの都市です。世界一高い超高層ビルのブルジュ・ハリファや、世界一大きい人工島のパーム・ジュメイラなどで有名な観光立国となっています。ドバイは年間を通して気温が高く、気温が43℃という日もあります。そのうえ湿度もとても高く、体感温度は50℃にもなります。猛烈な暑さのため、児童生徒の登校時間は午前7時30分と、朝のスタートはとても早いです。さらに、児童生徒の多くがスクールバスを利用し、1時間かけて通学している子もいます。朝がとても早いので、業間休みにはスナックやフルーツを食べるという「ドバイタイム」という時間があり、学校でスナックを食べるということに最初は驚きました。また、子どもたちは暑さに負けず運動場で遊ぶのが大好きで、休み時間が終わったら汗だくで教室に戻ってきます。


そんな、暑い暑いドバイ日本人学校は、G1〜9(小学校1年生から中学3年生)までが在籍する小中併設校で、全校児童生徒数は約200人。日本人学校の中では中規模の学校です。2023年当時、私はG6の担任に加えて、教科担任としてG5の理科、そして中学部の技術(情報分野)の授業も受け持っていました。中学部の技術の授業では教材研究やテスト作成など、免許外の授業ということもありとても大変でした。ただ、中学生への授業は、活動の質や思考の深さなど小学生とは異なるので、自身の指導においてとてもいい経験となりました。これは日本に戻った際の小中一貫教育などの取組に活かすことができるのではないかと考えています。
このほか、ドバイの公用語であるアラビア語やローカルティーチャーによる英会話の授業が週2時間ずつあり、7時間授業の日もあるので、児童生徒はとても忙しい毎日を送っています。ただし、金曜日は半日日課で12時頃下校します。というのも、イスラム教では金曜日にお祈りの義務があり、ローカルスタッフは午後に勤務をすることができないからです。そんな金曜日は、教員同士で一緒に昼食をとることができ、コミュニケーションをはかれるとても有意義な時間です。ただし、派遣教師は通常勤務のため、午後は職員会議や校内研究会を行います。
また、各都道府県から赴任してきた先生方と、教科指導・特別支援・生徒指導といったテーマを持ち寄って、1回15分程度のミニ研修が行われることもあります。お互いの強みを生かしながら主体的に学び合うことができるとても貴重な機会となっています。


