サボりや忘れ物が多い生徒への指導はどうする?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
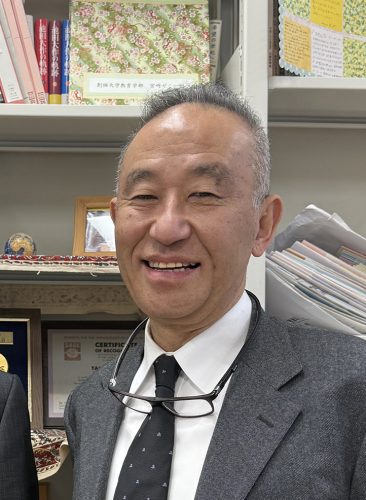

生活態度に問題のある生徒の指導は新任教師にとって、難しく感じる場面です。一人で抱え込まず、先生や保護者に連絡、相談しながら解決していきましょう。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#18
いくら注意しても忘れ物が減らない生徒。勉強にも支障が出るから何とかしたいけど……?
サボりや忘れ物など生活態度に問題がある場合は、「本人に指導をする」ことと「保護者に連絡して協力を求める」ことの2つの面からの対応が必要になります。一人で抱え込まずに、学年主任や生活指導主任の先生などに相談しながら対応しましょう。
目次
無断欠席をする子への指導
本人に指導する
連絡なく欠席をすることは、学校生活だけでなく、社会生活を送るうえで多くの人に心配や迷惑をかけ、信頼を失う行為であることを落ち着いて話します。その際、生徒の人格を否定するようなことを言ってはいけません。
<理由を聞く>
●なぜ無断で欠席したか、理由を聞くことが大切です。学校生活や勉強に対する意欲の欠如、人間関係の悩み、家庭でのトラブルなどを抱えていることがあります。
<約束する>
●欠席する場合は、学校に必ず連絡することを約束します。
<目標をもつ>
●悩みやトラブルを抱えている場合は、生徒の悩みを真剣に聞いて、目標をもち、一緒に解決策を探す努力をしていきます。

保護者に連絡し、協力を求める
事実を伝え、家庭の協力なしにはなかなか解決できないことを丁寧に話します。
<事実を連絡し、協力を求める>
●事実を伝え、欠席の連絡はできるだけ保護者からしてもらうようにお願いします。そして、生徒の成長を家庭と学校が協力して支えていきたいということを話します。
●高校では、単位取得にかかわる重大な問題であることをきちんと話します。
<家庭での様子を聞く>
●「友人関係が急に変わった」「いつもイライラしているなど」何か変わった様子はないか伺います。直接会って話を聞く機会をもつことも大切です。

無断での遅刻・早退・中抜けをする子への指導
●無断での遅刻・早退・中抜けに対しても、基本的には無断欠席と同じ対応をします。

●中抜けなどについては、管理職に連絡し、空き教員で生徒の居場所を探します。生徒が見つかったら二度としないよう注意するとともに、保護者に連絡をします。何度もくり返すような場合は、学年・学校全体で対応策を考えます。

忘れ物が多い生徒への指導
●なぜ忘れ物をしてしまうのか一緒に考えます(連絡帳を持っていない、プリント類を机の中に入れっぱなしにしている、生活が投げやりになっているなど)。
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

