小1特別活動「がっこうのきまり」指導アイデア

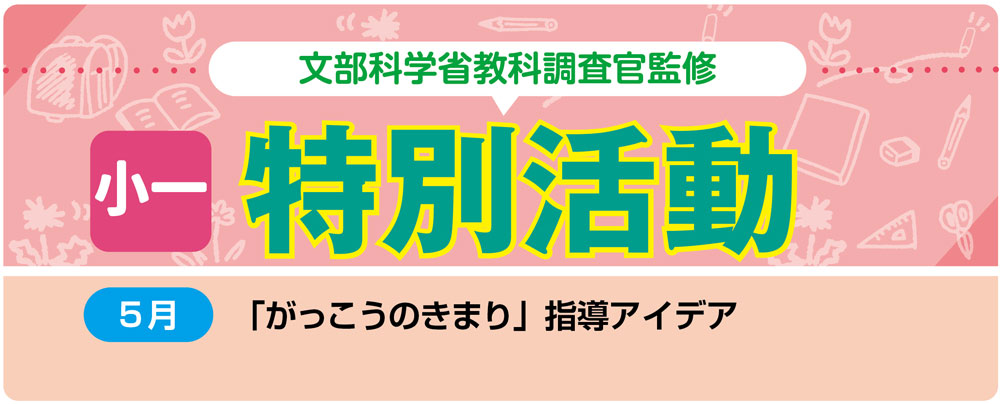
文部科学省教科調査官監修による、小1特別活動の指導アイデアです。5月は、学級活動(2)「がっこうのきまり」の実践の紹介をします。
「がっこうのきまり」という題材で話し合い、自分で取り組むことを決めて実践できることを目指します。
執筆/埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
監修:文部科学省教科調査官・和久井伸彦
埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
目次
年間執筆計画
04月 学級活動(1) なかよくあそぼうかいをしよう
05月 学級活動(2)ア がっこうのきまり
06月 学級活動(1) くらすのおしごとをきめよう
07月 学級活動(1) 1学期がんばったね会をしよう
09月 学級活動(1) すきなことはっぴょうかいをしよう
10月 学級活動(3)ウ 本となかよし
11月 学級活動(1) クラスのうたをつくろう
12月 学級活動(2)エ たべるのだいすき
01月 学級活動(1) クラスのすごろくをつくろう
02月 学級活動(3)ア もうすぐ2年生
03月 学級活動(1) 思い出集会をしよう
はじめに
入学してから2か月がたち、子供たちは学校生活に少しずつ慣れてきた頃かと思います。朝の始業前の時間や給食の配膳の時間、清掃の時間には高学年のお兄さん、お姉さんがサポートに来てくれるので、自分たちでできることが以前に比べてだいぶ増えたのではないでしょうか。ただし、学校生活の中でどうしても自分の思いが優先したり、自分で何に気を付ければいいかが分からなかったりする子供たちもいると思います。そこで、「がっこうのきまり」という題材で話し合い、自分で取り組むことを決めて実践できるようにしていきます。
「きまりを……」というと「教師が指示するもの」とイメージしてしまうこともあると思います。そのような捉え方で指導していると、「大人の顔色を見て行動する子供」を育成してしまうかもしれません。そこで、「きまり」は“道路標識のようなもの”と捉えてみてください。「こういう標識が出ているから守る」では、「急いでいるから……」「近くにおまわりさんがいないから……」ときまりを守らないことにつながってしまいます。
「この標識が出ているのはこういう意味があるから」と捉えることができれば、「急いではいるけど……」ときまりを守ろうとする意識が高まります。具体的な生活場面を伝えながら、危険であることの意味を理解することが大切です。

