よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第1回 指導主事の一日と教育公務員の特殊性

現場の教師にとって「指導主事」というと、ちょっと縁遠い存在で、具体的なイメージが持ちにくいかもしれません。しかし、実際に指導主事がどのような位置づけで、どんな仕事をしているのかを知ることは、公立学校を円滑に運営するためにとても重要です。新連載「よくわかる教育委員会~指導主事の仕事を中心に~」の第1回では、10年間の教育委員会事務局勤務経験を持つ西村健吾校長が、ある指導主事の一日の業務や、「教育公務員特例法」という法的根拠から「教育公務員」の特殊性と責任を解説。学校現場の先生方の仕事のヒントになるよう、指導主事の仕事ぶりを紹介します。
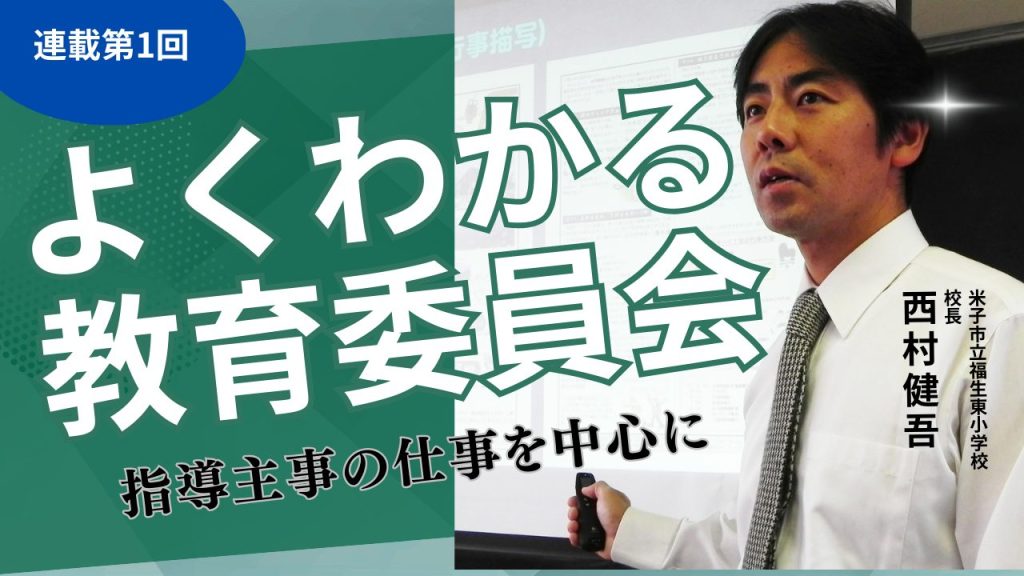

西村健吾(にしむら・けんご)
1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。
みなさんは「指導主事」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。「偉い人」「怖い人」「エリート」「指導助言する人」など、さまざまな印象があることでしょう。では、実際に指導主事が国の教育政策の中で、あるいは教育委員会の中で、どのように位置付いていて、どのような仕事をしているのかご存じでしょうか。
「指導主事の仕事なんか知っても……」と思われるかもしれません。しかし、指導主事の仕事や教育委員会について知ることは、実は公立学校を円滑に運営するためにとても重要なことであったりします。学校の運営は、一般の人が思うよりはるかに多くの根拠をもって成り立っているのですから。
指導主事や教育委員会について知ることで、
- 子供に対する教育の構えが情熱あふれるものに
- 校務を担ったり進めたりする心持ちが前向きなものに
- 保護者や地域住民への説明が説得力のあるものに
変わるかもしれません。
今回の連載では、幸か不幸か教育行政に10年も携わってしまった筆者が、教育委員会の仕事、学校との関わりといったことについて、指導主事の仕事を中心に解説していきます。学校の運営が年々難しくなっている昨今、連載の中で紹介する、艱難辛苦にまみれた(笑)指導主事の仕事ぶりを通して、学校現場の先生方の仕事上の何かしらのヒントをつかんでいただければ幸いです。
と同時に、「先の見えない道」に心ならずも足を踏み入れてしまった指導主事のみなさんの、「心の闇」を足元からぼんやりと照らす誘導灯らしきものになれば幸いです。
それでは始めましょう。
1分で分かるダイジェスト動画(試験運用中)
※動画は生成AIを利用した「NoLang」にて作成しました。
目次
ある指導主事の一日
先生方の「ヒント」「誘導灯」となるために、まずは、指導主事の仕事を知ってください。以下は、市町村教育委員会に勤務するある指導主事の一日です。日記風にまとめてみました。
始業時間や業務の名称などは自治体によって違うと思います。指導主事の一日の仕事のだいたいを知っていただき、新たな気づきがあれば幸いです。
午前8時:
働き方改革もあり、基本的には始業時間(8:30)までに登庁すればよいことになっているが、30分早く出勤。昨夜A中学校で施設が壊れていることが発見されたとの連絡があったため、今日はその報告を受ける必要がある。
報告の予定がない日でも早く来ておいた方が無難。天候不順やインフルエンザなど、学校に何かあったとき頼りにされる可能性があるからだ。
午前8時半:
始業時間。だいたい9時を過ぎると学校や外部からの電話がひっきりなしにかかってくる。そうなる前に自分に送られてきたメール、役所のイントラネットを確認しておかなければならない。ついでに当日のTo-Doリストをチェックする。漏れがないように、To-Doをリスト化しておくことが大事だ。しかし、時折漏れがあるのも事実。
午前10時:
ヤクルトさんがやってくる。毎日給食の牛乳を飲んでカルシウムを摂取できた教員時代と違い、委員会に来るとどうしても栄養が偏ってしまうので、とても助かる。
午前11時:
学校からの文書便がやってくる。とくに月初めは月例報告などが大量にやってくる。上司から「机上の乱れは文書紛失のリスクを高めるぞ」と言われているものの、なかなか整理ができない。
正午:
一日の中で唯一ゆったりできる時間。今日は同僚と役所近くの定食屋へ行った。弁当を持ってくる人もいるが、自分は外に出る方が気分転換になる。散歩や読書をする人もいる。リフレッシュの仕方は様々だ。
午後1時:
午後業務の開始。文書便の整理や、翌日までに学校に送らなければならない文書の作成などをする。学校からの提出文書は、すべて揃うのを待っていると作業が遅れてしまうので、届いた分だけを整理するのが大事。期日前に文書を出してくれる学校に感謝。
午後3時:
文書便のメールボックス前で、翌日発出する文書の袋詰め作業。このタイミングまでに文書の作成→稟議→決裁→印刷・丁合をしてボックスに入れなければならない。後で自分で入れることになると、その手間は大きいし、学校への文書到着が遅れてしまうことにもなる。
いつも「業務全体の見通しをもち、優先順位をつけながら文書を処理する」と心懸けてはいるのだが、なかなか。
夕方には地域の方からクレームの電話が入る。内容を記録し、報告しなければならないが、名乗ってくれないので困る。
午後5時:
終業のチャイムが鳴る。基本的に定時で帰りたいが、そうなることは稀。先輩の中には、定時でさっと帰宅して心と体をリフレッシュし、誰もおらず電話も鳴らない休日に集中して仕事を片付ける、という形で仕事を進めている方もいる。
庁舎を出て空を見上げると、満天の星がきれいだった。今日あった嫌なことはすべて忘れ、家には持ち帰らないようにしようと思った。
以上、ある指導主事の典型的な一日の仕事をご紹介しました。教育委員会には、これ以外にも本当に多くの仕事があります(詳しくは次回の記事で紹介します)。
それらの仕事内容を説明する前に、今回は学校や教職員が存在する根拠、すなわち法令等による裏付けについて説明させてください。これを知っておくと、学校や教育委員会の成り立ちがよく分かるからです。
まあ法令に関する話ゆえ、ここからはちょっと堅い内容になってしまうことをあらかじめお詫びします!

