授業時数【わかる!教育ニュース #64】
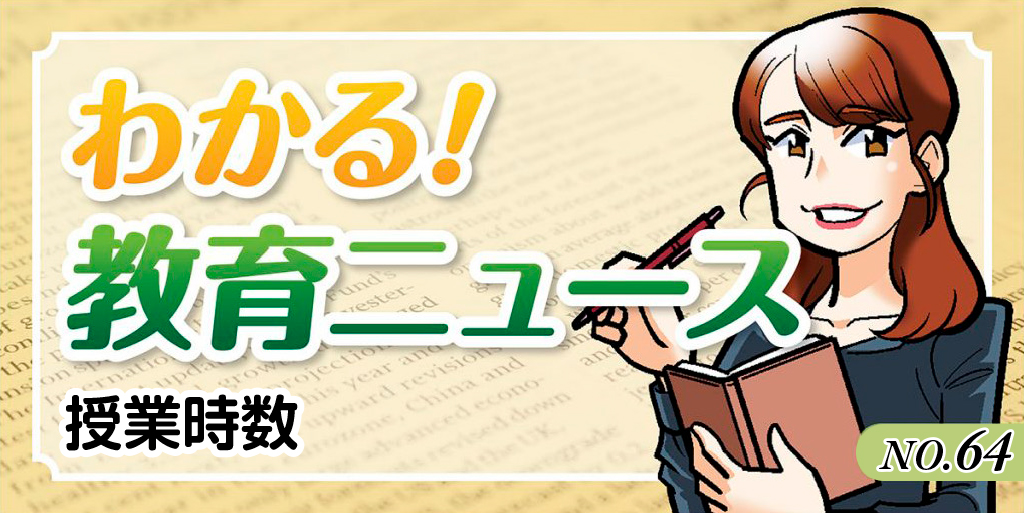
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第64回のテーマは「授業時数」です。
目次
授業時数を相当余分に確保しつつ、使い方をはっきり決めていない学校が4分の1
どの学年で何を教えるのかは、国が学習指導要領で定めています。そして、決められた学習内容を教えるために必要な授業のコマ数「標準授業時数」も、同様に示しています。でも、標準を超えた時数を見込んでいる学校は珍しくありません。
全国の公立小中学校がつくった2024年度の年間授業計画で、標準時数の1015コマを大きく上回る1086コマ以上の学校が、小5で17.7%、中2で15.2%に上ることが、文部科学省の調査で分かりました(参照データ)。22年度と比べて小5は19.4ポイント、中2も20.9ポイント減ったものの、まだ多いと言えます。
ただ、1086コマ以上の学校がどの自治体にもあるわけでもありません。小5の場合だと、北海道や静岡、高知など6道府県がゼロなのに対し、長野は53.9%、宮崎も49.3%と、大きな地域差があります。
なぜ1086コマ以上も見込んでおくのでしょうか。実は、具体的な使い道を想定していない学校が、小5で24.8%、中2も27.5%あります。
時数を相当余分に確保しつつ、使い方をはっきり決めていない学校が4分の1あることに、阿部俊子文科相は2月14日の会見で、計画した時数が本当に必要か精査を促すとともに、「教員の働き方改革にも大きく影響する」と述べました。3月4日の会見でも、重ねて同様の問題意識を口にしています。
理由がある場合、3割が学級閉鎖など不測の事態への備えを挙げました。文科省は「感染症などで時数が標準を下回っただけでは法令違反ではない」としていますが、学校にとって、時数が足りなくなることへの不安は根強いのでしょう。

