【木村泰子の「学びは楽しい」#35】「主体性」と「当事者性」を大切にした学びの場に!

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の35回目。今回は、「子どもの自殺」「不登校」過去最多の残念な事実を今年こそ止めるために、今私たちがすべきことについて考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
目の前の子どもの声を聴く
新たな年がスタートしましたね。みなさん、少しはリフレッシュできましたか。私は年末におせちをつくって、我が家(2世帯)の子どもたち(高校生と小学生)のリアルな姿を目の当たりにしていました。普段はあまり話す時間もないのですが、じっくり子どもの声を聴かせてもらえる貴重な時間を過ごしました。大人には分からない子どもの声はすべての子どもが秘めています。家族も学校も、案外分からないままに、正解を出そうとするのですよね。正解なんてないはずなのに!
昨年も全国の多くの子どもたちから学び、目の前の我が家の子どもの声も聴きながら、今年は子どもの「自殺」「不登校」過去最多の残念な事実だけは止めなくてはならないと決意して、この原稿を書いています。
社会では「無理して地域の学校に行かなくてもいいよ」とあちらこちらでささやかれ、そのことが当たり前になったかのような風潮があります。一方で「公教育の危機」とも言われ、公教育は崩壊した、ブラック企業だ、教員のなり手がない、教員のメンタルが壊れていくなどとメディアで毎日のように発信され、多くの人が「学校」に対する負のイメージを植え付けられてしまっているのではないでしょうか。
「子どもの自殺」や「不登校」は時代の流れではありません。子ども一人一人がそれぞれの理由や原因をもっています。ただ、「学校」はマジョリティーで、登校しない自分はマイノリティーと多くの子どもは思わされている現実があります。実はマジョリティーに合わせようとさせられることに必死に抵抗しています。自分を捨てない限り、マジョリティーには混じっていけないのです。だから、学校には行かない!
学校に来ていない子どもたちの声を学校の誰かが聴ける組織になっていることが不可欠です。
「学級経営」という言葉は捨てましょう
「子どもが主語の学校づくりを」と、これまでも伝え続けてきましたが、学校に来ていない子どもがいることは、学校に来ている子どもたちも育っていないことに気づくべきです。
「教員が主語」の時代に要求され続けたのが「学級経営力」でした。教員がどれだけこの力をつけることができるか、そのための研修も重ねられてきたのですが、それらの結果が残念な「子どもの事実」です。この結果を真摯に受け止め、学校の大人たちがこれまでとは違う「指導観」へと転換するしかないのです。
「子どもが育つ」事実をつくるのが教員の仕事です。
「主体性」と「当事者性」を優先に
前回も書きましたが、日本の学校教育の最大の課題は、「主体性」と「当事者性」の欠如だと言われています。
・自分の学校は自分がつくる
・自分のことは自分が決める
・人のせいにはしない
・この子が自分だったら……と想像する
・他者と適切に依存し合える関係性をつくる力が社会につながる
・他者評価より自己評価を大切にできるメタ認知能力を日常的に尊重し合う
・人と比べない
・人と自分の違いをリスペクトし合う
ここに挙げたことだけでも日々の学校での学びの上位目標に置くのです。数値で評価できない“子どもの「見えない力」”は、先生が指導することなどできません。一人一人違った自分をもつ子どもが、自分で自分をアップデートするしか手段はありません。先生の仕事は「支援」に徹すればいいのです。
一方、「主体性」と「当事者性」を阻むのは、「ヒエラルキー」「前例踏襲」「同調圧力」です。学校に蔓延しているこれらの悪しき学校文化に気づいたら、まず、気づいた人から捨てていくのです。
学級担任制の弊害
同様のことが職員室や学校の中で起きていませんか。
・指導力の競争になりサービスを提供しがちになる
・保護者の要求が過剰に増す
・子どもに失敗させなくなる
・学級担任の「アタリ」「ハズレ」をつくる
・一人の価値観しかない「ワク」の中で指導する
・人のせいにする子どもが育つ
・教員同士が対立する構図ができる
・自主的な子どもは育つが、主体的な子どもは育たない
・「自殺・不登校・いじめ」過去最多の原因になっている
「学びは楽しい」の原点に
「学び」は人を変えることではなく、自分をアップデートすることです。「すべての子どもの学習権を保障する学校づくり」のために、「教育」を「学び」に転換することが不可欠です。
まずは先生たちから学びを楽しむことです。学校は無理して来るところでも我慢するところでも自分を否定するところでもありません。
学びを楽しむ場です。
原点に立ち返りましょう。
〇子どもの自殺や不登校にはそれぞれ原因や理由がある。まずは子どもの声をよく聴こう。
〇学校に蔓延する悪しき学校文化を捨て、「主体性」と「当事者性」を大切にした学びの場をつくっていこう。
〇学校は「学びを楽しむ場」。子どもとともに学びを楽しみ、自分をアップデートしていこう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#34】対話を通じて学び合う環境をつくっていますか?
【木村泰子の「学びは楽しい」#33】子どもの人権について考えたことはありますか?
【木村泰子の「学びは楽しい」#32】現状に悩んだら、学校のシステムを抜本的に見直しませんか
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
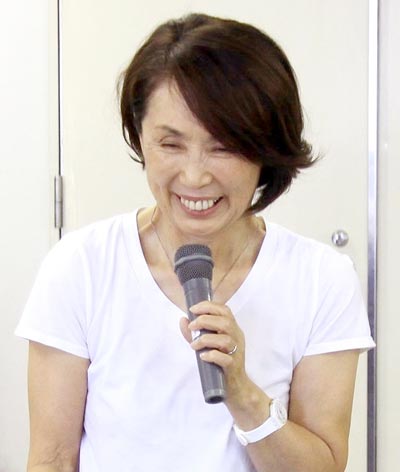
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、全ての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。

